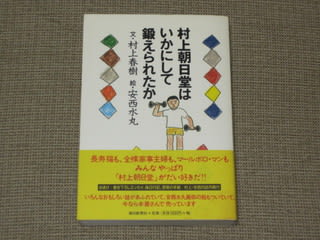文・村上春樹 絵・安西水丸 1997年 朝日新聞社
ということで、「村上朝日堂」なんである。
村上さんと水丸画伯が組むと、なんでも朝日堂みたいな気もするけど、これは「週刊朝日」連載エッセイなんで、ホントに朝日堂である。
いちばん初めの「村上朝日堂」に比べると、ひとつひとつのチャプターが、わりと長くて、読んでてしっかりとした手ごたえがある。1話完結の物語としても、十分な分量という感じを受ける。
で、なんで「鍛えられたか」なんてタイトルがついてるか知らないけど、この朝日堂では、いくつかシリーズものができていってる。
「梅竹下ランナーズ・クラブ通信」とか「空中浮遊クラブ通信」とか「全裸家事主婦クラブ通信」とか、いちど採りあげた題材に対して、読者からの反響があったりして、その続編が書かれる。
(ちなみに「空中浮遊クラブ通信」というのは、ヘンな宗教的修行すんぢゃなくて、空を飛ぶ夢をみる体験をもちよること。)
このあと、ホームページをつくって、メールで意見交換したり、同好の士が集まってクラブみたいの(「カラマーゾフの兄弟」を読むとかね)作ったりって活動があったらしいけど、この本がその嚆矢なんだろうかという気がする。
で、今回あらためて読み返してみると、意外なことに(私にとっては意外なことに)、この本のなかで村上さんは、けっこういろんなものに怒りをぶつけてる印象が残った。
たとえばテレビ番組での批評を理由に住宅ローンを断った銀行とか、自身の経験もふまえて、体罰を肯定する学校とか社会に対してとか。
全社一斉に休む新聞休刊日とか、ひとを外見で判断してせせら笑ったロンドンにオフィスのある航空会社とか。
事後承諾で全集の企画を持ってくる出版社の担当者とか、レジでちょうどの金額を支払ったのに「お預かりします」という店員の言葉とか。
法律で定められてるからエレベーターに車椅子用ボタンを設計はするけれど、利用者に無神経な注意書きをするデパートとか。
いろんなことに、わりとストレートに、怒りをぶつけてる。
で、最後の「おまけ」って章に、いま見て、ちょっとびっくりした一節があった。こういうこと書く人だったかと改めて感心したというか。
>世の中に「これからの二十一世紀、日本の進むべき道がよくわからない。見えてこない」と発言する人々がいるけれど、そうだろうか? 僕は思うのだけれど、現在我々の抱えている最重要課題のひとつは、エネルギー問題の解決―具体的に言えば、石油発電、ガソリン・エンジン、とくに原子力発電に代わる安全でクリーンな新しいエネルギー源を開発実現化することである。(略)
>でも技術的に原子力を廃絶できるシステムを作りあげることに成功すれば、日本という国家の重みが現実的に、歴史的にがらっと大きく違ってくるはずだ。「いろいろあったけど、日本はその時代やっぱりひとつ地球、人類のために役に立つ大きなことをしたんだな」ということになる。
…大きな地震があったからって、にわかに言い出したことではない、15年くらい前の発言である。
それはそうと、村上さんのエッセイとか読んでると、またそこからリンクが張られているかのように、買い物がしたくなっちゃう。
今回気になっているのは、ある日のコンサートで村上さんを癒したという、ピアニストのスヴィアトスラフ・リヒテルのブラームスの二番のピアノ協奏曲。
もうひとつは、生き生きとした例文が数多く出てきて、毎日ちょっとずつ読んで読破するのにふさわしいという、飛田茂雄氏の『探検する英和辞典』(草思社)。
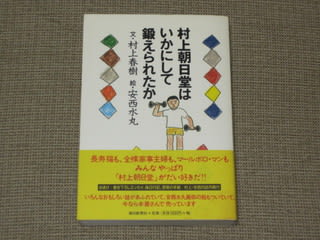
ということで、「村上朝日堂」なんである。
村上さんと水丸画伯が組むと、なんでも朝日堂みたいな気もするけど、これは「週刊朝日」連載エッセイなんで、ホントに朝日堂である。
いちばん初めの「村上朝日堂」に比べると、ひとつひとつのチャプターが、わりと長くて、読んでてしっかりとした手ごたえがある。1話完結の物語としても、十分な分量という感じを受ける。
で、なんで「鍛えられたか」なんてタイトルがついてるか知らないけど、この朝日堂では、いくつかシリーズものができていってる。
「梅竹下ランナーズ・クラブ通信」とか「空中浮遊クラブ通信」とか「全裸家事主婦クラブ通信」とか、いちど採りあげた題材に対して、読者からの反響があったりして、その続編が書かれる。
(ちなみに「空中浮遊クラブ通信」というのは、ヘンな宗教的修行すんぢゃなくて、空を飛ぶ夢をみる体験をもちよること。)
このあと、ホームページをつくって、メールで意見交換したり、同好の士が集まってクラブみたいの(「カラマーゾフの兄弟」を読むとかね)作ったりって活動があったらしいけど、この本がその嚆矢なんだろうかという気がする。
で、今回あらためて読み返してみると、意外なことに(私にとっては意外なことに)、この本のなかで村上さんは、けっこういろんなものに怒りをぶつけてる印象が残った。
たとえばテレビ番組での批評を理由に住宅ローンを断った銀行とか、自身の経験もふまえて、体罰を肯定する学校とか社会に対してとか。
全社一斉に休む新聞休刊日とか、ひとを外見で判断してせせら笑ったロンドンにオフィスのある航空会社とか。
事後承諾で全集の企画を持ってくる出版社の担当者とか、レジでちょうどの金額を支払ったのに「お預かりします」という店員の言葉とか。
法律で定められてるからエレベーターに車椅子用ボタンを設計はするけれど、利用者に無神経な注意書きをするデパートとか。
いろんなことに、わりとストレートに、怒りをぶつけてる。
で、最後の「おまけ」って章に、いま見て、ちょっとびっくりした一節があった。こういうこと書く人だったかと改めて感心したというか。
>世の中に「これからの二十一世紀、日本の進むべき道がよくわからない。見えてこない」と発言する人々がいるけれど、そうだろうか? 僕は思うのだけれど、現在我々の抱えている最重要課題のひとつは、エネルギー問題の解決―具体的に言えば、石油発電、ガソリン・エンジン、とくに原子力発電に代わる安全でクリーンな新しいエネルギー源を開発実現化することである。(略)
>でも技術的に原子力を廃絶できるシステムを作りあげることに成功すれば、日本という国家の重みが現実的に、歴史的にがらっと大きく違ってくるはずだ。「いろいろあったけど、日本はその時代やっぱりひとつ地球、人類のために役に立つ大きなことをしたんだな」ということになる。
…大きな地震があったからって、にわかに言い出したことではない、15年くらい前の発言である。
それはそうと、村上さんのエッセイとか読んでると、またそこからリンクが張られているかのように、買い物がしたくなっちゃう。
今回気になっているのは、ある日のコンサートで村上さんを癒したという、ピアニストのスヴィアトスラフ・リヒテルのブラームスの二番のピアノ協奏曲。
もうひとつは、生き生きとした例文が数多く出てきて、毎日ちょっとずつ読んで読破するのにふさわしいという、飛田茂雄氏の『探検する英和辞典』(草思社)。