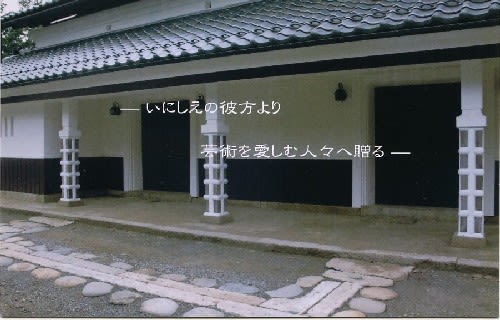あじさい「アナベル」 大輪のアジサイはあまり好きではないが、白だからまぁOK

先日の報道で知った知識
じゃがいもで食中毒をおこすことがあるそうだ。知らぬは私だけかいな?
昔から梅雨時期は食中毒に気をつけよう・・・と母から教わってはいた。
確かに芽は取り除くが、緑変部位は食べていた。
子育て中には一度も経験しなかったし、自分で植えた庭の小さなじゃがいもも平気でムシャムシャ。
以下ジャガイモ講座
■そもそもジャガイモは・・・
じゃがいもの原産地は南米アンデス高地。ヨーロッパへは16世紀初めに導入された。日本へは1601年オランダ船がジャガタラから長崎へ導入し『じゃがいも』と呼ばれるようになりました。今では、カレーの具や肉じゃがなど日本の食生活にかかせない食材の一つです。こんなに身近なじゃがいもでも、食中毒の原因になることがあるのです。
■原因
じゃがいもの発芽部分には有毒成分であるアルカロイド(主にα-ソラニンとα-チャコニン)が含まれています。また、芽だけでなく光が当たった部分にも多く含まれます。じゃがいもは光に当たるとクロロフィルが作られ表面が緑色になるほかアルカロイドも表皮の近くに作られるのです。注意が必要 なのは、たとえ表皮が緑色になっていなくてもアルカロイドが多く作られていることもあるということです。
■対策
芽の部分はきちんと取り除きましょう。
自分で栽培した小さい未成熟なじゃがいもはアルカロイド含有量が多いと言われているので十分注意しましょう。
緑変した部分の皮は厚めにむきましょう。
じゃがいもの皮には可食部(髄質部)と比べて多くアルカロイドが含まれているので、少ない量で中毒になる可能性があるお子様は、なるべく皮をむいて食べましょう。
貯蔵するときは、光の当たらない風通しの良い場所に保管しましょう。
苦味やえぐ味がある場合には食べないようにしましょう。
幼児と老人は抵抗力が低いので要注意だ。
最近は幼児だけでなく青少年の抵抗力も落ちているかもしれないから、要注意