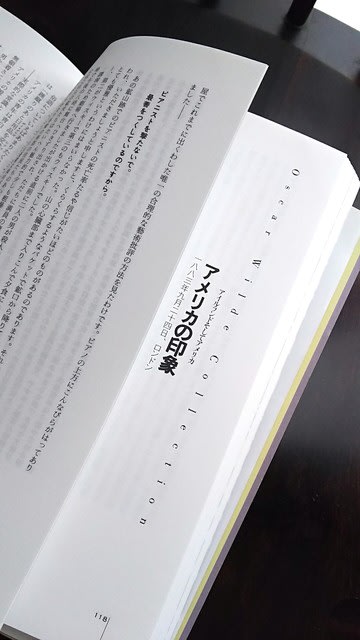「どうかピアニストを撃たないでください」
・・・この本の解説(ミステリ評論家 吉野仁)の冒頭に、 上の言葉が書かれている。。 アメリカ西部開拓時代の酒場には、 こう書かれた紙が貼ってあった、と。
吉野氏の解説のつづきにも、 オスカー・ワイルドがアメリカを旅した時、 この言葉の張り紙を目にした事が書かれている。 、、ここを読んでいて、 私もこの文言を前に読んでいた事を思い出しました。

『ピアニストを撃て』 デイヴィッド・グーディス著 真崎義博訳
ハヤカワポケットミステリ 2004年
原題 'Down There' (Shoot the Piano Player)
***
先の解説では 西部開拓時代、「当時はピアニストを東部からわざわざ招いており、彼らは貴重な存在だったからだ」 と説明している。
…あ、 そういうことだったんだ、、 と私はやっと納得しました。 どうしてかと言うと… オスカー・ワイルドの講演記 「アメリカの印象」(『ユリイカ』所収)で読むと、
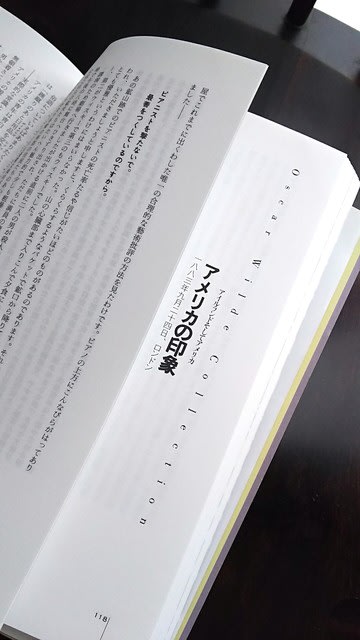
「ピアニストを撃たないで。 最善をつくしているのですから」
という張り紙をワイルドは見た、、と書かれていたので、 だから、私は 酒場の酔っぱらった荒くれ男が ピアニストが下手だとかいちゃもんをつけて それで撃ち殺してしまうのかなと思っていたのです。
、、でも、 上記の吉野氏の解説を読んで、 どうやらピアニストに腹を立てて撃ち殺す(のもあったかもしれないけれど)ほかに、 荒くれガンマン同士の喧嘩のとばっちりで、 流れ弾に当たってピアニストが犠牲になるのを避けようと、 そういう意味らしい、と。。
だいたい酒場のピアノは壁際に置かれて ピアニストはその前に坐るので、 お客たちに背中を向けているのです。 だから、 客同士の騒ぎに咄嗟に気づかないかもしれない、、 それに東部から来ているピアニストは拳銃だって持ってないかもしれない、、 だから
「どうかピアニストを撃たないでください」 、、って事だったんだ。。 成程。

***
本書『ピアニストを撃て』は、 西部開拓時代の物語でも 西部ガンマンの話でも無くて、 時代は1950年代のフィラデルフィア、 ポート・リッチモンドの労働者たちが集まる酒場の物語。。 でも、 先の開拓時代の「ピアニストを撃たないで下さい」という文言はきっと有名な文言なのでしょうね、、 それを知っていると踏まえての上で このタイトル、、 『ピアニストを撃て』
、、この小説は フランソワ・トリュフォー監督の映画で有名なのだそうです。
「ピアニストを撃て」(1960年)Wiki>>
… でも映画のほうは見ていないし、 舞台がフランスに変わっていたりするので、 あくまで小説の感想だけ書きます。 ただ いかにもヌーヴェルヴァーグの仏映画に似合いそうな、 そんな小説だというのは間違いないです。
、、 物語は、 二人組に追われた男が逃げ惑いながら酒場に飛び込んでくる場面から始まります。 金曜の夜、 労働者たちでテーブルは満員の酒場、、 追われてきた男はへとへとになりながら音楽のするほうへ… ピアノの音色のほうへ…
「おれだ」男はミュージシャシンの肩を揺すった。「ターリーだ。お前の兄貴、ターリーだ」
ミュージシャンは音楽を奏でつづけていた。ターリーはため息をつき、ゆっくりと首を振った。彼は思った、こいつには聞こえない。 まるで雲のなかにいるようだ、こいつを動かせるものは何もない。
、、 この追われている兄貴と、「雲のなかにいるよう」な 無関心な弟=ピアノ弾き、 そして酒場の喧騒、、 そういった描写がとてもいいんです。 モノクロームな画面、 切羽詰まっている兄貴がまくしたてる言葉、、 無関心に、 穏やかに笑って、、 あるいは肩をすくめて、、 ピアノに向かいながら兄貴の言葉を遣り過ごしている弟…
「だめだ」エディは静かに言った。それが何にしろ、おれを巻き込まないでくれ」
***
この小説の要は 文体なのだと思います。 事件=サスペンスの筋書きを追っているだけだと何てことは無いストーリーに思えるかもしれないけれど、、 大事なのは台詞と、 心の中の言葉=モノローグ。 それが全て。
、、 とにかく、 このピアノ弾きの空虚感がとても際立っていて… それはきっと、 厄介ごとの種ばかり重ねてきた兄貴達と縁を断って、 酒場の隅っこに居場所を見つけ、 闇に紛れるようにしてピアノを黙って弾く、、 そうしていれば何にも巻き込まれずに済む、、 兄貴だけでなく、 酒飲み達の喧嘩やもめ事にも。。 とばっちりを受けずに生きていくこと… 「ピアニストを撃たないでください」 、、そういう風に危険から逃れて生きていく術を、 エディは身につけたんだ、、たぶん、、 きっとそれが唯一の方法、だったんだと思う。。。
ピアノ弾きエディは言葉に出さず、 心の中で思いを反芻する。 兄貴のこと、 それから女のことも、、 同じ酒場で働いているウェイトレス、、
「…なのに、どうしたんだ? 何で、こんなふうに考えているんだ? 関わらないほうがいい。 カーヴの多すぎる道路みたいなものだし、第一、おまえは自分のいる場所もわかっていないじゃないか。 それにしても、彼女があまり話したがらないのはなぜだ? それに、滅多に笑顔を見せないのはなぜだ? …」
***
、、 そんな空虚な 「雲のなかにいるよう」な ピアノ弾きエディが 否応なく事件に巻き込まれてしまう物語なんだと思って読んでいったら、、 じつは そればかりではなかったのですよね。。。 エディ自身の過去… つづきは書けないけれど…
ピアノ弾きの名はエディ、、 エディ=本名はエドワード。 そう! エドワードなんです。 (ここからは小説と離れた話になってゴメンなさい)
上の西部劇風の酒場の写真。 クイックシルバー・メッセンジャー・サービス(Quicksilver Messenger Service)の1969年のアルバム 「Shady Grove」のライナーにあった写真を借りました。 そこにいるピアニストは ニッキー・ホプキンスさん。 ニッキーの代名詞は《エドワード》
どうしてニッキーのニックネームが《エドワード》なのか、というのは この「Shady Grove」のウィキに載っていますが、 ストーンズとのセッションの中でブライアン・ジョーンズがニッキーに発した言葉 「Eの音をくれ!」が聞こえなかったことから来てるみたいですね⤵
https://en.wikipedia.org/wiki/Shady_Grove_(Quicksilver_Messenger_Service_album)
「Shady Grove」にも収録されている ピアノインスト曲「Edward, The Mad Shirt Grinder」 この副題の The Mad Shirt Grinder がどういう意味なのか、 私知らないんですけど、、 いつも大人しく隅っこでピアノを弾いていたエドワード(ニッキー)のイメージと 《The Mad Shirt Grinder》、、 なんだかこの二面性が…
、、こじつけですけど 『ピアニストを撃て』のエディ=エドワードにも繋がっていくイメージなのです、、 これ以上は書けませんけれど…
、、 カートゥーン雑誌が大好きだったというニッキー・ホプキンスさん、、 スタジオで出番を待っている間ずっと隅っこで大人しく漫画を読んでいたというニッキー。。 もしかして、パルプフィクション出身のこの作家のペイパーバック「Down There」(1956)を読んでいた… なんて想像したら、、 ちょっと面白いな。。
***
思いきり話は脱線してしまいましたが、、 『ピアニストを撃て』、、 ピアノの黒鍵と白鍵のごとく白黒のフィルムノワールな世界観。
エドワードのモノローグと 女との会話(ダイアローグ)の対比や、、 夜の闇に包まれた街と そこに降ってくる雪の白…
そして、、 この物語に出てくる女がまた良いんです。。 場末の労働者ばかりが集まる酒場に普通こんないい女(ウェイトレス)はいないよ… そればかりか、 エディが住む同じアパートにいる女(娼婦)だって こんな理想的な女は普通いないよ… って思うんだけど、、 (理想的、というのは 見た目だけではなくて、 自分の境遇に対して強くて信念があって、 だけど優しい)
、、パルプフィクションだから、、ね。。 有り得ないくらいいい女でも良いよね、、
ところで、 この作家 デイヴィッド・グーディスさん、 いろんな作品が映画化されているらしいです、、 Wiki
>>
↑上記の日本語のウィキには載っていないけれど(翻訳本が出ていない)、、 ジャン・ジャック・ベネックス監督の映画 『溝の中の月』(ウィキ
>>) の原作 「The Moon in the Gutter」もこの人の本らしい。 ナスターシャ・キンスキーとジェラール・ドパルデューのこの映画、、 たしかビデオで見てるはずなんだけれど全く内容が思い出せなくて… ナタキンの美しさだけが朧に残っているだけ…
『溝の中の月』も 小説の言葉で読んでみたいなぁ…
だって、、 ナスターシャ・キンスキーみたいな美しい(しかも強さのある)人はもうなかなかいないもの、、 『ピアニストを撃て』に出てくるウェイトレスも、 娼婦も、、 ナタキンだったら どちらを演じても …たぶん 理想的だと思う。。
***
9月になりました。 夜が次第に長くなっていきます。。
夜のモノローグに
耳を澄ませましょう…