1953年製作。
山田洋次の宣伝用コメントではないが、これが恋愛映画であることはわかってはいた。
で、再見してみると冒頭、遥か彼方からシェーンが近づいてくるのと家の中で行き来しているジーン・アーサーの姿を窓越しになかなかはっきり見えないのとを微妙に気をもたせながらカットバックして、二人が出会うまでを映像として構成しているのがわかる。
さらに祭りに行くのに身支度をしたアーサーが馬車に乗るとき、シェーンが騎士さながらにいったん降りて乗るのを介助する。
祭りで仲間たちが祝福する中にスターレット夫妻がキスするところでシェーンがちょっと目を伏せる、隣でジョーイがまったく気づいていないのがコントラストになっている。
祭りでふたりが踊る間、旦那のヴァン・ヘフリンが囲いの戸につかまってぶらぶらしているあたりが、ふたりの仲に気づいてきているなと思わせる。
などなどまことに繊細な演出でシャイな恋愛を描き出している。
ウォルター・ジャック・パランスは前はウォルターをつけないで表記されるのがふつうだったのがこの映画でクレジットされている通りに元に戻っている。
西部劇で当然のように出てくる早撃ちというのを何のためにやるのかというのがはっきりわかるように描かれている。
つまり相手に先に抜かせてから撃ち殺す、この先に抜かせるというのが正当防衛を主張して無罪をかちとる根拠になるわけで、だから必ず証人に目撃させている。このあたりの描写と演出の細かさは特筆もの。
何しろ保安官を呼んでくるのに三日かかるという場所なのだから、力が正義というというのも無理はないと自然に納得させる。
遠くから来るシェーンにまず鹿が気づいたり、朝、鹿が窓から覗いていたり作物食べているあたりの自然の豊かさと、鹿と人間が生きている地帯との境界のなさがよく出ている。
クライマックスの決闘前、よく考えると子供の足で馬に乗ったシェーンに追いつくのはムリがあるはずなのだが、カットバックが見事なので納得させられてしまう。
スタンダード・サイズ(IMDbによると正確には1:1.37フレーム)は、現在の映画館の設備では例によって横にビスタサイズ(1:1.66)くらいに広げておいて左右に黒味を入れるという見苦しい上映になる。上下を切るよりはいいが(昔の映画館では珍しくなかったらしい)。
ところで西部劇だと西部の広大さを表すのに適したワイドスクリーンを使う場合もあるのだが、スタンダード・サイズだと広さより遠くに見えるワイオミングの山脈の美しさが映える。
今のアップかロングかやたらとメリハリをつけるカメラワークに慣れた目で見ると、ミドルショット中心のサイズが続くのが中庸という言葉を思わせ、さほど引いていなくても人物の全身ショットが引いた効果を出す。
南北戦争(1861-1865)後に時代を設定して、エライシャ・クック・ジュニアが南軍のアラバマ州出身で、よく揶揄するようにハモニカで北軍の歌を吹かれて怒っていたのが殺された後南軍の曲を吹いていると思う。
実はモデルになっているのは「天国の門」でも描かれた先行した牧畜業者と後発の移民との争いであるジョンソン郡戦争(1892)なのだが、当時記事にした新聞社の印刷機が破壊されたりしたもので、原作者のジャック・シェーファーは時代をずらして小説化したのだという。
「天国の門」が封切時に異常なくらい叩かれたのだが、触れれば痛いアメリカ史の恥部らしい。大統領命令で後発の移民を銃撃したのだからね。
あちこちに犬がいる。スターレット家にも、殺されるエライシャ・クック・ジュニアのそばにも、酒場にも犬がいる。葬式での犬の演技が見事。
雑貨屋と酒場が同じ建物にあっても隔てていて女子供は酒場には入らないというルールがあるらしい。
ジャック・パランスがエライシャ・クックを殺す場面、動きのとれない泥濘に誘導していく動きのつけ方、遠雷が鳴り刻々と雲が動いて明るくなったり暗くなったりする自然の光の変化を一シーンに入れている演出が見事。
銃は良くも悪くもない、扱う人間次第というシェーンのセリフは今だと全米ライフル協会の公式見解みたいに聞こえるが、実際に人を殺しただろうしその罪を贖う重さを背負っているのが違う。
エンドタイトルがだらだら流れないで、エンドマークが出たらすぱっと終わるというのはいいね。










 フジヤマガイチ @gaitifujiyama
フジヤマガイチ @gaitifujiyama 家畜人六号【小暮 宏】 @yapoono6
家畜人六号【小暮 宏】 @yapoono6
 シネフィルイマジカDVD @cinefilDVD
シネフィルイマジカDVD @cinefilDVD Yash_san(´・ω・`)? @yash_san
Yash_san(´・ω・`)? @yash_san 東京新聞政治部 @tokyoseijibu
東京新聞政治部 @tokyoseijibu

 高峰秀子 @HidekoTakamine
高峰秀子 @HidekoTakamine
 G.M @raoul_dandresy
G.M @raoul_dandresy
 三浦沙良 @saramiura
三浦沙良 @saramiura
 映画ランナー【映画雑学・トリビア】 @eigarunner
映画ランナー【映画雑学・トリビア】 @eigarunner
 スペックス @spexspexspex
スペックス @spexspexspex
 本宮映画劇場 @motomiyaeigeki
本宮映画劇場 @motomiyaeigeki
 キヨみみ @kiyomimi
キヨみみ @kiyomimi 新文芸坐 @shin_bungeiza
新文芸坐 @shin_bungeiza 御成座 @OdateOnariza
御成座 @OdateOnariza
 ごめちん @gomechin
ごめちん @gomechin 塚本晋也tsukamoto_shinya @tsukamoto_shiny
塚本晋也tsukamoto_shinya @tsukamoto_shiny

 ドートマンダー @dortmunder_k
ドートマンダー @dortmunder_k 勝海舟bot @KatsuKaishuBot
勝海舟bot @KatsuKaishuBot ふわり @fuwarihonwaka
ふわり @fuwarihonwaka
 ダークボ @darkbo
ダークボ @darkbo れっどゴルゴ@Anti-fascism @RedGolgo
れっどゴルゴ@Anti-fascism @RedGolgo
 水道橋博士 @s_hakase
水道橋博士 @s_hakase Tetsuya Kawamoto @xxcalmo
Tetsuya Kawamoto @xxcalmo 山本弘 @hirorin0015
山本弘 @hirorin0015 babby @cipriani_s
babby @cipriani_s 辻 真先 @mtsujiji
辻 真先 @mtsujiji 深爪 @fukazume_taro
深爪 @fukazume_taro







 山口茜 @punainenpenkoa
山口茜 @punainenpenkoa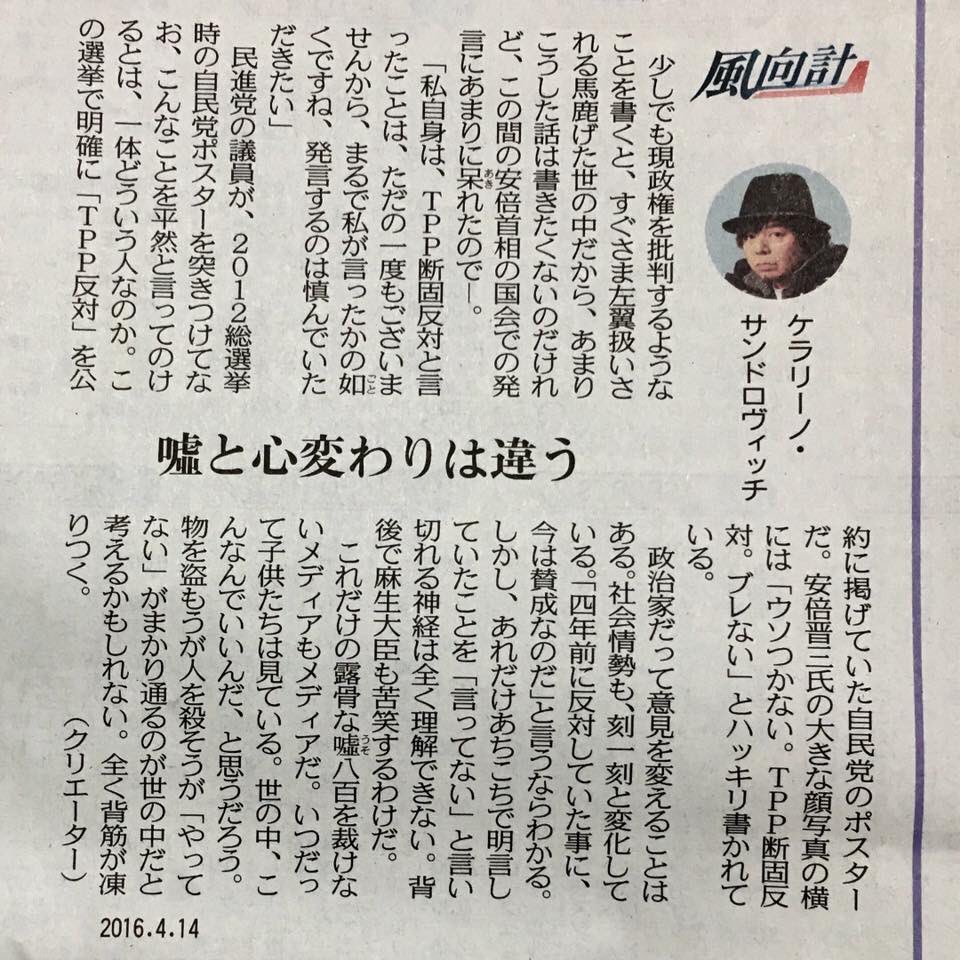

 みずみず @mizumizu25
みずみず @mizumizu25

 外国人名言集@GLOBALPOWER @_GLOBALPOWER
外国人名言集@GLOBALPOWER @_GLOBALPOWER 堀江貴文(Takafumi Horie) @takapon_jp
堀江貴文(Takafumi Horie) @takapon_jp

 きぬきぬ @kineukineu
きぬきぬ @kineukineu

 時計じかけの洋梨 @ClockworkReona
時計じかけの洋梨 @ClockworkReona
 単なる松竹錠 @reptilicus1
単なる松竹錠 @reptilicus1 高峰秀子 @HidekoTakamine
高峰秀子 @HidekoTakamine 竹熊健太郎《一直線》 @kentaro666
竹熊健太郎《一直線》 @kentaro666
 九条 はるさめ @Harusame_hope
九条 はるさめ @Harusame_hope


 マドモアゼルズ 坪倉 @heyheymy2
マドモアゼルズ 坪倉 @heyheymy2
 IndieTokyo @IndieTokyo
IndieTokyo @IndieTokyo
 サンキュータツオ(米粒写経) @39tatsuo
サンキュータツオ(米粒写経) @39tatsuo
 きよ @kysmgrc
きよ @kysmgrc Moonbeams @mellowbossa
Moonbeams @mellowbossa

 らばQ @lbqcom
らばQ @lbqcom
