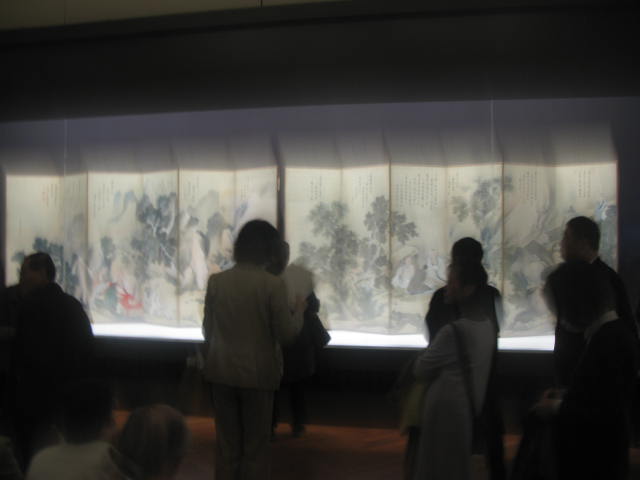昨日は、ふたりで東海道線で西に向かい熱海に行く予定だったが、天気が悪く中止した。その代わり、大船駅から、そのまんま東へ向かった(本当に都知事戦に出るのだろうか、出ても惨敗だろう)。上野の東博で遊んできた。あの素晴らしい平山郁夫展をもう一度、という手もあったけど、本館で、”黒田清輝と京都”の特集陳列があることを知り、平常展を観ることにした。二月に入り、正月展示とは違った作品がみられるだろうと、いうこともあった。玄関に入り、特別展示の一覧をみた。国宝室は、虚空蔵菩薩像に変わっていたし、前述の黒田清輝展、そして、二時から学芸員説明付きの蕪村の屏風絵”蘭亭曲水図屏風”も七室に展示されている。良かったと思った。さすが、東博、いつ来ても楽しめる。だから一年パスポートを買っているのだ。
はじめに、黒田清輝展を観た。黒田は1893年、9年間に及ぶ、フランス留学を終え、その年に京都を訪れ、まるで、珍しい異文化に触れた思いがしたという(もう、フランス人になっていたのでしょうか;笑)。そして、京都を題材とした(とくに舞妓さん)絵を描き始めた。この展示室では、大作”昔語り”の一連の下絵と”舞妓”が飾られている。”昔語り”は住友に所蔵されていたが、戦災で焼失し、現在は下絵しか残っていない。舞妓さん、草刈りの娘さん、僧侶など6名が一同に会しているのだが、それぞれの登場人物の詳細なスケッチと、淡い色が加えられた下絵がたくさん現存しているのだ。全体像の下絵もあり、ある程度、想像はできた。焼失しなければ、貴重な作品になっていたことだろう。
そして二時近くになったので、七室に向かった。もう大勢の人が集まっていた。若い女性学芸員が30分もかけて、ひとつの作品を説明してくれる。こんな贅沢なことはない。それにぼくは、蕪村については、俳句のことは去年、生涯学習センターの講座に出席したから、ある程度は知っているけど、絵のことになると、疎い。川端康成が国宝の、蕪村の絵画をもっていたことくらいしか知らないので、今回のガイド付きの鑑賞に出会えたことはラッキーだった。
蕪村、52歳のときの作だそうである。ということは俳句を始めた頃だ。まず屏風の画布の話があった。最高級の絹を使った絖(ぬめ)で、高価でお金持ちのパトロンがいないと無理だろうということだった。蕪村も絖を使った絵を描きたくて、富くじを買っていたという話もあるらしい(爆)。実際、光沢もうるわしく、観る方角によって変わるし、質感もある、との説明があった。
画題は、ぼくでも知っている”蘭亭曲水図”。書聖、王義之が文人四十一人を招き宴を開いた。曲水に盃を流し、それが目の前に来るまでに詩をつくる。つくれなかった人はその酒を飲まなければならない(ぼくなら、八百長して、わざと詩をつくらない、お酒の方がいい;爆)。のどかな時代だったなあ、中国も。屏風絵の中に入って、それぞれの人物と対話するのも美術鑑賞の楽しみのひとつですと。たしかに、画面の中には、酒ばかり飲んでる人がいる。ああ、こんな人とあほマスコミを肴に飲んでみたいなあ(汗)。絵の上部の文章は蕪村が書いたんですか、という質問が出た。蘭亭序というもので、別の人が書いたらしい。天気も良く、のどかな、楽しい一日だった、という意味のことだそうだ。屏風絵は、目が右から左へ誘うように、また時間が経過するように描かれている。また遠近も色の濃淡で表している。
春の海 ひねもすのたりのたりかな、 といったのどかな風情の、蕪村の屏風絵だった。これから、蕪村の絵も見逃さないようにしよう。