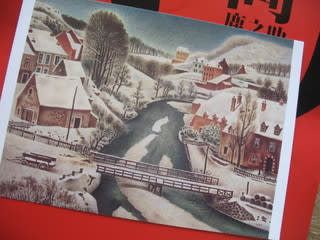明月院といえば、紫陽花。でも同じ頃に咲く、花菖蒲も見逃すことが出来ない。
日曜日の午後、紫陽花そして花菖蒲もそろそろではないかと偵察に行った。
紫陽花はほんのり青く、色づき始めてきていた。
ここのは、日本古来の姫紫陽花がほとんどで、淡い青色から濃い青色へと移っていく。ボクはこんな淡いブルーが好きなので、ボクにとっては今が見頃かな。
でも多くの人にとっては、”ショー(小)見頃”といったところかな。



花地蔵さんもお花見。”余もショー満足じゃ”。

この丸窓の向こうが花菖蒲園。ここからはみえない。

500円払って、庭園に入る。”チョー(超)きれい!”若い女性が素っ頓狂な声をあげる。みんなびっくりしている。最高に出来あがった状態だ。ボクもまねして”チョー見頃”宣言。



写生したりカメラに撮ったり。

遠目もいいけど、近目だって。



みんなが満足している姿をみて赤地蔵さんも、”余もチョー満足じゃ”。

ここ数日が花菖蒲の”チョー見頃”です。近くの方は是非観に行ってください。鎌倉一です。
紫陽花の”チョー見頃”は今週末でしょうか。
日曜日の午後、紫陽花そして花菖蒲もそろそろではないかと偵察に行った。
紫陽花はほんのり青く、色づき始めてきていた。
ここのは、日本古来の姫紫陽花がほとんどで、淡い青色から濃い青色へと移っていく。ボクはこんな淡いブルーが好きなので、ボクにとっては今が見頃かな。
でも多くの人にとっては、”ショー(小)見頃”といったところかな。



花地蔵さんもお花見。”余もショー満足じゃ”。

この丸窓の向こうが花菖蒲園。ここからはみえない。

500円払って、庭園に入る。”チョー(超)きれい!”若い女性が素っ頓狂な声をあげる。みんなびっくりしている。最高に出来あがった状態だ。ボクもまねして”チョー見頃”宣言。



写生したりカメラに撮ったり。

遠目もいいけど、近目だって。



みんなが満足している姿をみて赤地蔵さんも、”余もチョー満足じゃ”。

ここ数日が花菖蒲の”チョー見頃”です。近くの方は是非観に行ってください。鎌倉一です。
紫陽花の”チョー見頃”は今週末でしょうか。