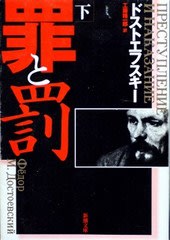
十数年ぶりに読み終えて、深いふかいため息のようなものが唇をついて出た。ため息の大部分は驚嘆であり、賛嘆である。一章ごとに、苦悩と崇高と哄笑が炸裂し、読者の胸に食い込んでくる。「うん、ここは覚えている。そうだったな~」とうなずいていたのは最初の数十ページだった。わたしはたちまち「新しい体験」のなかに投げ込まれることとなった。読むたびに「新しいドストエフスキー」。こういった体験をとても2000字程度のことばでは要約できないのは明らかである。
まず眼を見はらされるのが、意識と無意識との葛藤。さらに、善と悪との、神と人との、男と女との葛藤。しかも、そういった二元論が、登場人物相互間の葛藤にとどまらず、ひとりの人間のなかに存在しているという発見! これはフランス流の心理小説とは似て非なる世界の開幕といわざるをえない。そこからもたらされる愚劣さ、滑稽と悲惨を、彼がつくり出した登場人物相互の絡み合いを通じて、あますところなく描き出す。
ドストエフスキーは、ひょっとして、殺人もしくは殺人未遂の経験がほんとうにあるのではないか? そう邪推したくなるくらい、本書における人間への洞察力はすさまじい。ひとりの人間のなかに宿った、こういった恐ろしい矛盾は、ブラックホールのように、周囲の空間と時間をねじまげてしまう。その種の強力な磁場を持っているのは、ラスコーリニコフばかりでなく、ポリフィーリィやスヴィドリガイロフについてもあてはまる。映画もテレビもラジオもない時代に、小説という形式が、それまでにない自由さとパワーを発揮しはじめたのは、バルザックあたりからであろう。むろん、近代市民社会の成熟につれ、民衆が台頭して、爆発的に市場が拡大し、近代資本主義経済があらたな段階へとすすんだという時代背景を抜きには考えらないことである。こういった人間中心世界の規模拡大はルネサンス期とは比較にならないさまざまな思想を生み出したのだ。
ドストエフスキーも、そういった時代の子である。「現代の予言者」などといって、自説を補強するため拡大解釈するのはまちがっている。とはいえ、ドストエフスキーが到達しえた普遍性は、時代の制約をやすやすとのり超え、21世紀にいたっても新たな広範な読者を獲得していく。
ポリフォニックでカーニバル的な人間たちの愚かしさの饗宴。いや、「崇高な」といってもいい、ひとつの場面を読み終え、さて、つぎはどんな展開がまっているのか、と読みすすんでいく。主筋のほか、いろいろな要因が複雑にパッチワークのように絡み合ってくるが、サスペンスは最後までとぎれることはない。すべてドストエフスキーが生み出した「登場人物」にすぎないのに、彼らは作者に反抗し、勝手気ままに動き回ろうとする。作者は細心の注意を払って、正確に書きとめようと息をこらしている。わずか数行。そのなかに、どれほどの「魂の真実」をきらめかせていることか・・・。
たとえば、第六部第二章におけるラスコーリニコフとポリフィーリィとの対決。また、それに続く、ラスコーリニコフと、あるいは妹ドゥーニャとスヴィドリガイロフとの、綱わたりじみた対決場面のなんという緊迫感。一歩誤れば地獄が待っているのだ。こういった場面を書き込んでいくドストエフスキーの作家的力量には、最大級の讃辞をささげるしかあるまい。
スヴィドリガイロフの彷徨と死のありさまを見よ! N橋から眺めたネヴァ川の黒い水面とペトロフスキー島。夢のなかに出てくる美しい花や、悩ましいネズミども。そうして彼は現実と幻想のあいだをさまよう。この懊悩はいったいなんだろう? そうだ、スヴィドリガイロフこそ、ラズーミヒンもソーニャも家族もいないラスコーリニコフそのものではないか。
本書には夢がじつにたくさん書き込まれ、そのどれもが、深い象徴的な役割を負わされている。そこには無意識の深淵が、ぽっかり口をあけているのだ。どれもすばらしく効果的だが、なかでも極めつけは、流刑地に着いてから彼を苦しめることになるある疫病の夢だろう。
<全世界が、アジアの奥地からヨーロッパにひろがっていくある恐ろしい、見たことも聞いたこともないような疫病の犠牲になる運命になった。>
ドストエフスキーはそれを「ある微生物」だと書いているが、いろいろな解釈が可能だろう。こういう場面を読まされると、ドストエフスキーが「黙示録的な作家だ」という意味がよくわかる。
<あれは小説ってよりむしろ抒情詩だな。つまり、小説にしようと思うと、焼いてからのことを書かなきゃ、小説にならない。つまり現実の対人関係ってものが出て来ない。対社会関係も出て来ないからね。君のラスコルニコフは動機という主観の中に立てこもっているのだから・・・>(小林秀雄対話集より「美のかたち」)
対話の相手はいうまでもなく三島由紀夫。わたしは二十歳になったころこの対話集を読んでいるが、「罪と罰」というと、小林のこの鋭利な指摘を思いおこす。「あれ」というのは「金閣寺」をさしている。小林秀雄はおそらく、ドストエフスキーを「魂の事件」として、わが国で最初に体験した批評家である。
19世紀はさまざまなジャンルで多くの天才を輩出した時代であった。彼らの生み出したものが、つぎの100年をある意味で決定づけたといえるような、真の巨匠たち。わたし自身もむろん、その影の中を歩んでいるひとりである。先日ドストエフスキーの年表を眺めていて、おやと思って調べてみたら、つぎの一致に気がついた。
カール・マルクス (1818-1883) ドイツの経済学者・哲学者・革命家
ドストエフスキー (1821-1881) ロシアの小説家
うかつな話だが、このふたりの天才が、まったくの同時代人であったとは!
ドストエフスキー「罪と罰」工藤精一郎訳 新潮文庫>☆☆☆☆☆
まず眼を見はらされるのが、意識と無意識との葛藤。さらに、善と悪との、神と人との、男と女との葛藤。しかも、そういった二元論が、登場人物相互間の葛藤にとどまらず、ひとりの人間のなかに存在しているという発見! これはフランス流の心理小説とは似て非なる世界の開幕といわざるをえない。そこからもたらされる愚劣さ、滑稽と悲惨を、彼がつくり出した登場人物相互の絡み合いを通じて、あますところなく描き出す。
ドストエフスキーは、ひょっとして、殺人もしくは殺人未遂の経験がほんとうにあるのではないか? そう邪推したくなるくらい、本書における人間への洞察力はすさまじい。ひとりの人間のなかに宿った、こういった恐ろしい矛盾は、ブラックホールのように、周囲の空間と時間をねじまげてしまう。その種の強力な磁場を持っているのは、ラスコーリニコフばかりでなく、ポリフィーリィやスヴィドリガイロフについてもあてはまる。映画もテレビもラジオもない時代に、小説という形式が、それまでにない自由さとパワーを発揮しはじめたのは、バルザックあたりからであろう。むろん、近代市民社会の成熟につれ、民衆が台頭して、爆発的に市場が拡大し、近代資本主義経済があらたな段階へとすすんだという時代背景を抜きには考えらないことである。こういった人間中心世界の規模拡大はルネサンス期とは比較にならないさまざまな思想を生み出したのだ。
ドストエフスキーも、そういった時代の子である。「現代の予言者」などといって、自説を補強するため拡大解釈するのはまちがっている。とはいえ、ドストエフスキーが到達しえた普遍性は、時代の制約をやすやすとのり超え、21世紀にいたっても新たな広範な読者を獲得していく。
ポリフォニックでカーニバル的な人間たちの愚かしさの饗宴。いや、「崇高な」といってもいい、ひとつの場面を読み終え、さて、つぎはどんな展開がまっているのか、と読みすすんでいく。主筋のほか、いろいろな要因が複雑にパッチワークのように絡み合ってくるが、サスペンスは最後までとぎれることはない。すべてドストエフスキーが生み出した「登場人物」にすぎないのに、彼らは作者に反抗し、勝手気ままに動き回ろうとする。作者は細心の注意を払って、正確に書きとめようと息をこらしている。わずか数行。そのなかに、どれほどの「魂の真実」をきらめかせていることか・・・。
たとえば、第六部第二章におけるラスコーリニコフとポリフィーリィとの対決。また、それに続く、ラスコーリニコフと、あるいは妹ドゥーニャとスヴィドリガイロフとの、綱わたりじみた対決場面のなんという緊迫感。一歩誤れば地獄が待っているのだ。こういった場面を書き込んでいくドストエフスキーの作家的力量には、最大級の讃辞をささげるしかあるまい。
スヴィドリガイロフの彷徨と死のありさまを見よ! N橋から眺めたネヴァ川の黒い水面とペトロフスキー島。夢のなかに出てくる美しい花や、悩ましいネズミども。そうして彼は現実と幻想のあいだをさまよう。この懊悩はいったいなんだろう? そうだ、スヴィドリガイロフこそ、ラズーミヒンもソーニャも家族もいないラスコーリニコフそのものではないか。
本書には夢がじつにたくさん書き込まれ、そのどれもが、深い象徴的な役割を負わされている。そこには無意識の深淵が、ぽっかり口をあけているのだ。どれもすばらしく効果的だが、なかでも極めつけは、流刑地に着いてから彼を苦しめることになるある疫病の夢だろう。
<全世界が、アジアの奥地からヨーロッパにひろがっていくある恐ろしい、見たことも聞いたこともないような疫病の犠牲になる運命になった。>
ドストエフスキーはそれを「ある微生物」だと書いているが、いろいろな解釈が可能だろう。こういう場面を読まされると、ドストエフスキーが「黙示録的な作家だ」という意味がよくわかる。
<あれは小説ってよりむしろ抒情詩だな。つまり、小説にしようと思うと、焼いてからのことを書かなきゃ、小説にならない。つまり現実の対人関係ってものが出て来ない。対社会関係も出て来ないからね。君のラスコルニコフは動機という主観の中に立てこもっているのだから・・・>(小林秀雄対話集より「美のかたち」)
対話の相手はいうまでもなく三島由紀夫。わたしは二十歳になったころこの対話集を読んでいるが、「罪と罰」というと、小林のこの鋭利な指摘を思いおこす。「あれ」というのは「金閣寺」をさしている。小林秀雄はおそらく、ドストエフスキーを「魂の事件」として、わが国で最初に体験した批評家である。
19世紀はさまざまなジャンルで多くの天才を輩出した時代であった。彼らの生み出したものが、つぎの100年をある意味で決定づけたといえるような、真の巨匠たち。わたし自身もむろん、その影の中を歩んでいるひとりである。先日ドストエフスキーの年表を眺めていて、おやと思って調べてみたら、つぎの一致に気がついた。
カール・マルクス (1818-1883) ドイツの経済学者・哲学者・革命家
ドストエフスキー (1821-1881) ロシアの小説家
うかつな話だが、このふたりの天才が、まったくの同時代人であったとは!
ドストエフスキー「罪と罰」工藤精一郎訳 新潮文庫>☆☆☆☆☆



























