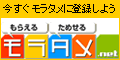4月26日(日)晴れ

今朝の朝日新聞を読んで・・・う〜む・・・以前から夫がよく口にしていることはこういうことかぁ〜
夫は「今のテレビってネットからのものだらけだ。」
確かに朝のニュースですら、「あ、それ昨夜、ネットで見た映像だ!」というものが多い。
動物ものの面白映像は、もうほとんどがネットから拾ってきたでしょというものだらけ。
猫動画にいたっては、ワタクシの、猫関連に強い友人知人から早々に回ってくるので「それ、見ました。知ってます。」感が強い。
「もうテレビの時代は終わった」なんて言う人がいるとちょっと寂しい気持ちになるのは、昭和生まれでなおかつネット世界の波には乗り遅れているからか。
ネットはネットで面白いし、でもテレビはテレビで面白いし、紙の本はもちろん紙の新聞もやめる気はありません!と思っている。
今朝の朝日新聞社会面にある「窓」というコラム。
飲食店でバイトを始めた大学生、使えないヤツでクビ寸前のところを、そこの料理長が救う。
料理長は、彼が仕事しやすいようにミスしないように色々工夫してくれる。
彼はそれに感謝して一生懸命真面目に努力する。
ある日、その料理長に「料理の世界に入りたい」と言うと料理長は「おまえは発達障害の子達となんかおもろいことやってるって言ってただろ。研究者になれ!」
彼は今、大学の准教授で、障害支援などの研究をしている。
読み始めてすぐ「あ、これツイッターで読んだことある。すごく好きな話だったので、何度も読んだ。」
ワタクシが違和感を感じたのは、この新聞の記事が、ツイッターで彼が言ってたことをただ長々と文章にしただけ。
20年30年前ならまだしも、今、この時代で、もっといえばネットでバズった話をそのまま記事にするのってどうなの?
ネットで彼の存在を知ったのならそれはそれでいい。
でもそれはスタートであって、そこから広げるべきじゃないのかなあ。
別にあたしゃ、この記事を書いた人と「あ、それ読みました、いい話ですよね〜」と共感を分かち合いたいとは思わない。
それは夫や娘達、友人達とすることであって、メディア側の人はそれ以上の存在であってほしいなあと思う。
まあ、いつもこの「窓」のコラムはよくわからんコラムだなあと思うことが多いので、いいんだけどさっ。
それにひきかえ、4月22日の「多事奏論」編集委員高橋純子氏の『首相の地金 「ある」と言えども取らぬ責任』といい
今日の文化文芸欄 吉田純子氏の『風刺で「連なる」これが文化」といい、そのとおりっ!と膝を打った。
どちらも、安倍首相の、例の「星野氏に便乗した件」を絡めている。
さすがだ。文章が上手いだけでなく、切り取り方も、目の付け所も、上手い。
高橋氏は星野源氏の「アイデア」の歌詞を引いてくる。
♪生きてただ生きていて 踏まれ潰れた花のように にこやかに 中指を♪
ままならない日々をアイデアで乗り切る賢さを。
尊厳を踏みにじってくる相手には、にこやかに中指を立てて抗議するしなやかな強さを。(中略)
この二つがあれば生きていける。今はそんな風に解釈して聴いている。と書き、安倍首相の責任というものへの感覚を問う。
そして、最後の締めが・・・
ひとり鏡の前に立つ午前10時48分。(←彼女はずっと寝ていないのだ)
カッコいい中指の立て方を、研究してみる。
くーーーっ!カッコいいっ。
吉田氏は星野源氏の「うちで踊ろう」の歌いやすさからタイトルの背景までを細やかに解読する。
さらには、「連なる」ということは日本の伝統文化であるとも言う。
連歌、連詩、連句。
そんな若者たちの輪に入ろうとして邪険に扱われた首相に彼女は「ちょっと可哀想でもある」と少しだけ優しい。
そして、お笑い芸人(掲載されているのはたむけんのパロディー動画の写真)達による迅速な「ツッコミ」のおかげで「ボケ」という居場所ができたのは救いだったかもしれないと。
そして、彼女の文章も、やはり最後が効いている。
風刺の力が境界線を曖昧にし、新たな「連なり」の礎となる。首相、これが文化です。
くーーーっ!カッコいいっ。
ただただあの動画にはムカつき、苛立ち、わぁわぁ文句を言っていただけの自分に、反論っていうのはこうやるのよとやり方を教えてもらった気がした。
今日の一枚は・・・
娘から「前に作ってくれたマスク、ちょっと大きいから、小さめに作って!」とのご要望にお答えし、新たに小さめの型紙を入手したのだが、前回と作り方が違うことに気づかず、ここまで縫ってから「え?こうなるの?」と驚いた。
小学生の頃から、展開図は苦手。
夫に「ガッチャマン の悪者みたいでしょ!」と言うと即「総裁X?」
でも今、検索したらマジンガーZの「あしゅら男爵」でした。
小さいサイズのマスクはその後無事作って本日発送しました。

この失敗マスクで思い出すのは、あしゅら男爵もそうだけど、今、ナイツの塙氏がやってるユーチューブでの漫才。
一人二役でやってて、笑う。

今朝の朝日新聞を読んで・・・う〜む・・・以前から夫がよく口にしていることはこういうことかぁ〜
夫は「今のテレビってネットからのものだらけだ。」
確かに朝のニュースですら、「あ、それ昨夜、ネットで見た映像だ!」というものが多い。
動物ものの面白映像は、もうほとんどがネットから拾ってきたでしょというものだらけ。
猫動画にいたっては、ワタクシの、猫関連に強い友人知人から早々に回ってくるので「それ、見ました。知ってます。」感が強い。
「もうテレビの時代は終わった」なんて言う人がいるとちょっと寂しい気持ちになるのは、昭和生まれでなおかつネット世界の波には乗り遅れているからか。
ネットはネットで面白いし、でもテレビはテレビで面白いし、紙の本はもちろん紙の新聞もやめる気はありません!と思っている。
今朝の朝日新聞社会面にある「窓」というコラム。
飲食店でバイトを始めた大学生、使えないヤツでクビ寸前のところを、そこの料理長が救う。
料理長は、彼が仕事しやすいようにミスしないように色々工夫してくれる。
彼はそれに感謝して一生懸命真面目に努力する。
ある日、その料理長に「料理の世界に入りたい」と言うと料理長は「おまえは発達障害の子達となんかおもろいことやってるって言ってただろ。研究者になれ!」
彼は今、大学の准教授で、障害支援などの研究をしている。
読み始めてすぐ「あ、これツイッターで読んだことある。すごく好きな話だったので、何度も読んだ。」
ワタクシが違和感を感じたのは、この新聞の記事が、ツイッターで彼が言ってたことをただ長々と文章にしただけ。
20年30年前ならまだしも、今、この時代で、もっといえばネットでバズった話をそのまま記事にするのってどうなの?
ネットで彼の存在を知ったのならそれはそれでいい。
でもそれはスタートであって、そこから広げるべきじゃないのかなあ。
別にあたしゃ、この記事を書いた人と「あ、それ読みました、いい話ですよね〜」と共感を分かち合いたいとは思わない。
それは夫や娘達、友人達とすることであって、メディア側の人はそれ以上の存在であってほしいなあと思う。
まあ、いつもこの「窓」のコラムはよくわからんコラムだなあと思うことが多いので、いいんだけどさっ。
それにひきかえ、4月22日の「多事奏論」編集委員高橋純子氏の『首相の地金 「ある」と言えども取らぬ責任』といい
今日の文化文芸欄 吉田純子氏の『風刺で「連なる」これが文化」といい、そのとおりっ!と膝を打った。
どちらも、安倍首相の、例の「星野氏に便乗した件」を絡めている。
さすがだ。文章が上手いだけでなく、切り取り方も、目の付け所も、上手い。
高橋氏は星野源氏の「アイデア」の歌詞を引いてくる。
♪生きてただ生きていて 踏まれ潰れた花のように にこやかに 中指を♪
ままならない日々をアイデアで乗り切る賢さを。
尊厳を踏みにじってくる相手には、にこやかに中指を立てて抗議するしなやかな強さを。(中略)
この二つがあれば生きていける。今はそんな風に解釈して聴いている。と書き、安倍首相の責任というものへの感覚を問う。
そして、最後の締めが・・・
ひとり鏡の前に立つ午前10時48分。(←彼女はずっと寝ていないのだ)
カッコいい中指の立て方を、研究してみる。
くーーーっ!カッコいいっ。
吉田氏は星野源氏の「うちで踊ろう」の歌いやすさからタイトルの背景までを細やかに解読する。
さらには、「連なる」ということは日本の伝統文化であるとも言う。
連歌、連詩、連句。
そんな若者たちの輪に入ろうとして邪険に扱われた首相に彼女は「ちょっと可哀想でもある」と少しだけ優しい。
そして、お笑い芸人(掲載されているのはたむけんのパロディー動画の写真)達による迅速な「ツッコミ」のおかげで「ボケ」という居場所ができたのは救いだったかもしれないと。
そして、彼女の文章も、やはり最後が効いている。
風刺の力が境界線を曖昧にし、新たな「連なり」の礎となる。首相、これが文化です。
くーーーっ!カッコいいっ。
ただただあの動画にはムカつき、苛立ち、わぁわぁ文句を言っていただけの自分に、反論っていうのはこうやるのよとやり方を教えてもらった気がした。
今日の一枚は・・・
娘から「前に作ってくれたマスク、ちょっと大きいから、小さめに作って!」とのご要望にお答えし、新たに小さめの型紙を入手したのだが、前回と作り方が違うことに気づかず、ここまで縫ってから「え?こうなるの?」と驚いた。
小学生の頃から、展開図は苦手。
夫に「ガッチャマン の悪者みたいでしょ!」と言うと即「総裁X?」
でも今、検索したらマジンガーZの「あしゅら男爵」でした。
小さいサイズのマスクはその後無事作って本日発送しました。

この失敗マスクで思い出すのは、あしゅら男爵もそうだけど、今、ナイツの塙氏がやってるユーチューブでの漫才。
一人二役でやってて、笑う。