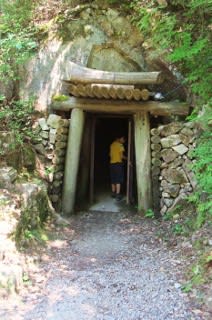先日猪名川へ行ったついでに川西の西多田にある「豆腐庵」の温泉湯豆腐がおいしいと
聞いてたので立ち寄り、試しに買ってみた。
この時期温泉湯豆腐のセットはおいてなかったのだが、同じ豆腐だということで
小分けされてた寄せ豆腐と温泉水を購入。

まずはそのまま食べてみる。
厳選された国産大豆と天然のにがりと水だけで丁寧に作られたという豆腐なだけに
やさしくクリーミーな味わい。

そして土鍋に温泉水と豆腐を入れ、温泉湯豆腐にした。
温泉水が白濁し、豆腐の角がとれてなめらかになってきたら食べごろ。

美味しい~!
そのまま食べるよりさらにとろけるような舌触り。
豆腐の風味も濃厚でうっとり~
なんでも温泉水で炊くことで、とうふのにがり成分と温泉水のナトリウムが化学反応を
起こして、豆腐のうまみを引き出し、更にとろけるようにやわらかくなるのだとか。
へえぇ~~
この豆腐庵の豆腐は厳選された豆腐と九州の温泉水だったが、
スーパーの100円の豆腐をただの炭酸水で炊いてもこんな風にとろけるんだろうか~?!
ちょっとやってみたいなぁ・・

温泉湯豆腐を堪能した後は豆腐の成分が溶け出て白濁した温泉水で豆乳鍋を楽しむことができる。
この豆乳で炊かれた野菜もまた美味しかった!
最後はうどんで締めに。
満足~~