14歳の時から死にかけていた母の男から母の代わりとして性的虐待を受け、生まれた乳児2人を次々と取り上げられた黒人女性セリーが、女好きで暴力的なミスター**ことアルバートに嫁がされ、妹ネッティーとも離ればなれになり夫にネッティーからの手紙も隠されたまま長い年月を耐え、夫が慕う女シャグの導きや舞い込んだ相続話などから自立を勝ち取ってゆくという小説。
セリーは黒人女性が白人や夫に殴られ虐げられることには、そういうものだと受け止めて自らは抵抗しないだけではなく、アルバートの息子のハーポに反抗的な妻のソフィアにいうことを聞かせるために殴ることを勧める人物として設定されています。そのためセリーの視点で描かれる虐待は過酷なものとしてよりもしかたないものとして受け流すような描写になります。その中で、暴力や差別に果敢に抵抗し反発を示すソフィアは踏みつけられ敗北し、あからさまには抵抗しないセリーが耐え(それもそれほど無理してではなく耐え)続けた結果、ささやかな勝利を得るというこの作品のコンセプトは、ある意味で現実的かも知れませんが、闘おうとする者への視線に冷ややかさ、シニカルさをも感じてしまいます。
また白人の暴力は、市長夫妻によるものとネッティーが移り住んだアフリカのオリンカの村でのイギリスのゴム会社によるもの以外は描かれず、主として黒人社会・黒人家庭内での黒人男性による黒人女性への暴力・虐待が描かれています。読み方によっては、黒人男性こそが悪い(白人の方がましだ)というアピールに見えるおそれも感じます。ネッティーからの手紙に描かれるアフリカの場面では、アフリカの黒人が同胞を奴隷としてアメリカに売り渡したとか、アフリカの村の人々(黒人)が愚かでアメリカの方がましだというニュアンスが漂っています。
現実世界にある差別と虐待を告発する物語には、厳しい差別とそれに対する真っ向からの抗議、闘う者の勝利を求めたくなりますが、この作品が広く支持されたことを考えると、文学の世界では少し距離を置いた抜いた描写の方が好まれるのかも知れません。
タイトルは、セリーとの対話の中でのシャグの言葉「あんたが野原を歩いていて、むらさきいろのそばを通りすぎて、それに気づきさえしなかったら、神は本気で腹を立てると思うよ」(234ページ)から。セリーが暴力夫ではなく周りを見る余裕ができるという意味では象徴的なところではありますが、ここでも正面から闘おうというよりは主観面での見方の変化が語られているもので、作者の指向を示しています。

原題:THE COLOR PURPLE
アリス・ウォーカー 訳:柳沢由実子
集英社文庫 1986年4月10日発行(単行本は1985年2月、原書は1982年)
ピューリッツァ賞、全米図書賞受賞作
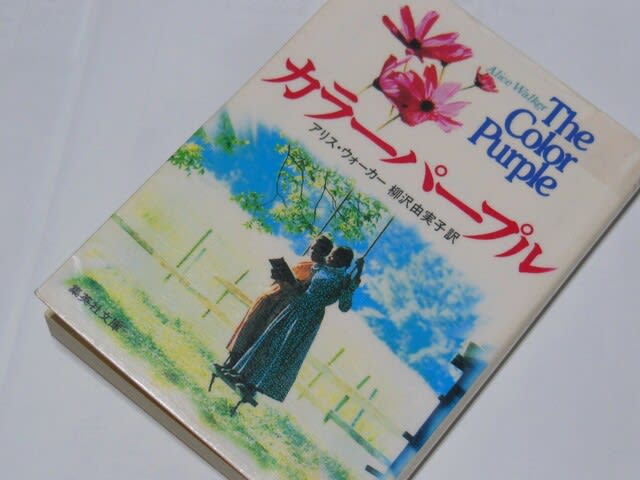
セリーは黒人女性が白人や夫に殴られ虐げられることには、そういうものだと受け止めて自らは抵抗しないだけではなく、アルバートの息子のハーポに反抗的な妻のソフィアにいうことを聞かせるために殴ることを勧める人物として設定されています。そのためセリーの視点で描かれる虐待は過酷なものとしてよりもしかたないものとして受け流すような描写になります。その中で、暴力や差別に果敢に抵抗し反発を示すソフィアは踏みつけられ敗北し、あからさまには抵抗しないセリーが耐え(それもそれほど無理してではなく耐え)続けた結果、ささやかな勝利を得るというこの作品のコンセプトは、ある意味で現実的かも知れませんが、闘おうとする者への視線に冷ややかさ、シニカルさをも感じてしまいます。
また白人の暴力は、市長夫妻によるものとネッティーが移り住んだアフリカのオリンカの村でのイギリスのゴム会社によるもの以外は描かれず、主として黒人社会・黒人家庭内での黒人男性による黒人女性への暴力・虐待が描かれています。読み方によっては、黒人男性こそが悪い(白人の方がましだ)というアピールに見えるおそれも感じます。ネッティーからの手紙に描かれるアフリカの場面では、アフリカの黒人が同胞を奴隷としてアメリカに売り渡したとか、アフリカの村の人々(黒人)が愚かでアメリカの方がましだというニュアンスが漂っています。
現実世界にある差別と虐待を告発する物語には、厳しい差別とそれに対する真っ向からの抗議、闘う者の勝利を求めたくなりますが、この作品が広く支持されたことを考えると、文学の世界では少し距離を置いた抜いた描写の方が好まれるのかも知れません。
タイトルは、セリーとの対話の中でのシャグの言葉「あんたが野原を歩いていて、むらさきいろのそばを通りすぎて、それに気づきさえしなかったら、神は本気で腹を立てると思うよ」(234ページ)から。セリーが暴力夫ではなく周りを見る余裕ができるという意味では象徴的なところではありますが、ここでも正面から闘おうというよりは主観面での見方の変化が語られているもので、作者の指向を示しています。

原題:THE COLOR PURPLE
アリス・ウォーカー 訳:柳沢由実子
集英社文庫 1986年4月10日発行(単行本は1985年2月、原書は1982年)
ピューリッツァ賞、全米図書賞受賞作
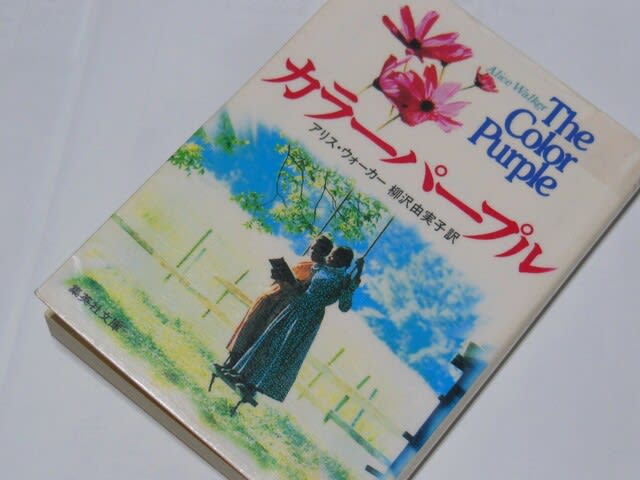


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます