先日、農協の直売所で「マツモトセンノウ」を売っていたのを発見。あわてて入手する。植物園の日陰で咲く「フシグロセンノウ」の朱色の鮮やかさに惹かれたが、尾上邸ガーデンで見た「マツモトセンノウ」もまた見事だった。しかもその名前の由来が、高麗屋の松本幸四郎の家紋に似ているからという言われがあるので名前を憶えていた。
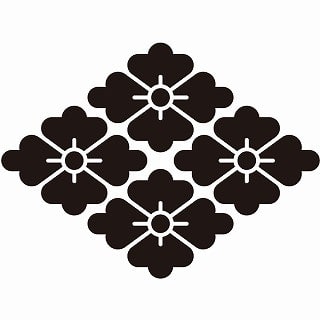 (画像はweb「家紋のいろは」から)
(画像はweb「家紋のいろは」から)
しかし、家紋の花弁は4弁だが、実際の花弁は5弁だ。しかも、花の形が全く違う。松本という名前がどこから出てきたのかが不明だ。最近の研究では中国・朝鮮に自生する種と同一であることがわかり、したがって、その渡来種が信州松本で栽培されたことで名前がついたという。
江戸でブームになったマツモトセンノウは明治と共に絶滅したと思われた。それが戦後、長野伊那谷の石垣で自生していたのを発見された。そのためまだ絶滅危惧種に指定されている。

山野草の仲間では、朱色は珍しい。現在のマツモトセンノウには、そのほか赤・白・桃・斑入りなどがあり、花弁もいろいろあるようだ。ついでに、「センノウ」の由来は、むかし京都・嵯峨にある「仙翁寺」で栽培してきたことかららしい。
一時、日本で絶滅したと思われたマツモトセンノウは不死鳥のように復活を遂げた。松本幸四郎由来説は怪しくなったが、歌舞伎の衰えないパワーを考えるとその説にちなんだ由来だと言ってもいいのかもしれない。この花を見て幸四郎ファンの娘もえらく感激していたけど。





















































