都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」

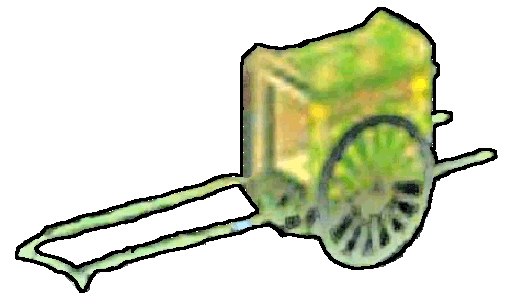
平安時代の大文豪が訪れた「初瀬(はせ)の長谷(はせ)寺」、現在の奈良県櫻井市初瀬町の長谷寺の宿でのエピソードです。
「人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞ昔の 香(か)ににほひける」紀貫之『古今集』
 「あなたは、さてどうでしょうね。他人の心は分からないけれど、昔なじみのこの里では梅の花が昔と変わらずによい香りを漂わせて咲いていますよ。」
「あなたは、さてどうでしょうね。他人の心は分からないけれど、昔なじみのこの里では梅の花が昔と変わらずによい香りを漂わせて咲いていますよ。」
この歌は、二人(多くは男女)が意中を述べ合ってやりとりする「贈答歌」ですので、「人」は直接には「相手」のことを指していますが、後の「ふるさと」と対比した、一般的な「人間」という意味も含んでいます。
「花」言えばこの時代は普通桜を指しますが、ここでは「梅」です。「人の心」と「ふるさとの花」が対置されています。
「昔の香ににほひける」の「にほひ」は「花が美しく咲く」という意味です。
平安時代になると視覚だけでなく「香り」といった嗅覚も含まれるようになりました。
さて、この歌は古今集に収められたものですが、「詞書(ことばがき/和歌や俳句の前書き)」に「初瀬に詣(まう)づるごとに宿りける人の家に、久しく宿らで、程へて後にいたれりければ、かの家の主人(あるじ)、『かく定かになむ宿りは在る』と言ひ出して侍(はべ)りければ、そこに立てりける梅の花を折りて詠める」とあります。
すなわち、昔は初瀬の寺へお参りに行くたびに泊まっていた宿にしばらく行かなくなっていて、何年も後に訪れてみたら、宿の主人が「このように確かに、お宿は昔のままでございますというのに(あなたは心変わりされて、ずいぶんいらしてくれませんでした)」と言った。
そこで、その辺りの梅の枝を折ってこの歌を詠んだ、ということです。
「そういう、あなたの方はどうだったのでしょう。ずっと覚えていてくれたのでしょうか。この里は昔ながらに梅の良い香りを漂わせていますよ。」
き‐の‐つらゆき【紀貫之】
[870ころ~945ころ]平安前期の歌人。三十六歌仙の一人。大内記・土佐守(とさのかみ)などを歴任。紀友則(きのとものり)・凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)・壬生忠岑(みぶのただみね)と古今集の撰にあたり、仮名序を書いた。著「土佐日記」、家集「貫之集」など。
大辞泉
『土佐日記』は、改めて言うまでもなく、土佐守の任を終えて都に帰るときの旅の様子を1人の女性に託してひらがなで書かれた日記です。
紀貫之は、「土佐日記」で歴史上はじめて日記文学を書いたり、古今集を先頭に立って編集したり、歌論として有名な「仮名序(かなじょ/仮名で書かれた序文)」を書くなど、平安時代を代表する「大文豪」です。
まあ言うなれば、昔なじみだったホテルを久々に訪れた老いた大文豪が支配人から「ホテルは昔のままでございますよ。あなたはお変わりになられたようですが」などと、ちょいと嫌味を言われたので、花びんの花を一本抜いて「君も私のことなんて忘れていたのじゃありませんか。世間の人は忘れっぽいものですから。花びんの花はずっと昔のままだけどね」と支配人の言葉を、さらりと切り返したといったところでしょうか。
この歌には、「紀貫之」の機知と粋なダンディズムが漂います。
私は、宿の主人が女性で、遠い昔の恋愛を暗示していると考えたほうが、よりお洒落な気がするのですが・・・。
「貴女は、私があなたのことを忘れていたように言いますが、貴女こそ、私のことを忘れていたのじゃありませんか。この梅は、あのころの様に、いい香り漂わせていますよ」
私には、そう思えてならないのですが・・・。
「あ~ら、キーさん。随分とお見限りだったじゃなぁい。こんなお店のことなんか、お忘れでしたかぁ?」
「そんなことはありませんよ。ママちゃんこそ、私のことなんか忘れて、ほかの客と宜しくやってたんじゃないの。お店の雰囲気も、花も昔のままのいい匂いがしているのに・・・」
梅の香りと、女性の色香・・・。どうです、そう思いませんか。
したっけ。


そろそろ、桜の便りも聞こえてきそうな季節になりました。桜の花の香りにはリラックス効果もあるそうです。
桜の香りの効能としては、喘息を抑え、痰をとり、咳止めに効果があり、熱をとり、解毒作用があり、二日酔いに効くと言われています。さらに、抑うつ作用もあるそうです。
また桜の葉は、胃腸を整え、下痢を止める作用があるとして昔から用いられていたそうです。
ですから、桜の花が咲くと、人が集まるのも自然なことだったようです。お花見は日本古来のアロマテラピーだったのかもしれません。
というわけで、儚くも散る桜の花に自分の衰えた美貌を重ねた、日本を代表する美人の一首です。
「花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに」小野小町『古今集』
 長雨をぼんやり眺めて、無駄に時間を過ごしていたら、いつの間にか花の色も移ろっていってしまった」というだけの歌ではありません。
長雨をぼんやり眺めて、無駄に時間を過ごしていたら、いつの間にか花の色も移ろっていってしまった」というだけの歌ではありません。
「桜の花の色は、むなしく衰え色あせてしまった、春の長雨をぼんやり眺めているうちに。ちょうど私の美貌が衰えたように、恋や世間のもろもろのことに思い悩んでいるうちに。」
「花」といえば、この時代「桜」のことです。「花の色」とは「桜の花の色」という意味だけではなく、「女性の若さ・美しさ」も暗示しています。
「世にふる」の「世」は「世代」という意味と「男女の仲」という二重の意味が掛けてある掛詞(かけことば)です。
さらに「ふる」も「降る(雨が降る)」」と「経る(経過する)」が掛けてあり、「ずっと降り続く雨」と「歳をとっていく自分」の二重の意味が含まれています。
「ながめせしまに」の「眺め」は「物思い」という意味と「長雨」の掛詞で、「物思いにふけっている間に」と「長雨がしている間に」という二重の意味があります。
満開に咲き誇った桜の花も、むなしく色あせてしまったわ。私が降り続く長雨でぼんやり時間を過ごしているうちにね。かつては絶世の美女と謳われた私も、もうすっかりお婆ちゃんだわ。恋とか愛とか、そんなことを考えているうちにね。
小野小町といえば、絶世の美女。しかし、花がいつかは枯れていくようにその美しさも永遠ではないと、憂いていたのです。
掛詞を多用して、自分の思いを、やんわりと伝える女心は、切ないですね。
美人であればあるほど、その思いは大きかったのかもしれません。
おの‐の‐こまち【小野小町】
平安前期の女流歌人。六歌仙・三十六歌仙の一人。仁明(にんみょう)・文徳(もんとく)両天皇の後宮に仕えた。美貌(びぼう)の歌人といわれ、多くの伝説があり、謡曲・歌舞伎の題材となっている。家集に「小町集」がある。生没年未詳。
大辞泉
この歌が人の心を打つのは、誰にも少なからず、こういう思いがあるからではないでしょうか。
「私だって若い頃は、ずいぶんモテたのよ。その気になっていたら、いつの間に、こんなに歳とっちゃったのかしら・・・いやだわ」
要するに誰もが心に思っている「若かった頃にやり残したことへの後悔」をこの歌が表現しているからかもしれません。
歳をとってくると時間の過ぎゆくのが、とても早く感じます。若い人もそうでない方も、今からでも遅くはありません。やり残したことをがんばってみてはいかがでしょうか。
老いらくの恋?それもいいじゃありませんか。
したっけ。

三月といえば、思い浮かぶのは「雛祭り」です。別名「桃の節句」。
本来の節句としては「上巳(じょうし)の節句」というのが正しい呼び方です。
節句には、その節句行事と結びついた節句植物があります。
1/7(人日・じんじつ)→七草(七草粥)
3/3(上巳・じょうし)→桃・よもぎ(桃花酒→江戸時代以降は白酒)
5/5(端午・たんご)→しょうぶ(ちまき→江戸時代以降は柏餅)
7/7(七夕・しちせき)→瓜(さくげ→江戸時代以降はそうめん)
9/9(重陽・ちょうよう)→菊(菊酒)
 「桃の節句」と結びついた植物といえば、いうまでもなく「桃」です。今では当たり前の話ですが、「上巳の節句」の起源・由来をたどってみると「桃」ではなかったようです。
「桃の節句」と結びついた植物といえば、いうまでもなく「桃」です。今では当たり前の話ですが、「上巳の節句」の起源・由来をたどってみると「桃」ではなかったようです。
「上巳の節句」は中国における「上巳の故事」に由来している。上巳の故事とは,上巳の日に生まれた3人の子女がわずか3日足らずで死んだことを忌み,それ以降不祥祓除のため水中に沐浴するようになったといわれています。(『晋書』束哲伝)
しんじょ【晋書】
中国の二十四史の一。唐の太宗の命により房玄齢・李延寿らが撰。646年成立。晋の歴史を記したもので、帝紀10、志20、列伝70、載記30の全130巻。
大辞泉
「上巳の節句」と思われる行事については紀元前9~7世紀に成立したと考えられている中国の『詩経(しきょう)』の中に、こんな記述があるそうです。
「三月上巳に蘭を水上に採って不祥を祓除く」 (詩経鄭風)
「三月上巳」とは、三月の最初の巳の日ということで、必ずしも3日とは限りません。問題は次の、「蘭を水上に採る」です。上巳の節供の説明に登場した植物は「桃」ではなく「蘭」だったようです。
 蘭」が今日の何を指すかには諸説あるが、「蘭草」といわれるキク科の「藤袴」と、「蘭花」といわれるラン科の「春蘭」類の2系統があるようです。
蘭」が今日の何を指すかには諸説あるが、「蘭草」といわれるキク科の「藤袴」と、「蘭花」といわれるラン科の「春蘭」類の2系統があるようです。
「蘭草(フジバカマ)」は葉に香気があり、秋に開花する。「蘭花(シュンラン)」は花に香気があり、春に開花する。両者とも、その香気ゆえに珍重されたらしい。
 ここに登場する「蘭」は、我々の考える蘭ではなくて「藤袴(ふじばかま)」のことだと考えられているそうです。
ここに登場する「蘭」は、我々の考える蘭ではなくて「藤袴(ふじばかま)」のことだと考えられているそうです。
しかし、季節を考えると「春蘭」のほうが妥当だと私は思います。
芳香を放つ草は悪いもの、禍々しいものを祓う霊力があると考えられていたことから、これはそうした不祥を祓う行事だったのでしょう。
また「水上に採る」とは「水辺で採る」の意味です。水辺というのは水による穢れ祓い(禊ぎ)の際にこうした芳香を放つ草をその近くで調達したとかんがえられるようです。
詩経(しきょう)
[ 日本大百科全書(小学館)
中国最古の詩集。黄河流域の諸国や王宮で歌われた詩歌305首を収めたもので、『書経』『易経』『春秋』『礼記(らいき)』とともに儒教の経典(いわゆる五経)の一つとされた。西周初期(前11世紀)から東周中期(前6世紀)に至る約500年間の作品群と推測されている。
今からざっと3000年近く昔から、上巳の節句行事はあったようです。
ちなみに、「桃の節句」とは日本でつけられた名前だそうです。
雛壇の金屏風の花も「桃」ではなく「桜」です。
したっけ。


さて、平安時代の恋愛は、実際に逢うまでは女性優位利で、逢ってからは立場が逆転すると書きました。
逢瀬では、どんなに素敵な言葉を並べられても、独りになると男性が浮気しないかちょっと心配なんてことも多かったはずです。そんな気がかりも恋を深めるきっかけかもしれませんが・・・。
この歌も、不安に揺れる微妙な女心を歌ったものです。
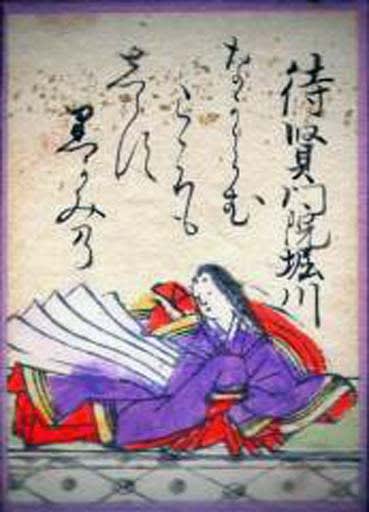 「長からむ 心も知らず 黒髪の 乱れて今朝は ものをこそ思へ」待賢門院堀河『千載集』
「長からむ 心も知らず 黒髪の 乱れて今朝は ものをこそ思へ」待賢門院堀河『千載集』
「(昨夜契りを結んだ)あなたは、末永く心変わりはしないといいましたが、どこまでが本心か心をはかりかねています。お別れした今朝はこの黒髪のように、私の心は心乱れて、いろいろ物思いにふけってしまうのです。」
昨夜一晩を一緒に過ごし、契りを結んだあなた。翌朝帰っていってから、後朝(きぬぎぬ)の歌をいただいて「いつまでも末長くあなたのことが好きですよ」と言葉をもらったけれども、その言葉はどこまで本当なのでしょうか。お別れした後、あなたの心をはかりかねて、この私の寝乱れた黒髪のように、心乱れて思い悩むばかりですわ。
この歌は、男が届けてきた後朝の歌に対する返歌という趣向で詠まれました。
そもそも平安時代というのは男性が女性の家に行って一晩を明かすという慣習がありました。「後朝」というのは男と女が一晩を明かした翌朝で、男が帰った後で女の許へ「昨夜はとても幸せだった」と一首詠んで贈る、という雅な慣習があったのです。
それに対して女性が返したのがこの一首というわけです。
この歌、女性が「あなたの誠意は本当でしょうか、心配です」という繊細な女性の心を表現したものです。
「黒髪の 乱れて・・・」というところなどに、情事の後の色香が漂う雰囲気が現れています。
いいですね。ファンタスティックとロマンティック、エロティックまでもが、チクチクと心に刺さります。
実はここに、心配ですなどといいながら男心の気を惹く、平安女性の激情と愛の技巧が現れているのです。
これだから、「女心」は理解できません。心配なのか、気を惹きたいのか、もっとわかりやすく伝えてほしいものです。
この歌はこの「黒髪」の表現の美しさで、百人一首の中でも際だっているといわれています。
日本女性の美しさの象徴として、黒髪が扱われているといっていいでしょう。
「待賢門院堀河(たいけんもんいんのほりかわ)」(12世紀ごろ)神祇伯(じんぎはく)・源顕仲(みなもとのあきなか)の娘で崇徳院の生母、待賢門院(鳥羽院の中宮・璋子(しょうし))に仕えて「堀河」と呼ばれました。
若いころに、もっと「百人一首」を勉強しておけばよかったと思うのは、私だけでしょうか。
したっけ。

 平安時代の恋愛は今と違って、男女が簡単に顔を合わせることができなかったそうです。
平安時代の恋愛は今と違って、男女が簡単に顔を合わせることができなかったそうです。
平安時代の女性における礼儀作法は、家族以外の男性には顔を見せない、口を利かないことでした。
女性は、寝殿造りの奥の間に隠れるように暮らしていました。これが、奥様の語源。
人前に出るときは扇で顔を隠さねばなりませんでした、女性が男性に顔を見せるということは、結婚を許したのも同然のことだったからです。
扇で顔を隠すのは、吹き出物がすごかったとか、化粧が剥げ落ちたのを隠すためとかの説もありますが・・・。
というわけで、平安の男性は女性の噂に恋をするのです。女の姿を実際に見ることができない平安時代においては、男性は女性の情報を集めることから恋が始まったのです。
美人であるか、教養はあるか、気立てはどうか、家柄は、財産は…。財産、家柄は重要でした。当時は、男性が女性の家に通い、やがて婿入りするという形でしたはら・・・。「通い婚」、「婿入り婚」
情報収集の直接自分で噂を聞き歩く方法や、その女性の侍女とのコネクションを活用する方法などです。
一方、女性のほうも黙って待っているばかりではありません。意図的によい「情報漏洩」して、情報操作をすることもあったようです。
ガセネタに引っかかった男性もいたはずです。
女性の情報に恋をした男性たちは、まず女に和歌を贈ります。
女性は受け取った和歌の良し悪しを見て、誘いに乗るか袖にするかを判断するのです。
最初は女性からの返事がないのが普通だったようです。今でも、しばしば使われる「じらし戦法」です。
そのうち、侍女の代筆で様子を伺われます。やがて女性の自筆の手紙をもらえるようになれば、ようやく男性の想いが女に認められたということになります。
さらに、何回かのやり取りの後で情熱を認められ、女性の家で一夜を過ごし、男性は初めて女の顔を見ることになります。
ここまでは、女性が一方的に有利な状況でした。
ところが、逢瀬を終えると、形勢逆転します。
互いに相手に不満がなければ男性は忍んで女性宅に通うことになります。
中には情報にほど遠い誇大広告の女性であることもあります。そんなときは、男性は通ってこなくなります。
形成を逆転された女性は女必死に和歌を贈ります。
つまり、平安時代には男女ともに容姿がいいとか悪いよりも、まず「うまい和歌」が作れるかどうかで恋愛が始まったのです。
女性の方も、技巧を効かせた和歌を返せば、あの女性は和歌が上手」と良い評判が広がります。
 その代表格は、平安のプレイガール「和泉式部(いずみしきぶ)」だったようです。
その代表格は、平安のプレイガール「和泉式部(いずみしきぶ)」だったようです。
最初の夫が和泉守・橘道貞(たちばなのみちさだ)だったので、和泉 式部の名前で呼ばれるようになりました。
このとき生んだ娘が、百人一首にも登場する小式部内侍です。
平安時代の代表的歌人で、自分の恋愛遍歴を記した『和泉式部日記』は時代を代表する日記文学となっています。
和泉式部は恋多き女性で、道貞と数年後破局した後、為尊(ためたか)親王、その弟・敦道(あつみち)親王と結ばれ、さらに2人の死後、一条天皇の中宮彰子に仕え、藤原保昌(やすまさ) も結婚します。晩年は消息不明です。
「あらざらむ この世の外の 思ひでに 今一度(いまひとたび)の 逢ふこともがな」和泉式部『後拾遺集』
「老いさらばえて、もうすぐ私は死ぬでしょう。あの世へもっていく思い出に、もう一度だけあなたにお逢いして、愛していただけたらと思うばかりです」
当時の平均寿命は27歳くらいだったそうです。
この歌から、女性の激情が強烈に伝わります。
もう今や自分が死にかけている息の下から、「あなたにもう一度逢いたい」と叫んでいるのです。(本当に死にかけているかどうかはわかりません)
「黒髪の 乱れも知らずうち臥せば まづかきやりし 人ぞ恋しき」和泉式部『後拾遺集』
「黒髪の乱れもかまわずに泣き伏していると、このような時に(昨夜この床で)真っ先にこの髪をかきなでてくれた人が恋しく思われます」
どうです、こんなことを言われたら・・・。
私は、残念ながら言われたことがないからわかりません。
したっけ。























