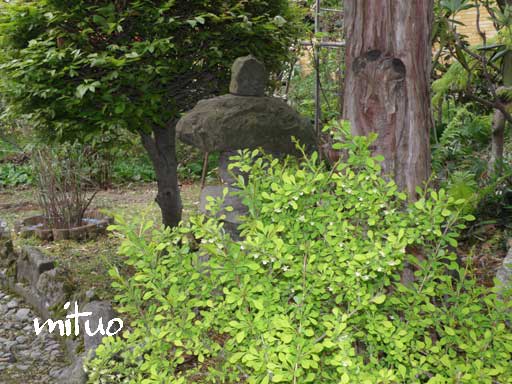都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
「蝦夷山躑躅(エゾヤマツツジ)」 ツツジ科ツツジ属の半落葉低木
花期:4月~5月
樹高:1m~4mくらい
分布:北海道と本州の北部(日本固有種で各地に分布する山躑躅の品種の1つです。)
山躑躅(ヤマツツジ)との違いは、葉が大きいことと、萼片の幅が広いことです。枝や葉の柄、萼などを含め、全体に毛が生えています。
葉は長さ3㎝から5㎝の楕円形で、互い違いに生えます(互生)。
枝先に集まってつくことが多い。
葉の質は薄く、表面は緑色で裏面は灰色を帯びています。
葉の先は丸く、縁には細かくて鈍いぎざぎざ(鋸歯)があります。
枝先に散形花序(枝先に1個つずつ花がつく)を出し、花径3㎝から5㎝の漏斗状の花を1輪から3輪つけます。
花冠の先は5つに深く裂け、雄蕊は5本です。葯(雄蕊の花粉を入れる袋)は黄色です。
花の色は赤を基調にするが、橙色がかったものや桃色がかったものなど変化に富んでいます。
花の後につく実は卵形のさく果(熟すると下部が裂け、種子が散布される果実)で、剛毛が生えています。
十勝では広尾町に多いことから「ヒロオツツジ」と呼ばれています。
名前の由来は、北海道産のヤマツツジの意味です。
花言葉は、「愛の喜び」、「情熱」、「初恋」です。
したっけ。
「磯躑躅(イソツツジ)」 ツツジ科 イソツツジ属の常緑小低木
花期:6月~7月
樹高:50㎝~100㎝くらい
分布:北方領土を含む北海道と本州の東北地方に分布(海外では、朝鮮半島、サハリン、シベリアなどにも分布)
育成地:亜高山や高山の湿原や林の縁
枝先に総状花序(柄のある花が花茎に均等につく)を出し、小さな白い花を球状につけます。
花径は1㎝くらいで、花冠は先が5つに裂けて横に開いています。
雄蕊が長くて花冠から飛び出しています。花には強い芳香があります。
葉は披針形で、互い違いに生え(互生)、葉の質は厚く、縁は裏面に巻き込んでいます。葉の裏面には白い毛が生えています。
「磯躑躅」には「磯」の名がついていますが海浜植物ではありません。
「イソ」の語源は「蝦夷」の転訛したものだと考えられています。昔は「エゾイシツツジ」と呼ばれていましたが、「エゾ」と「イソ」が同じ意味なので現在は「イソツツジ」と呼ぶのが一般的です。
精油には抗菌・殺菌作用があり、アロマテラピーで利用されるそうです。ただし、精油や蜜には揮発性の成分を含むので、長い時間嗅ぐと頭痛や眩暈を引き起こすそうです。
花の後にできる実はさく果(熟すると下部が裂け、種子が散布される果実)です。
花言葉:「初恋」
ツツジの語源と豆知識
躑躅(つつじ)の語源には多くの説があります。
①「ツヅキサキギ」で「続き咲き木」の意の説
②「ツヅリシゲル」で「綴り茂る」の意の説
③蕾の形が女性の乳頭に似ていることから、「タルチチ」で垂乳の転訛説
④ツツジのラッパ形をした花を古代人が「ツツシベ」と呼んだという。これは、花の筒形の中から長く突き出たオシベの意が転訛したとする説
⑤花が筒のように咲く様子から「ツツサキ(筒咲き)」の意の説、などがあります。
漢字名の「躑躅」は、漢語で「テキチョク」と読みます。これは、足踏みし、あがくが原義ですが、行っては止まる、躊躇(ちゅうちょ)するという意味にとらえると、咲く花が人の足を引き止める美しさにより、この漢字がツツジの「当て字」の和名として使われたものと推測されています。
ただし、本来は「羊躑躅」であり、羊がツツジの葉を食べて躊躇して死ぬ事からということです。
昨日の地元紙に広尾町のツツジで有名な公園のツツジがエゾシカの食害にあっていると載っていました。ツツジ祭りに花がない状態になりそうだと心配していました。エゾシカは食べても大丈夫なんでしょうか・・・。
「サツキ」は、皐月(五月の異名)躑躅で、サツキツツジの略。
したっけ。
「林檎(リンゴ)」 バラ科 リンゴ属 落葉低木、高木
花期:5月 実9~10月
樹高:2~5m
原産地:ヨーロッパ東南部およびアジア西部
育成地:涼しい地域
花は白から薄いピンクを帯び、花びらは5弁、雄蕊は約20本種類により若干異なりますが、直径3~5cm程度が標準です。実は、直径10~15cm程度まで成長します。
葉の長さ2.5~5㎝です。
日本では、明治時代にセイヨウリンゴの品種が多数入り、青森県・長野県・岩手県など東北地方でひろく栽培されています。
「林檎」は中国語です。「檎」は本来「家禽(かきん)」の「禽」と書き「鳥」を意味しています。果実が甘いため「林」にたくさん「鳥」があつまったことから「林檎」と呼ばれるようになりました。漢字が伝わった頃には「リンキン」、「リンゴン」などと読んでいたそうです。平安時代には「リンゴウ」と読んでいたという記録があるそうです。
我が家の「リンゴ」は実はなりますが食べられるほどにはなりません。従って、鳥も集まりません。
花言葉:「選択」
したっけ。
今まで「イボタノキ」だと思っていたのですが(そういわれて買った)、どうも違う気がして調べてみました。やっぱり違う木でした。北海道には自生しない木でした。
「目木(メギ)」 メギ科 メギ属の落葉低木
花期: 5~6月
樹高:1.0~3.0m
分布:日本固有種で本州の関東地方から九州
育成地:山地や丘陵の草地や林の中など
よく枝分かれをし、針状の細い刺が枝や葉のつけ根に生えます。
このため、「コトリトマラズ」や「コトリスワラズ」の別名もあります。
葉は箆形(へらじょう)で、長枝では互い違いに生え(互生)、短枝では束になって生えます(束生)。
葉の縁にぎざぎざ(鋸歯)はありません。短枝から新しい葉とともに短い花序が出て、黄色い花を数個下向きにつけます。
花は、同じメギ科の柊南天(ヒイラギナンテン)に似ていて、それを小さくしたような感じである。
花径は5~6㎜くらいで、花弁と萼片が6枚ずつあります。
萼片のほうが花弁よりも大きくて、萼のほうが花びらのように見えます。
雄蕊も6本あります。
10月ころには楕円形をした液果(果皮が肉質で液汁が多い実)が赤く熟します。
紅葉もきれいです。
名前の由来は、枝などを乾燥させたものを生薬で小蘗(しょうはく)といい、結膜炎などの目の病気に効異によります。(煎じて洗浄に使用)
また、生垣として利用されている。北海道に自生してはいませんが、耐寒性は十分あるようです。
花言葉は「過敏」、「貴方の助けになる」
したっけ。
今日は、玄関脇のコーナーに植えてある「黄花石楠花」を紹介します。
「黄花石楠花(キバナシャクナゲ)」ツツジ科ツツジ属の常緑小低木
花期:6月~8月
樹高:5㎝~30㎝程度(幹は地を這う)
生育地:北方領土を含む北海道から本州の中部地方にかけて分布し、高山のハイマツ帯から上に自生します。(海外では、朝鮮半島北部、中国東北部、サハリン、東シベリアなどに広く分布)
葉は楕円形で先は丸く、互い違いに生えます(互生)。
葉の質は革質で硬く、縁は裏側に巻き込んでいます
花径3㎝くらいの淡い黄色の花を枝先に数輪ずつつけます。これが、黄花石楠花の語源です。
花冠は漏斗状で、真ん中に茶色い斑点があります。
雄蕊は10本です。
花の後にできる実はさく果(熟すると下部が裂け、種子が散布される果実)です。
なお、漢字で「石楠花」と書くのは、「石南花」を呉音読みした「シャクナンゲ」が転訛した名前です。「石楠」、「石南」と書くのは、石の間の南側の土地を好むことに由来します。中国で言う「石南」は漢名の石南はバラ科のオオカナメモチのことで誤って名づけられたものとされています。
その他、「シャクナゲ」の語源は、枝が曲がっていてまっすぐな部分が1尺にもならないことから「シャクナシ」、これが転訛してシャクナゲになったとか、「癪に利くから」など諸説あるようですが俗説とされています。
花言葉:「威厳」、「厳格」、「壮厳」
したっけ。
今日は、昨日に引き続きもうひとつ「立坪菫」を紹介します。
「大葉立坪菫 (オオバタチツボツボスミレ)」 スミレ科スミレ属の多年草
花期: 5~7月
草丈: 20~30 cm程度。
生育地:北方領土を含む北海道や本州北部の山地や亜高山の林の中や湿原に生えます。
葉はハート形で、長さが7㎝くらいあります。
葉の縁には波状のぎざぎざ(鋸歯)があります。
花径は2㎝から3㎝で、花の色は淡い紫色や紅紫色で、すべての花弁に濃い紫色の筋が入っています。
側弁のつけ根の部分には白い毛がたくさん生えています。
距(花冠のつけ根が後ろに飛び出たもの)は短い。
花の後にできる実はさく果(熟すると下部が裂け、種子が散布される果実)です。
和名の由来は、大型の葉をもつタチツボスミレの意味です。
「タチツボ」の「坪」とは道端や庭の意味で、そういう身近な所で見られることからツボスミレというそうです。「立」は、花の盛りを過ぎると茎がしだいに立ち上がってくることに由来します。
環境省のレッドリスト(2007)では、「現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては『絶滅危惧』に移行する可能性のある種」である準絶滅危惧(NT)に登録されています。
花言葉:ありません。立坪菫の花言葉は「つつましい幸福」、「誠実」
したっけ。
「蝦夷の立坪菫(エゾノタチツボスミレ)」 スミレ科 スミレ属の多年草
花期:4~7月
分布:北海道・本州(海外では、朝鮮半島、中国の東北部にも分布)
草丈:20㎝から40㎝くらい(スミレの中では背が高い)
環境:山地・低山,森林・林縁,原野・草原
茎の下部につく葉は卵形またはハート形で小さい。茎の上部につく葉は長い三角形で、長さは25㎜から50㎜ミリくらいです。
托葉は櫛状に深く切れ込み、毛が生えています。
葉の脇から5㎝から10㎝くらいの柄を出し、花径15㎜から20㎜くらいの小さな花をつけます。
花の色は白ないし淡い紫色です。花びらは5枚であり、2枚の上弁はウサギの耳のように反り返っています。白花は青紫系の色素が発現しない突然変異で、一般には見かけるのはかなりまれだそうです。
2枚の側弁のつけ根には細かい毛がたくさん生えています。
雌蕊の柱頭にも突起毛があります。
距(きょ:花冠のつけ根が後ろに飛び出たもの)は白くて短い。
萼片は細長い。
花の後にできる実はさく果(熟すると下部が裂け、種子が散布される果実)です。
語源は北海道のタチツボスミレの意味です。「タチツボ」の「坪」とは道端や庭の意味で、そういう身近な所で見られることからツボスミレというそうです。「立」は、花の盛りを過ぎると茎がしだいに立ち上がってくることに由来します。
花言葉:ありません。立坪菫の花言葉は「つつましい幸福」、「誠実」
したっけ。
「常盤姫萩(トキワヒメハギ)」 ヒメハギ科 ヒメハギ属耐寒性常緑低木
樹高:10~30cm(自宅のものは10㎝ほど)
開花期:3~5月
原産地:ヨーロッパ、アルプス山脈などに分布
分布:標高900~2500mの林の中など
ピンクの花弁で先端に黄色が入るカラフルな色の小花を咲かせます。
葉の脇に花径1㎝チくらいの小さな花を1~2個つけます。花は蝶形で、竜骨弁が黄色く、翼弁と旗弁は紅紫色です。
竜骨弁:蝶形花(ちょうけいか)で、翼弁の下位につく左右一対の花びら
翼弁:蝶形花(ちょうけいか)で、左右一対ある花びら。鳥の翼に見立てていう。その上方に旗(き)弁、下方に竜骨(りゅうこつ)弁がある。
旗弁:蝶形花(ちょうけいか)で、上方にある1枚の花びら。 旗を立てたような形なのでいう。
葉は披針形で、互い違いに生える(互生)。葉の質は革質で艶があります。
花の後にできる実はさく果(熟すると下部が裂け、種子が散布される果実)です。
地を這ってマット状に広がります。基本種の白花常盤姫萩(シロバナトキワヒメハギ)は翼弁と旗弁が白いそうです。常盤姫萩はその変種だそうです。
名前の由来は、常緑でマメ科のハギに似た小型のハギからこの名が付いたそうです。ハギはマメ科ですが、こちらはヒメハギ科です。
花言葉:「節制」、「信じる恋」
したっけ。
「五葉躑躅(ゴヨウツツジ)」 ツツジ科 ツツジ属の落葉低木
開花時期:4月から5月
樹高:2mから4m(自宅のものは1mくらい)
原産地:日本固有種です。
分布:本州の東北地方から近畿地方にかけてと四国に分布し、太平洋側の山地に生えます。
葉は倒卵形で、枝先に5枚が輪生状に互い違いに生えています(互生)。和名の「五葉躑躅(ゴヨウツツジ)」は枝先に五枚の葉をつけることに由来しています。
葉の先は尖らない。
葉には細かい毛が密生しています。
葉の展開と同時に花を咲かせます。
花の色は白く、花径は3センチから4センチくらいで、上部の裂片には緑色の斑が入っています。
花の後にできる実はさく果(熟すると下部が裂け、種子が散布される果実)です。
花言葉:「愛の喜び」、「上品」
したっけ。
バラ科 ボケ属 落葉低木
開花時期:11/25頃~ 4/15頃(北海道は5月)
樹高:2m.
原産地:中国
日本には「平安時代」に渡来したといわれます。
花の色は赤、白、ピンクなど。五弁花が前年枝に数個ずつつきます。花径は2~3㎝です。
11月頃から咲き出す花は、春に開花するものと区別するために「寒木瓜(かんぼけ)」と呼ばれることがあります。
枝にトゲがある場合とない場合があるそうですが、自宅の木はトゲがあります。
秋には5~6㎝ほどの楕円形の実をつけます。この果実は黄熟し、良い香りがします。果実酒は、香り高く疲労回復や筋肉のケイレンに良く利くといわれています。
この果実は枝についたままで年を越します。
実が瓜のような形であるところから「木瓜」と書き、「モケ」、「モッケ」、「モッカ」と呼んでいたのが次第に「モケ」→「ボケ」になったそうです。(「ボックワ」→「ボケ」の説もあります。)
『広辞苑』で「木瓜」の項を見ると、「キウリ」、「キュウリ」、「ボケ」、「ボッカ」、「モケ」、「モッカ」、「モッコウ」の読みが載っていました。
花言葉:「熱情」・「平凡」・「妖精の輝き」・「魅感的な恋」
したっけ。