都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
何処の家にもある玄関。普段何気なく使っている「玄関」ですが、何故入り口のことを、こう呼ぶのでしょうか。実は、「玄関」とは由緒ある言葉なようです。
「玄関」は、皆様ご存知の通り建物の正面にある入り口のことですが、元は中国の『老子』の「玄のまた玄なる衆の妙なる門」による言葉だそうです。日本では鎌倉時代に禅宗で用いられた仏教語だそうです。
もともと「玄妙(奥深く微妙なさま)な仏道(真理)に入る関門(通過するのに困難を伴うところ)」という意味であったそうです。
玄関の名称の由来は鎌倉時代に遡ります。禅僧の栄西が京都東山に建仁寺を建立した時に、僧院の門を玄妙なる関門として「玄関」と命名したのが始まりとされています
「僧院の門」として命名した「玄関」は、「幽玄で僧坊への関門」という意味があり、外界と内界との接点を表わす仏門としての大切な入口でした。
えいさい【栄西】
[1141~1215]平安末・鎌倉初期の僧。備中(びっちゅう)の人。字(あざな)は明庵。日本臨済宗の祖。はじめ比叡山で天台密教を学んだ。二度宋(そう)に渡って禅を学び、帰国後、博多に聖福寺、京都に建仁寺、鎌倉に寿福寺を建立。また、宋から茶の種を持ち帰り、栽培法を広めた。著「興禅護国論」「喫茶養生記」など。千光国師。葉上房。ようさい。
大辞泉
特に禅宗寺院では禅宗入門の第一歩をしるす場所として重んじられました。禅宗では入門しようとしても、簡単には入門させてくれなかったそうです。
 玄関の門を叩き、「入門をお願いいたします」と言うと、奥から修行僧が出てきて、「あいにく、部屋がいっぱいで、あなたを受け入れる余裕はございません。申し訳ございませんが、お帰り下さい」と慇懃(いんぎん)に断られるのが通例だったそうです。
玄関の門を叩き、「入門をお願いいたします」と言うと、奥から修行僧が出てきて、「あいにく、部屋がいっぱいで、あなたを受け入れる余裕はございません。申し訳ございませんが、お帰り下さい」と慇懃(いんぎん)に断られるのが通例だったそうです。
しかし、本気で入門する覚悟を持った人は、一度入門を断られたからといって、「はい、そうですか」と引き下がる訳にはいきません。
入門を断られたのですから、寺の門の中には入れませんので、 門の外に座って、入門の許しを得るまで待ち続けなければなりません。夕方になると、中から僧が出てきて、バケツの水を頭からかぶせられ、「帰れ、ここはおまえの来るところではない」等と怒鳴られたそうです。
雨が降ろうと雪が降ろうと、そのまま放置されます。
そうして三日間ほどたつと、寺の中から、柔和な僧が出てきて、入門希望者を寺の中へと招じ入れてくれたそうです。このように入門制度は、非常に厳しいものだったようです。
修行に対する甘い考えを吹き飛ばし、道を求める謙虚な態度を芽生えさせる意味があったといわれています。
室町時代に至って武家や公家の居宅に禅寺の形式が取り入れられるようになり、和風住宅建築の一様式として江戸時代に完成し、「玄関」が一般住宅の出入口をいうことばとして定着したそうです。
玄関に入るということは、厳粛な意味があったのですね。由来を知ると、靴を脱ぎ散らかしたり、開けっ放しにしたりはできないですね。
したっけ。
 「台所」のことを、「お勝手」と呼ぶのは、意外なことに弓道が関係しているのです。
「台所」のことを、「お勝手」と呼ぶのは、意外なことに弓道が関係しているのです。
弓道では弓を支える左手を「押し手」と呼び、もう一方の、自由に動かせる右手のことを「勝手」というそうです。
箙(えびら:矢を入れる道具)から矢を抜くことを「刈る」と言い、「刈る手」から転じて「勝手」になったと考えられるそうです。
この呼び方にちなんで、女性が自由に使える台所のことを「お勝手」と呼ぶようになったそうです。
かっ‐て【勝手】
[名]
1 台所。「―仕事」
2 暮らし向き。生計。「―が苦しい」
3 自分がかかわる物事のようす・事情。「仕事の―がわからない」「―が違う」「―知ったる他人の家」
4 弓の弦を引くほうの手。右手。左手より力が勝ちやすいからいう。引き手。
大辞泉
現代の女性は、台所だけではなく、リビングも寝室もいたるところを勝手に使っていますが、昔は女性の思い通りになる場所といえば、一切を任される台所しかなかったのです。
誰ですか、自分にも「お勝手」が欲しいよとお嘆きの男性は・・・。お察し申し上げます。
したっけ。
夏が近づき、いよいよ電力問題が心配になってきました。
一部の会社は、営業時間や営業日をずらすなど、各自節電への取り組みの発表をしています。
でも夏は本当に暑いですから、クーラーを付けないのは正直厳しいですよね。
そこで今回のお題は、クーラーがない部屋と暖房がない部屋住むならどっち?
クーラーは無くても、暖房がない部屋よりはまし!という方や、その逆の方も、どしどしご意見ください!
これからの季節、節電も大事ですが、みなさんのお身体も十分にお大事になさってください。
久々の「ブログ人投票箱」と思ったら、なんてえ質問だい 。日本
。日本 は広いんだぜ。日本人がみんな東京に住んでいると思っている人間の発想だ
は広いんだぜ。日本人がみんな東京に住んでいると思っている人間の発想だ 。
。
こっちとらあ、北海道に住んでんだよ。そりゃあ、北海道だってオレの住んでいるところは、夏にゃあ30度超える日 もあるよ。だけど、夜にゃあ涼しくなる。本当に夜も暑い日は一週間ほどしかない。
もあるよ。だけど、夜にゃあ涼しくなる。本当に夜も暑い日は一週間ほどしかない。
そのかわり、寒い日は多いぜ。真冬は氷点下25度だ 。今日だって雨が降っていて寒くて暖房入れている。暖房っていたって電気じゃあ間に合わない。灯油だよ。
。今日だって雨が降っていて寒くて暖房入れている。暖房っていたって電気じゃあ間に合わない。灯油だよ。
そんなところに住んでる人間に、「クーラーがない部屋と暖房がない部屋住むならどっち?」なんて聞かれたって、考える余地はないいってもんよ 。
。
氷点下25度以下の生活したこと無いんだろうよ。暖房なけりゃ死んじゃうよ 。
。
暖房は節電にはならないってことさ。灯油も値上がりしたから節油には心がけるがね。
沖縄の人たちにしてみりゃあ、暖房なんかなくたってなんくるないさぁって言うんでないかい。
いずれにしても、これからは節電には心がけなきゃならんことには間違いないけどな 。
。
したっけ。
「麻婆豆腐」の名前の由来には諸説あります。
昔、清の時代、四川省成都市で「豆花飯(ドウホワファン)」という料理を作って商売をしている、陳富文の妻がいました。豆花飯とは、にがりを入れたばかりのやわらかい豆腐(豆花)をご飯にかけて、辛いタレで食べるものだそうです。
 ある日、油売りが肉を少々買い、彼女に何かおいしいものを作ってほしいと頼みました。彼女は肉を細かく切って炒め、豆板醤で味をつけ、豆花を入れて1つの料理を作りました。これがとてもおいしいと評判になりました。
ある日、油売りが肉を少々買い、彼女に何かおいしいものを作ってほしいと頼みました。彼女は肉を細かく切って炒め、豆板醤で味をつけ、豆花を入れて1つの料理を作りました。これがとてもおいしいと評判になりました。
陳富文の妻がこの料理を考案したのですが、この妻には「あばた」があったので「陳という、あばたのある妻が作った豆腐料理」という意味で「陳麻婆豆腐(ツェンマーポートウフウ)」という名前がついたようです。
つまり「麻」は、中国語の「あばた」、「婆」は「妻」を意味していたわけです。
 この陳さんの威光はいまだに健在で、成都の料理店で麻婆豆腐を出す際も陳さんの家系・関係者以外が経営する料理店では、当然ながら、「陳麻婆豆腐」は名乗ることが出来ないという由緒正しき料理名のようです。
この陳さんの威光はいまだに健在で、成都の料理店で麻婆豆腐を出す際も陳さんの家系・関係者以外が経営する料理店では、当然ながら、「陳麻婆豆腐」は名乗ることが出来ないという由緒正しき料理名のようです。
昭和27年(1952年)中華の鉄人で御馴染の陳建一の父、陳健民が来日して日本人の口に合うようにアレンジしてこの料理を紹介しました。
麻婆豆腐
麻婆豆腐(まーぼーどうふ)は中華料理(四川料理)の1つで、挽肉と赤唐辛子・花椒(山椒の同属異種)・豆板醤(豆瓣醤)などを炒め、鶏がらスープを入れて豆腐を煮た料理。
Feペディア
 その他、日本ではあまり使いませんが、四川ではこの料理に欠かすことのできない「花椒」の粒が黒く点々と入っている様子が「あばた」に似ていることから、この名前がついたという説もあります。
その他、日本ではあまり使いませんが、四川ではこの料理に欠かすことのできない「花椒」の粒が黒く点々と入っている様子が「あばた」に似ていることから、この名前がついたという説もあります。
四川省では、花椒は粒で入れるほか、仕上げにも粉にしたものを振りかけるそうです。少々ではなく大量に掛けるので表面が黒くなるほどだといいます。「麻」(山椒の痺れるような辛味)、「辣」(唐辛子の辛味)、そのどちらが不足しても本場の麻婆豆腐にはならないそうです。
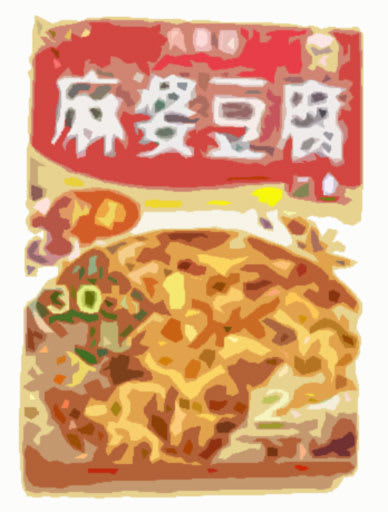 また、「婆」ですが、「婆」という文字を料理に付けるのも、ちょっと問題だと考えすぎた人もいるようです。
また、「婆」ですが、「婆」という文字を料理に付けるのも、ちょっと問題だと考えすぎた人もいるようです。
色々と考えた末、元々がとても辛い料理なので、辣油(ラー油)の辣から麻辣豆腐(マーラートウフウ)という名前で供することにした料理店も、一部にはあるようです。
麻婆豆腐は、今では簡単に出来る家庭でも御馴染の料理となりましたね。
したっけ。
中国で初めて豆腐が作られたのは、紀元前2世紀、前漢の淮南王・劉安が初めて作ったという伝説がある。これは、16世紀(1578年)に明朝の李時珍(りじちん)が著した中国の書『本草綱目(ほんぞうこうもく)』での記述がもとになっており、あくまでも伝説の域を出ない。
別に五代(10世紀)頃の農民の発明とする説もあります。
豆腐について同時代的に書かれはじめるようになったのは唐代と言われ、現在確認できる文献上では淮南王(わいなんおう)・劉安(りゅうあん)の時代からずっとあとの北宋(960~1127年)の初めに陶穀の著した『清異録』にある「豆腐」の語が一番古いとされている。
 「豆腐」が発明された頃の中国では、「腐」という語は、もともと固まりでやわらかく弾力があるもの、「ブヨブヨしたもの」という意味があったそうです。
「豆腐」が発明された頃の中国では、「腐」という語は、もともと固まりでやわらかく弾力があるもの、「ブヨブヨしたもの」という意味があったそうです。
豆腐は豆が腐ったから「豆腐」と名付けられたのではなく、豆を加工してブヨブヨしたものだから「豆腐」なのです。ですから腐っているという解釈はあてはまりません。
現代では、「腐」の意味は中国も日本と同じだそうです。
日本へは奈良時代(710~784年)に、中国に渡った遣唐使の僧侶等によって伝えられたとされていますが、明確な記録はありません。豆腐が記録として登場したのは、寿永2年(1183年)、奈良春日大社の神主の日記に、お供物として「春近唐符一種」の記載があり、この「唐符」が最初の記録といわれています。
「とうふ」という読みは、中国語読みの「doufu」そのままの借用語です。もちろん中国でも「豆腐」は「豆腐」です。
いずれにしてもわが国で豆腐が造られたのは、奈良・平安時代からといえそうです。
当初は、寺院の僧侶等の間で、次いで精進料理の普及等にともない貴族社会や武家社会に伝わり、室町時代(1393~1572年)になって、ようやく全国的にもかなり浸透したようです。製造も奈良から京都へと伝わり、次第に全国へと広がっていきました。
「豆腐」という漢字が記述されたのは、鎌倉時代の日蓮上人の書状(1280年)からだそうです。
納豆の起源は中国の「鼓」(し)という食品ではないかという説があります。この鼓こそ、麹菌納豆です。鼓の伝来時期は明らかでありませんが、本格的に作られるようになったのは、奈良時代のことではないかと考えられます。鼓の製造には大量の塩が必要です。貴重品であった塩が流通しはじめるのと同じころに、鼓の製造が始まったのではないかと考えられます。
中国で豆鼓(とうち)は味噌の一種で調味料。蒸した大豆を塩漬けにして発酵させたものだそうです。日本のみそとしょうゆを合わせたような味で、塩辛いが濃いうまみがあるといわれます。乾燥させると塩納豆になります。
中国から伝来した当初は「久喜」(くき)」といっていました。この頃は、現在の糸引き納豆とは違うものだったと考えられているそうです。
後三年の役(1051~1087年)で安部貞任(あべのさだとう)、安部宗任(あべのむねとう)を征伐すべく睦に下った八幡太郎義家(はちまんたろうよしいえ)が、平泉付近に陣をしき、近所から集めた大豆を煮ているときに、敵の急襲を受けた。このとき義家は、せっかく煮立てた豆を捨てるのはもったいないと、急いで藁俵に詰めて馬の鞍に乗せた。戦いに後、その大豆を取り出すと納豆ができていたという。
また、弥生時代に偶然できたという説もあります。
「納豆」の語源は昔、僧が寺院の台所、すなわち「納所(なっしょ)」で作られた豆だから「納豆」と元禄時代の『本朝食鑑(ほんちょうしょっかん)』(1695年)に書かれているそうです。
よく、「豆腐」と「納豆」は文字が逆ではないかという話がありますが、そうではないようです。
したっけ。
キバナシャクナゲ(黄花石楠花) ツツジ科 ツツジ属 シャクナゲ亜属
学名:Rhododendron aureum
花 期:6~7月
生育地:高山の草原、砂礫地や岩の隙間に生える。
名前の通り黄色い花を付けるシャクナゲで、シベリア東部・満洲・朝鮮半島北部・樺太・千島列島・カムチャツカなど東アジアの寒冷地に広く分布する。
背丈10~30㎝の常緑低木。幹は地面を這い、多くの枝を立ち上げます。
葉は長さ3~6㎝の長~広楕円形で無毛、質は厚くて硬く、表面は葉脈に沿って凹み、ややしわ状となります。
花は枝先に5~6個集まって付き、花冠は径3~4㎝の漏斗形で、先が5裂し、上部裂片内側に濃色の斑点があります。
果実は長楕円形で褐色の毛が密生しています。
花の咲き初めは淡黄色をしているのですが、時間が経つと段々と赤味がかってきます。
玄関脇の一角に植えてあります。
したっけ。
ムラサキケマン(紫華鬘) ケシ科 キケマン属
学名:Corydalis incise
別名:ヤブケマン(藪華鬘)
花期:春 5~6月
軟弱な2年草で、茎には稜があり無毛です。
葉は1~2回3出複葉で小葉はさらに深裂し、縁には鋸歯があります。根出葉には長い柄があり、茎葉にも柄があります。
花は長さ1,2~2㎝、花弁は4枚有り、上弁の後方は距となります。
※距(きょ):植物の花びらや萼(がく)の付け根にある突起部分。内部に蜜腺(みっせん)をもつ。
花柄の基部に扇状くさび形の苞があります。花は紅紫色,ときには白もあるそうで筒状です。
果実は長さ1.2㎝前後の円筒形です。
花の色から紫華鬘と名付けられました。華鬘とは仏殿の装飾のことです。
平地や山麓の日陰のやや湿った所に生える越年草です。
知らない間に、大量に増えました。雑草が生えずにいいので、放置しています。
したっけ。
「らち」とは「埒」と書きます。「埒」の意味は、低い垣や柵のことで、馬場などの周りの柵をさす言葉です。
「柵」や、「仕切り」、「区切り」みたいなものです。
らち【埒】
1 馬場の周囲に巡らした柵。2 物の周囲に、また仕切りとして設けた柵。駅の改札口付近の柵など。3物事の区切り。また、限界。「職権の―を超える」
大辞泉
 この「埒」を使う言葉に、「不埒(ふらち)」があります。不都合、不届き、不法といった意味です。
この「埒」を使う言葉に、「不埒(ふらち)」があります。不都合、不届き、不法といった意味です。
「不埒なやつ」などと聞いたことがあるとおもいます。現在ではあまり使いませんが、時代劇ではよく使われます。
また、「埒内(外)(らちない、がい)」とは、範囲の内(外)、限界の内(外)という意味です。
「埒」は「枠」や「境」の意味ですから判りやすいと思います。
「埒があく」とは、物事にきまりがつく、かたがつく、といった意味です。
枠や囲いが開くことでしょうか。なんだかしっくりきませんね。
「埒があかない」という言葉があります。こちらの由来は、奈良時代、春日大社の祭礼において、前夜、神輿の周囲に柵(埒)をつくり、翌朝、能楽の金春太夫(こんぱるだゆう:当時の猿楽のシテ役のこと)が一人で中に入って、祝詞をとなえる習慣がありました。
この儀式が終わると、埒があいて、ほかの参加者も中に入れる、ということから、埒があく、つまり祭礼が進行するということになります。
このことを踏まえて、「埒があかない」は祭礼が滞る、はかどらず、じれったい、というようになった、という説があります。これは、ちょっとおかしいのです。
「埒があく」は、「埒が開く」ではなくて「埒が明く」と書くからです。もちろん「あかない」も「明かない」です。
埒(らち)が明・く
物事にきまりがつく。かたがつく。「電話では―・かない」 「そんなことなら、わけもなく、―・くんだよ」〈浜田・泣いた赤おに〉
大辞泉
つまり、同じ「あく」でも、「ひらく」の意味の「開く」ではなく、「あきらかにする」の「明く」なんです。
「埒が明く」、「埒を付ける」とは、埒(柵)を付けることによって、物事の境をはっきりさせる、転じて、きまりがつく、かたがつく、という意味になったのです。
反対の意味である、「埒が明かない」は、きまりがつかない、かたがつかない、という意味です。
「電話では、埒が明かない。今からそっちへ行く。」などと使いますね。
「あく(明く)」を「開く」と誤解して、「開く」にこじつけた語源・由来になってしまった例です。本来の意味は、物事の進行具合などとは関係なく、柵、境、枠などをつけて、物事をはっきりさせる、きまりをつける、ということです。
したっけ。






































