都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
昨今、一人カラオケや、一人焼肉などが、一部では人気があるようです。一人ならではの有意義な時間を楽しむ方が多くなっているのではないでしょうか。
そんな中で、旅行会社の一人旅のツアーも充実してきているように思います。
さて、皆さんは、一人旅をしたいですか?したくないですか?
一人旅の経験談などもありましたら、ぜひお聞かせください。
おや、今回はずいぶん恐る恐る聞いているではありませんか。
しかし、「一人カラオケ 」や、「一人焼肉
」や、「一人焼肉 」と「一人旅」は一緒にしちゃあいけないでしょう。
」と「一人旅」は一緒にしちゃあいけないでしょう。
一人カラオケや、一人焼肉の場合は、やむを得ず「一人」なんだろうよ。自ら好んで一人でカラオケや焼肉に行くかなあ?
だとしたら、寂しすぎるんでないかい 。ダレもいない部屋にむなしく響く自分の声
。ダレもいない部屋にむなしく響く自分の声 。一人で肉をひっくり返して、煙が目にしみる。涙も出るだろうよ
。一人で肉をひっくり返して、煙が目にしみる。涙も出るだろうよ 。
。
「一人旅」ってのはさ、傷心 を抱えて自分探しに行く先もなく・・・。そういう、言うに言えない思いってのがあるだろうよ。
を抱えて自分探しに行く先もなく・・・。そういう、言うに言えない思いってのがあるだろうよ。
どこかの町で、行きずりの恋を求めていくのかもしれない。
いいなあ・・・。私も「一人旅」してみたいなあ・・・。ゴメが鳴いてる港町 。雪深い温泉宿
。雪深い温泉宿 。無口なマスターのいるカフェ
。無口なマスターのいるカフェ 。
。
でも、私は極端な出不精なんだよ。憬れるけど、一人は面倒くさいな。
やっぱり、誰か面倒見てくれる人が必要だな。
でも、二人旅じゃあ、出会いはないだろうな・・・。酒 も飲めないし・・・
も飲めないし・・・ 。
。
したっけ。
「ちゅうじつ」と読んだ人は真面目な人。もちろん「ちゅうじつ」で間違いありません。
ちゅう‐じつ【忠実】
[名・形動]
1 まごころをこめてよくつとめること。また、そのさま。「職務に―な人」「―な臣下」「―に任務を遂行する」
2 内容をごまかしたり省略したりせずそのままに示すこと。また、そのさま。「原文に―な翻訳」「史実に―に再現する」
[派生] ちゅうじつさ[名]
大辞泉
実は「まめ」とも読みます。
「まめまめしい」という言葉があります。
他にも「筆まめ」「小まめ」「手まめ」「足まめ」などの「まめ」表現があります。
最近では「まめ」にメールのやり取りをするなどとも使われます。
この「まめ」は「豆」じゃありませんよ。「忠実」と書きます。
奈良時代からある言葉で、元々「誠実でまじめであるさま」をいっていました。
平安時代には、「真心を持って相手を思う」意味で使われました。
鎌倉時代以降、「面倒がらずに勤勉によく働くこと」という意味が派生しました。また、体が丈夫なさまを表すようになりました。「まめに暮らす」という言葉を聴いたことはありませんか。これはまめまめしく働いて暮らすことではなく、「達者に暮らす」という意味なのです。
まめ【忠=実/▽実】
[名・形動]
1 労苦をいとわず物事にはげむこと。また、そのさま。勤勉。「―に帳簿をつける」「若いのに―な人だ」「筆―」
2 からだのじょうぶなこと。また、そのさま。健康。たっしゃ。「―で暮らしております」「―なのが何より」
3 まじめであること。また、そのさま。実直。本気。誠実。
「いと―に、じちよう(=実用本位)にて、あだなる心なかりけり」〈伊勢・一〇三
4 実際の役に立つこと。実用的であること。また、そのさま。
「をかしきものは…君達に、―なるものは北の方にと」〈落窪・四〉
大辞泉
津軽弁では「な、まめしてらな~」っていうのは「あなたは元気ですか」だそうです。
この「まめ」という言葉の語源にはいくつかの説がありはっきりわかりません。
「マミ(真実)」の転とする説、「マジメ(真面目)」の略とする説、「マミ(正身)」の義とする説です。
したっけ。
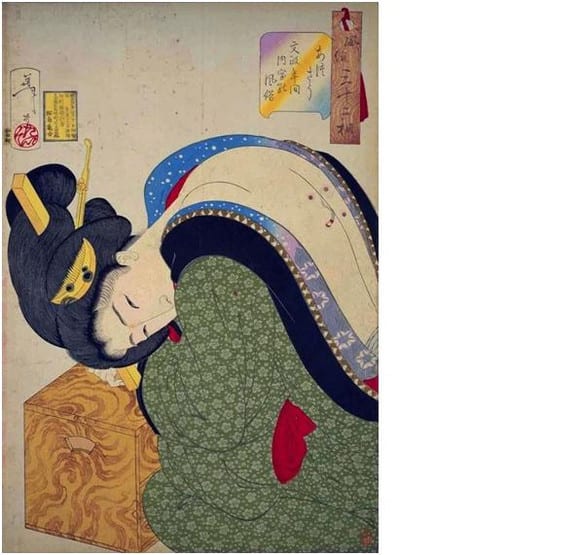 鍼灸(しんきゅう)療法から出たことばで、物事の始め、最初のことを意味する。
鍼灸(しんきゅう)療法から出たことばで、物事の始め、最初のことを意味する。
最初に打つ針や最初にすえる灸は大変痛く、まるで身の皮を切られるようだ、ということから使われた言葉です。
1603年『日葡辞典(にっぽじてん)』(日本語をポルトガル語で解説した辞典)には「最初の灸」と解説があるそうです。
何事も最初は苦しいとの例えとして「皮切りの一灸」と言う諺がある。
皮切りの一灸
〔補説〕 最初にすえる灸が特別熱いところから何事も最初は苦痛で困難であることのたとえ。
大辞林
物事の始めを表す言葉に「手始め」というのがあります。「皮切り」が「手始め」と違う点は、「皮切り」には、勇気や根気がいることの始まりというニュアンスがあります。
○○の全国ツアーは、大阪を皮切りに各地で行われます・・・のように。
なお、灸をすえて効果があがるところを「ツボ」と呼び、そこから「ツボを抑える」「ツボを心得る」などの言葉が出来ました。
したっけ。
ファスナー(英語: fastener)とは、衣類などに用いる留め具のうち、何度でも自在に開け閉めできるものである。ファスナーは英語で「しっかり留めるもの」を意味する。構造から、点、線、面のファスナーに大別される。
工業分野では、ファスナーを使って複数部材を組み合わせ接合することをファスニングという。
ウィキペディア
「点ファスナー」には、ボルトやナット、ねじ、釘、リベット、スナップボタンなどがあり、「点」で留めるための器具をいいます。
「線ファスナー」は、いわゆる「ファスナー」です。チャックやシール付きビニール袋のジッパーなど、留める部分が線状になっているものです。
「面ファスナー」は、ベルクロテープ(マジックテープ)などの「面」で留めるものをいいます。
ここでは、「線ファスナー」といわれる、ファスナー、ジッパー、チャックについての話です。
いわゆる「ファスナー」は、正式には「slide fastener(スライドファスナー)」という英語の一般名詞です。
 この便利な器具は、1890年、アメリカ人のホイットコム・L・ジャドソンという人が、靴紐のかわりになるものを考えた「clasp-locker(クラスプロッカー)」が起源とされています。これは、彼が生きている間は普及しなかったようです。
この便利な器具は、1890年、アメリカ人のホイットコム・L・ジャドソンという人が、靴紐のかわりになるものを考えた「clasp-locker(クラスプロッカー)」が起源とされています。これは、彼が生きている間は普及しなかったようです。
後に製品化されていき、普及していくわけですが、その途上、アメリカではBFグッドリッチ社が1918年、アメリカ海軍向けの飛行服に、このファスナーが使いました。1923年、BFグッドリッチ社はゴム製オーバーシューズにファスナーを使うようになり、これを「Zipper(ジッパー)」というネーミングで売り出したため、「ジッパー」が定着しました。
日本では、1927年ごろ、広島の「日本開閉機会社」がファスナーの製造を始め、巾着をもじった「チャック印」という商標をとりました。
そのため日本ではファスナーを「チャック」という名称で定着したのですが、これは「巾着(きんちゃく)」の造語であって、固定するという意味の英語「chuck」とは関係ありません。
「チャック」は日本語だったのです。
したっけ。
ワイシャツなどのカフスをとめる「カフスボタン」、正しくは「カフリンクス」ですが、スーツの上着にもカフスボタンの一種と言えるボタンが3~4個ほど付いています。
ただ、このボタンはワイシャツの袖口を留めるのは実用とオシャレの意味がありそうですが、スーツでは実用的な意味合いはないように思えます。単なる装飾にしては無駄な気がします。
実はスーツの袖口にボタンが付いているのは「ナポレオン」と関係があります。
ナポレオンがロシア遠征をした際に極寒のため兵士達が鼻水を軍服の袖で拭っていたので袖がカピカピになっていました。
これを見たナポレオンがとった対策が鼻水を拭けないように軍服の袖にボタンを付けることだったのです。
オシャレにこだわるフランス人らしい名案です。
これが現在のスーツや学生服の袖にボタンが付いている由来なのです。
今どき、学生服の袖で鼻水を拭う学生もいないでしょうが・・・。
寒くなってきました。風邪など引かぬようご自愛ください。
したっけ。
私たち日本人は、初対面のもの同士を紹介するとき、目下のほうから紹介する習慣があります。ところが、外国では目上のほうから紹介するそうです。
日本人の、この紹介の仕方には理由があります。
昔は格式のある家を訪問するときは、まず取り次ぎという者がいました。ツギは門番、さらに玄関番、そして緒太夫という使用人、その上にまた側近の奉仕者がいて、最後にやっと主人が現れるわけです。
この、だんだん下から上に名前と来意を告げて、上がっていく順序が、日常生活にも取り入れられたといいう訳です。
私は、この順番に閉口した経験があります。
仕事で、ある特殊社会の事務所兼住宅に集金に行っていたのですが、これがまったく昔と同じ取り次ぎ方でなかなか社長(親分とも言うらしい)まで話が行きません。返事が帰ってくるのも順番で、まるで「伝言ゲーム」のようでした。
そのほかにも、紹介する順序は、「立てたい人を後に」というルールもあります。
これは、ちょっと、難しいのでおぼえておいてください。
「立てたい人を後にする」というのは、その時に尊重しなければならない人のほうを、後に紹介すると言うことです。
 例えば、取引先のA商事の課長である佐藤課長が来社したとします。
例えば、取引先のA商事の課長である佐藤課長が来社したとします。
取引先ということは大切な相手なので、そちらを尊重しなければいけません。
では、この佐藤課長を自分の直属の上司、鈴木部長に紹介したい場合、さてどうしますか?
部長と課長ですから間違えてしまいそうですが、まず佐藤課長に対し、『私どもの営業部長の、鈴木でございます。』と自社の部長を紹介します。
次に、鈴木部長に対し『A商事営業課長の佐藤課長でいらっしゃいます。』と紹介します。このように、まずは、尊重したいほうに呼びかけて、身内を紹介し、そして、身内の鈴木部長に佐藤課長を紹介します。
このとき、敬語の使い方も注意しましょう。
したっけ。

最近は、キッチンのアイディア商品がたくさん発売されている他、いろいろな機能を備えたレンジや、ホームベーカリーなどの家電も登場し、簡単で楽しく料理ができるようになってきました。
さて、あなたは料理を作るのがすきですか?それとも作ってもらうのがすきですか?
おすすめのレシピ、作ってもらえるとうれしい料理なども、ぜひお聞かせください。
料理家電で簡単に楽しく料理?それじゃあ家電が料理を作るみたいではありませんか。
料理は人が「旬の食材」「素材の持ち味を活かす」「親切心や心配りをもった調理」といった心配りをして作るものです。
作るのが好きかと聞かれれば、「好き 」と答えます。そのとき自分が一番食べたいものを食べるのには、自分で作るのが一番ですからね
」と答えます。そのとき自分が一番食べたいものを食べるのには、自分で作るのが一番ですからね 。
。
作ってもらうのが好きかときかれれば、これも「好き 」と答えます。しかし、これは美味しい料理に限りますよ
」と答えます。しかし、これは美味しい料理に限りますよ 。
。
不味いものは困ります。せっかく作っていただいたものを、不味いとも言えませんし、食べるのも辛い 。
。
そういう意味では、自分で作ったほうが気楽と言えます。
一番いいのは、大好きな人に美味しい料理を作ってあげること 。大好きな人に美味しい料理を作ってもらうこと
。大好きな人に美味しい料理を作ってもらうこと 。
。
大好きな人に不味い料理を作ってもらうこと。これは一番困ります 。
。
つまり、作るのも、作ってもらうのも、その状況によって変わってしまうということです。
これは、質問を変えたほうがいいのかもしれませんね。
「あなたは料理が作れますか?それとも作れませんか?」これだと、答えがはっきりします。
「作れます! 」
」
したっけ。
11月23日は「勤労を尊び、生産を祝い、国民がたがいに感謝しあう日」と1948年(昭和23年)に法律で定められました。
戦前11月23日は「新嘗祭(にいなめさい/しんじょうさい)」で農作物の恵みを感じる日でした。
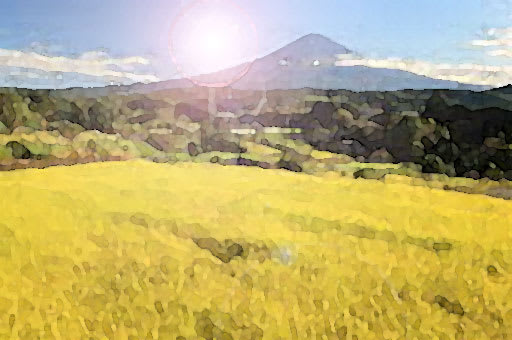 日々の労働に対して「農作物」という形のあるものが目に見えて返ってくることが少ない現代で、勤労の目的を再認識する日という意味がこめられているようです。
日々の労働に対して「農作物」という形のあるものが目に見えて返ってくることが少ない現代で、勤労の目的を再認識する日という意味がこめられているようです。
一方、勤労の意味について、戦後発行された衆議院文化委員受田新吉著の『日本の新しい祝日』には「肉体的な労働によって物品等を生産するということにのみ終始するものではなくて、精神的な方面においても一日一日を真剣に考え、物事の本質へと深めてゆく研究態度にも勤労の大きい意味は存在し、創造し、生産していくことの貴重な意義ある生活が営まれていくことが出来る。物質的にも、精神的にも広い意味での文化財を建設してゆくことは、生産ということの正しい理解の仕方である」と記載されているそうです。
勤労感謝の日が制定される以前は、「新嘗祭」が行われていました。新嘗祭は古くから国家の重要な行事であり「瑞穂の国」の祭祀を司る最高責任者である「大王(おおきみ)(天皇)」が国民を代表して、農作物の恵みに感謝する式典でした。
新嘗祭の起源は、『古事記』にも天照大御神が新嘗祭を行ったことが記されています。
しん‐じょう【新嘗】
《「しんしょう」とも》秋に新しくとれた穀物を神に供えて天皇みずからもそれを食べること。にいなめ。
大辞泉
「新嘗」とはその年収穫された新しい穀物のことをいいます。農業中心の時代、この行事はとても重要な儀式でした。
「勤労感謝の日」は1948年に定められましたが、この日を制定するにあたっては、元々の「新嘗祭」として祝いたいなど様々な意見があったようです。しかし「労働」とは本来「農業に従事して生産を行うもの」だけを言うのではなく、今日のサービス産業なども含めた幅広い意味を持つことから「新嘗祭の日」という考えは却下され、現在の「勤労感謝の日」が制定されたそうです。
私は天皇を神格化する思想の持ち主ではありませんが、「勤労感謝の日」が農耕民族として脈々と受け継がれてきた「新嘗祭」という「農作物に感謝をすること」が起源だったことは覚えておいて欲しいものです。
その農業が今「TPP」に参加することで失われつつあります。
したっけ。
「会席料理(かいせきりょうり)」は日本料理の形式の一つ。「俳席料理(はいせきりょうり)」が本来の名称で、そのおこりは江戸の初期俳諧(はいかい)の祖ともいえる「松永貞徳(ていとく)」の門人「山本西武(さいむ)」が、京都二条寺町の妙満寺で「百韻興行」を催したとき(1629)に始まるとされています。
ひゃく‐いん【百韻】
連歌・俳諧で、100句を連ねて一巻きとする形式。懐紙4枚を用い、初折(しょおり)は表8句・裏14句、二の折・三の折は表裏とも各14句、名残の折は表14句・裏8句を記す。
大辞泉
はい‐かい【俳諧/誹諧】
1 こっけい。おかしみ。たわむれ。2 俳句(発句(ほっく))・連句および俳文などの総称。3 「俳諧の連歌」の略。4 「俳諧歌(はいかいか)」の略。
大辞泉
 この席に酒食を出して、俳席に出席した人たちが会食し、それを「俳席料理」といったのです。
この席に酒食を出して、俳席に出席した人たちが会食し、それを「俳席料理」といったのです。
俳席で提供される料理ですから「簡素」であるが「礼儀正しく」、酒は「会の終わりに少量」出していました。それがしだいに崩れ、俳諧のほうも百韻から簡易化した歌仙(36句)になり、俳諧の行事が終わらないうちに、杯(さかずき)を交わし、歌をうたうといった酒食本位の俳席が「延宝(えんぽう)年間(1673~81)」に始まりました。
 俳席料理は「宴会本位の会食」になり、いつしか「会席料理」というようになりました。1771年(明和8)には料理屋が江戸・深川八幡(はちまん)近くにでき、各所に続出するに至って、料理屋料理として急速に進展し、内容も一段と複雑になり「高級化」した「宴会料理」となった。
俳席料理は「宴会本位の会食」になり、いつしか「会席料理」というようになりました。1771年(明和8)には料理屋が江戸・深川八幡(はちまん)近くにでき、各所に続出するに至って、料理屋料理として急速に進展し、内容も一段と複雑になり「高級化」した「宴会料理」となった。
会席料理は西洋料理のディナーと同じで、一つの型をもつ定食となったが、関東の会席料理では、口取りのグループに属する料理は折詰めにして持ち帰る方式をとっていました。
昭和の初めからは、関西式の、出た料理をその場で食べる「食切(くいきり)料理」の形態となってきたそうです。
「懐石料理」は「一時的に空腹を満たす軽い食事」のことです。
「会席料理」は「酒を楽しむための料理」のことです。和食料理屋で出て来る料理は普通「会席料理」です。この会席料理は酒席を前提に献立が組まれています。
したっけ。
昨日に引き続き「懐石料理の作法」について考えて見ましょう。
懐石料理には亭主(おもてなしをする人)と客人(おもてなしを受ける人)どちらにも作法が決められています。
亭主の作法(提供の作法)
・ 材料はすべて使いきり、切れ端まで決して粗末に扱ってはいけません。
・ 温かい料理は温かく、冷たい料理は盛る器まで冷たくして客人に提供するといった心配りを重んじ、料理を運ぶ「間」を大切にします。
・ 献立の中で「海」、「山」、「里」の幸を重複しないように組み合わせなければなりません。
・ 食べにくいものには「隠し包丁」を入れ、骨の多いものはしっかりと取り除いて料理を食べやすくして提供します。
・ 料理を盛り付ける食器に関してもその取り合わせや組み合わせまでしっかり心配りをします。
客人の作法(いただき方の作法)
・ 「焼魚」 まるごとの魚は、頭の後ろ背中の方からつまんで食べます。中骨に沿って箸を入れ、上半分、下半分の順で食べます。頭を左手で押さえながら、下の身と骨をは がし、頭と骨は身の向こう側に置きます。表側を食べ終わってもひっくり返してはいけません。残った身も、上半分、下半分の順 で食べます。そのまま骨を取って下の身を食べます。
がし、頭と骨は身の向こう側に置きます。表側を食べ終わってもひっくり返してはいけません。残った身も、上半分、下半分の順 で食べます。そのまま骨を取って下の身を食べます。
・ 「刺身」 わさびを醤油に溶いてはいけません。わさびは刺身の片側に付けて醤油は反対側につけて食します。醤油の小皿を手に持った方が醤油を垂らさず食べられます。
・ 「煮物」 里芋などの滑りやすいものは、片方の箸を刺してもかまいません。もう一方の箸で挟んで食べます。
・ 「串物」 串に刺さった料理は、串を持って食べてはいけません。まず串は抜き、箸で適当な大きさに切って食べます。
この、いただき方の作法は懐石料理でなくても、共通ですので心がけてください。
明日は「会席料理の起源」について書くつもりです。
したっけ。































