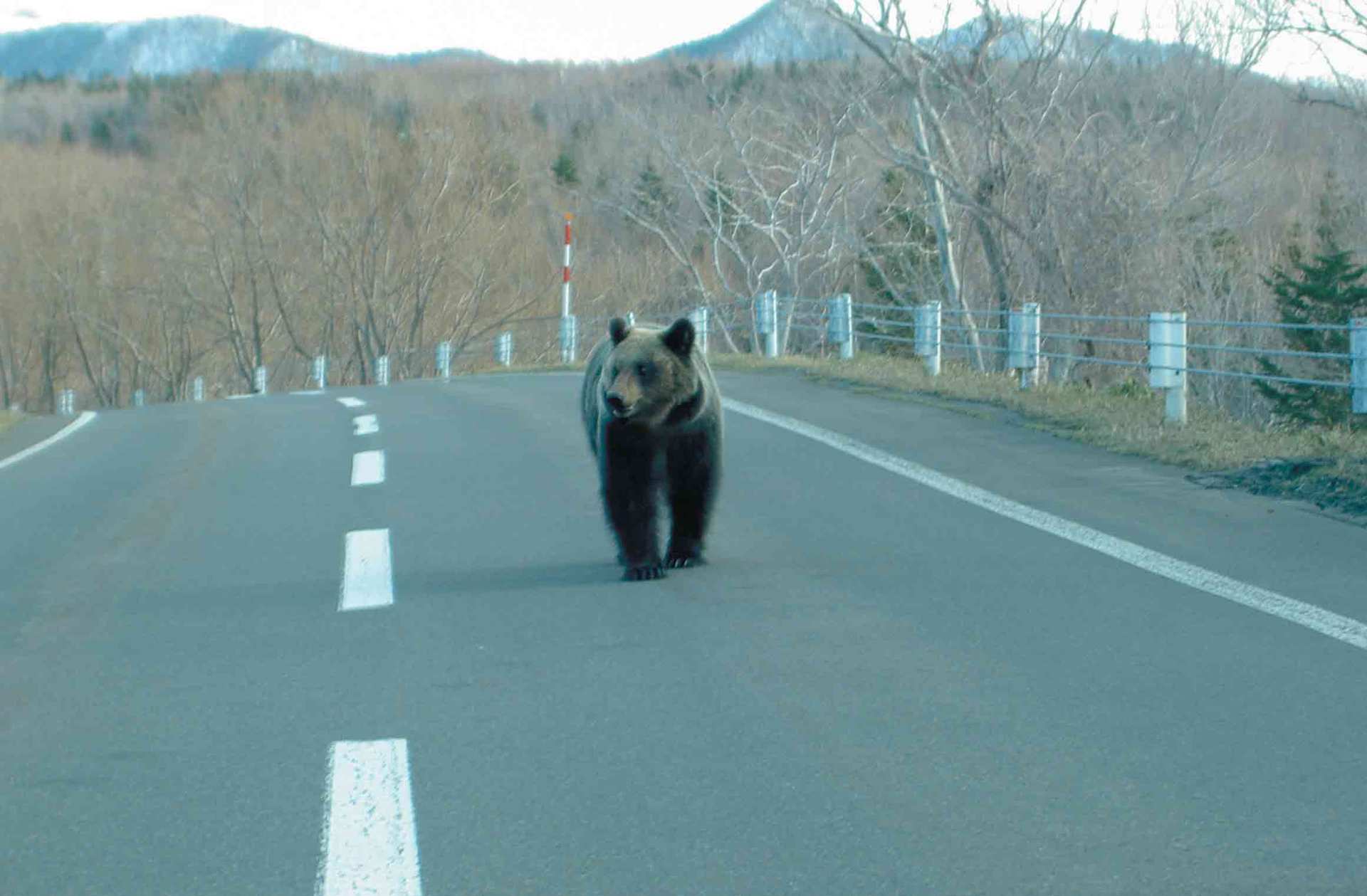20XX-8-23 (土) 晴れ 午後気温低下
朝9時、北見を出発。この時期、婚姻色で美しく変身しつつあるオショロコマを撮影に出かけた。1時間ほどで釣り場へ着いた。M川上流にいくつかある支流のひとつの源流域にオショロコマたちは産卵体制にはいるため集結しつつある。うっそうたる原生林、オショロコマの森は見ていてほれぼれする。森の中を流れる小さな支流に入って行く途中、川を渡る橋の上から渓流をのぞくと小型のオショロコマがあちこちに群れているのが見える。だらだら川なので、ちょっとしたよどみにはオショロコマがたまりやすい。条件の良いところをさがして釣りはじめ、撮影を開始した。 M川本流域に棲息するやや大型の個体群と比較すると。外見的にはかなり異なって♂は体色の色調が濃く、赤点紋理は鮮明な赤色、やや小型の個体が多い。

ミドリヒョウモン♂























婚姻色で腹部が鮮やかに黄色く染まったオショロコマ♂。
撮影させていただいたオショロコマたちはすべて丁寧にもとの場所にリリースしました。