都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「巴里憧憬 - エコール・ド・パリと日本の画家たち - 」 埼玉県立近代美術館
埼玉県立近代美術館(さいたま市浦和区常盤9-30-1)
「巴里憧憬 - エコール・ド・パリと日本の画家たち - 」
1/6-2/12
数ある「エコール・ド・パリ」と銘打たれた展覧会の中でも、これほど多くの日本人画家にスポットを当てた企画はそうありません。パリを目指した画家たちの足取りを作品で概観します。有名どころの藤田嗣治や佐伯祐三を初めとして、里美勝蔵や結城素明、それに埼玉にも所縁のあった斎藤豊作らの作品が揃っていました。(全展示数161点のうち、125点が日本人画家の作品です。)
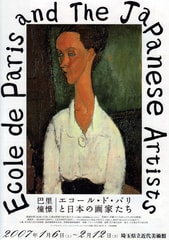
この展覧会では、いわゆるエコール・ド・パリの時代にパリと関わった日本人の画家を5つに分類しています。(カッコ内は各章のタイトルです。)
1 「目指せ!エコール・ド・パリの頂点 - 藤田嗣治とその追従者たち - 」
エコール・ド・パリの画家として最も知名度の高い藤田嗣治と、彼を追う形でパリへと繰り出した、海老原喜之助、高野三三男、板東敏雄、高崎剛、小柳正など。
2 「テクニク・オリアンタル! - エコール・ド・パリの日本画家 - 」
パリにて日本画を描いて生活していた画家。出島春光、古城江観、蕗谷虹児、金子光晴など。
3 「芸術の都パリ - 画家たちの聖地巡礼 - 」
既に日本で地位のあった大家らのパリ遊学。田中保、清水登之、黒田重太郎、土田麦僊、結城素明など。
4 「美術思潮の伝道者 - 留学生が見たエコール・ド・パリ - 」
一時、数百人にも及んだパリ美術留学生から、里美勝蔵、前田寛治、佐伯祐三、荻須高徳、坂田一男など。
5 「ヴェヌヴェルの静寂のなかで - 斎藤豊作の交友 - 」
渡仏しながらもパリに背を向けて制作を続けた斎藤豊作と、彼と交遊のあった長谷川潔や岡鹿之助。
藤田に憧れてパリを目指した者から、逆に彼に反発しながら制作を続けていた画家、或はアメリカよりパリに移住して拠点を構えたり、またあえてパリから離れて絵に没頭した画家など、その生き様は実に多種多様です。またもちろん彼らの作風もそれぞれに異なっています。複雑に絡み合っていたエコール・ド・パリの日本人画家を辿るのは、一筋縄ではいかないようです。
まずは、19歳にて渡仏し、藤田に師事した経歴もある海老原喜之助の二点に見応えがありました。澄み切った青空の下に広がる真っ白なゲレンデを描いたその名も「ゲレンデ」(1930)と、厚みのあるタッチがヴラマンク風の雪景色を生み出した「冬」(1928)は対照的な作品です。前者が晴天の眩しい雪原を、まさに颯爽と冷風を切るかのような心地良い雰囲気でまとめ上げているのに対し、後者は油彩をキャンバスに厚く塗り付け、雪の重みがズッシリとも伝わるような、半ば寂寥感も思わせる冬の光景を描いています。私の趣向はその「冬」にありますが、ともに表現力に優れていました。甲乙付け難い作品です。

有りがちな主題の並ぶ日本画の中では、技巧にも冴えた蕗谷紅児の「柘榴を持つ女」(1927)が印象に残りました。チューリップ柄の衣服を纏った女性が、胸に柘榴を持ちながら構えて座っています。テーブルクロスなどに描かれた洒落た装飾と、控えめでありながらもやはり艶やかなその振る舞いには惹かれました。ネックレスやイヤリングなどもなかなか魅惑的です。
佐伯祐三や里美勝蔵らの重厚な作品が並んだ、「美術思潮の伝道者」(4)のコーナーが展示のハイライトかもしれません。ここでは力強いグレーの支配する中で果実や花の佇む、里美勝蔵の「静物」(1924頃)が一番心に残りました。ペンキを塗るかのような大胆なタッチで塗られた灰色を背景に、紅白のバラ(?)や葡萄、それにグラスが端正に置かれています。佐伯祐三に見るようなダイナミックな情感こそありませんが、静謐でありながらもその存在感がしっかりと感じられる作品でした。

埼玉県越谷市出身で、パリ南西部のヴェヌヴェルの古城(何と購入したものだそうです…。)にて悠々自適な画業生活を送っていたという斎藤豊作も忘れてはなりません。決して器用な画家ではありませんが、パステルの淡い質感と時に点描の技法を巧みに利用しながら、長閑な田園風景を伸びやかに描いています。ちなみに斎藤の作品は、常設展示にも数点展示されていました。(私はあまり彼の作品に惹かれる部分が少ないのですが、どちらかと言えばそちらに魅力的な作品が多いようです。)これは地元作家ならではの充実したコレクションと言えそうです。(また斎藤と交友関係にあった長谷川潔や岡鹿之助の作品は優れています。特に版画家で知られる長谷川の大きな油彩画が展示されていたのには驚きました。これはおすすめしたい作品です。)
パンフレットにも挙げられているモディリアーニなど、まさにエコール・ド・パリを代表する画家の作品も約40点弱ほど展示されています。その中では二点の彫刻、モディリアーニの「頭部」(1911-12頃)とブランクーシの「うぶごえ」(1917)に惹かれました。その他ではユトリロ、ローランサン、シャガールらのお馴染みの名が連なっています。
一点豪華主義でも、また決して名品揃いの展覧会でもありませんが、地味ながらも目立たない画家をじっくりと見せた良い企画だったと思います。(出来ればパンフレットの表紙にも、日本人画家の作品を載せて欲しかったところです。)来月12日までの開催です。(1/22鑑賞)
「巴里憧憬 - エコール・ド・パリと日本の画家たち - 」
1/6-2/12
数ある「エコール・ド・パリ」と銘打たれた展覧会の中でも、これほど多くの日本人画家にスポットを当てた企画はそうありません。パリを目指した画家たちの足取りを作品で概観します。有名どころの藤田嗣治や佐伯祐三を初めとして、里美勝蔵や結城素明、それに埼玉にも所縁のあった斎藤豊作らの作品が揃っていました。(全展示数161点のうち、125点が日本人画家の作品です。)
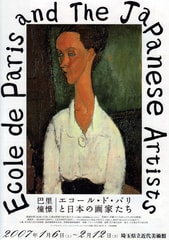
この展覧会では、いわゆるエコール・ド・パリの時代にパリと関わった日本人の画家を5つに分類しています。(カッコ内は各章のタイトルです。)
1 「目指せ!エコール・ド・パリの頂点 - 藤田嗣治とその追従者たち - 」
エコール・ド・パリの画家として最も知名度の高い藤田嗣治と、彼を追う形でパリへと繰り出した、海老原喜之助、高野三三男、板東敏雄、高崎剛、小柳正など。
2 「テクニク・オリアンタル! - エコール・ド・パリの日本画家 - 」
パリにて日本画を描いて生活していた画家。出島春光、古城江観、蕗谷虹児、金子光晴など。
3 「芸術の都パリ - 画家たちの聖地巡礼 - 」
既に日本で地位のあった大家らのパリ遊学。田中保、清水登之、黒田重太郎、土田麦僊、結城素明など。
4 「美術思潮の伝道者 - 留学生が見たエコール・ド・パリ - 」
一時、数百人にも及んだパリ美術留学生から、里美勝蔵、前田寛治、佐伯祐三、荻須高徳、坂田一男など。
5 「ヴェヌヴェルの静寂のなかで - 斎藤豊作の交友 - 」
渡仏しながらもパリに背を向けて制作を続けた斎藤豊作と、彼と交遊のあった長谷川潔や岡鹿之助。
藤田に憧れてパリを目指した者から、逆に彼に反発しながら制作を続けていた画家、或はアメリカよりパリに移住して拠点を構えたり、またあえてパリから離れて絵に没頭した画家など、その生き様は実に多種多様です。またもちろん彼らの作風もそれぞれに異なっています。複雑に絡み合っていたエコール・ド・パリの日本人画家を辿るのは、一筋縄ではいかないようです。
まずは、19歳にて渡仏し、藤田に師事した経歴もある海老原喜之助の二点に見応えがありました。澄み切った青空の下に広がる真っ白なゲレンデを描いたその名も「ゲレンデ」(1930)と、厚みのあるタッチがヴラマンク風の雪景色を生み出した「冬」(1928)は対照的な作品です。前者が晴天の眩しい雪原を、まさに颯爽と冷風を切るかのような心地良い雰囲気でまとめ上げているのに対し、後者は油彩をキャンバスに厚く塗り付け、雪の重みがズッシリとも伝わるような、半ば寂寥感も思わせる冬の光景を描いています。私の趣向はその「冬」にありますが、ともに表現力に優れていました。甲乙付け難い作品です。

有りがちな主題の並ぶ日本画の中では、技巧にも冴えた蕗谷紅児の「柘榴を持つ女」(1927)が印象に残りました。チューリップ柄の衣服を纏った女性が、胸に柘榴を持ちながら構えて座っています。テーブルクロスなどに描かれた洒落た装飾と、控えめでありながらもやはり艶やかなその振る舞いには惹かれました。ネックレスやイヤリングなどもなかなか魅惑的です。
佐伯祐三や里美勝蔵らの重厚な作品が並んだ、「美術思潮の伝道者」(4)のコーナーが展示のハイライトかもしれません。ここでは力強いグレーの支配する中で果実や花の佇む、里美勝蔵の「静物」(1924頃)が一番心に残りました。ペンキを塗るかのような大胆なタッチで塗られた灰色を背景に、紅白のバラ(?)や葡萄、それにグラスが端正に置かれています。佐伯祐三に見るようなダイナミックな情感こそありませんが、静謐でありながらもその存在感がしっかりと感じられる作品でした。

埼玉県越谷市出身で、パリ南西部のヴェヌヴェルの古城(何と購入したものだそうです…。)にて悠々自適な画業生活を送っていたという斎藤豊作も忘れてはなりません。決して器用な画家ではありませんが、パステルの淡い質感と時に点描の技法を巧みに利用しながら、長閑な田園風景を伸びやかに描いています。ちなみに斎藤の作品は、常設展示にも数点展示されていました。(私はあまり彼の作品に惹かれる部分が少ないのですが、どちらかと言えばそちらに魅力的な作品が多いようです。)これは地元作家ならではの充実したコレクションと言えそうです。(また斎藤と交友関係にあった長谷川潔や岡鹿之助の作品は優れています。特に版画家で知られる長谷川の大きな油彩画が展示されていたのには驚きました。これはおすすめしたい作品です。)
パンフレットにも挙げられているモディリアーニなど、まさにエコール・ド・パリを代表する画家の作品も約40点弱ほど展示されています。その中では二点の彫刻、モディリアーニの「頭部」(1911-12頃)とブランクーシの「うぶごえ」(1917)に惹かれました。その他ではユトリロ、ローランサン、シャガールらのお馴染みの名が連なっています。
一点豪華主義でも、また決して名品揃いの展覧会でもありませんが、地味ながらも目立たない画家をじっくりと見せた良い企画だったと思います。(出来ればパンフレットの表紙にも、日本人画家の作品を載せて欲しかったところです。)来月12日までの開催です。(1/22鑑賞)
コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )









