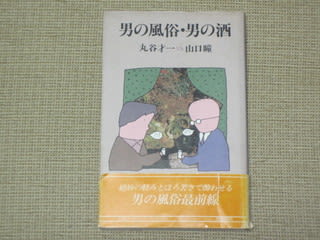丸谷才一VS.山口瞳 一九八三年 TBSブリタニカ・ペーパーバックス
ことし5月の古本まつりで見つけた対談録。
なんか色あせてる感じだし、帯なんか切れちゃってるし、状態はよくないんだけど、私はこれまで見かけたことなかったものだから、そういうの見つけたときに買わないと後悔するので、とりあえず買った。
なんだか知らないけど『サントリークォータリー』というのに連載された対談だということで、だから酒が看板に掲げられてんだろうと思う、そんなに酒の話ばかりしているわけではない。
風俗ってのも、もちろん狭義のいわゆるフーゾクではなくて、「その時代や地域を特徴づける生活上のしきたり」(角川書店・類語国語辞典)なんかのことである。
丸谷才一は小説は風俗を重視すべしみたいな意見の持ち主なんだけど、
>生き生きとした態度で生きていくためには、どんなつまらないことであろうと、現世の風俗というものに関心を持つべきですね。僕はそれは、非常に大事なことだと思いますよ。それをやらないと老けちゃうんですね。小説家が、わりに老けないのは、それなんじゃないかな。くだらないことに関心を持つから気が若い。(p.57「文壇は“オール・カマーズ!!”」)
なんて本書でも言ってたりする。
んで、対談相手の山口瞳に向かって、あなたの書いたものの愛読者だと告げたうえで、
>山口さんは、風俗を観察する人間として非常に向いているんだな。僕はそれを手がかりにして、いろいろ考える。(p.46「山口瞳の会社員論――その読み方」)
だなんて言ってみたりする。
そういうふうに、どっちかっていうと丸谷氏が山口氏をもちあげるような展開が多いんだけど、それに対して、山口氏は最初はよくわからん的な態度にみえてたんだが、
>丸谷さんと話をしていると自分のだめなところが見えてくる。とてもタメになる。(p.112「早く故郷を忘れたい」)
とかって、だんだん理解が深まってくる感じになる。終盤のほうになると、
>あなたもだんだん僕と似てきたな、そういうふうに断言するところが(笑)。やっぱりこれは、うつるんだね。(p.172「本棚のあるホテルの話」)
って具合に山口氏の側からも波長が合ってきたことを認めるんだが、この言葉に対する丸谷氏の返しが、
>江戸後期の俳句に「うら枯れの人に欠伸をうつしけり」というのがありますけど、さしずめ僕が、うら枯れの人だな(笑)。
っていうのが、しゃれているったらありゃしない。
ほかにも、例によってところどころに丸谷才一のいろんなこと知ってる一面がでてきて、それがおもしろかったりする。
山口瞳が「イギリスなんか、小学校くらいまで歯列矯正がタダなんですってね」と言うと、
>歯が悪いと、西洋では社交界にぜったい出入りできないらしいですね。つまり全くの下層階級ということになってしまい、仕事にも差しつかえる。日本人は、西洋に行ったときそれでかなり失敗するという話を聞いたことがあります。(p.34「歯並びも男の風俗だね」)
とか。
イギリスを旅行したら、鉄道の案内が非常に不親切で、車掌も来ないから他の乗客に聞くしかないんだけど、
>そのうち、クロスワード・パズルをやっている客に聞けば、ちゃんと安心できる返事が返ってくるということがわかってきた。つまり安心しているからクロスワード・パズルができるわけで、これは、いつも乗っているイギリス人なんですね(笑)。(p.154「お節介な日本人」)
とか。
ホテルや旅館のよしあしの話では、
>なるほどな。僕には悪い日本旅館の見分け方というのがあって(笑)、玄関入ってすぐに階段があるというやつ、これはダメ。(p.169「いい日本旅館、悪い日本旅館」)
とか。
本書の大きな章立ては、以下の三つだけ、そのなかで短く細かくけっこう分かれてはいる。まえがきが山口瞳、あとがきが丸谷才一。
「男の酒」
「東京を語る」
「旅の楽しみ」
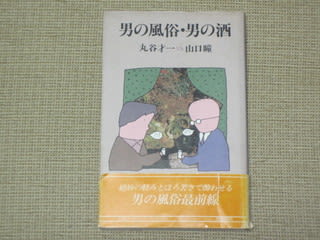
ことし5月の古本まつりで見つけた対談録。
なんか色あせてる感じだし、帯なんか切れちゃってるし、状態はよくないんだけど、私はこれまで見かけたことなかったものだから、そういうの見つけたときに買わないと後悔するので、とりあえず買った。
なんだか知らないけど『サントリークォータリー』というのに連載された対談だということで、だから酒が看板に掲げられてんだろうと思う、そんなに酒の話ばかりしているわけではない。
風俗ってのも、もちろん狭義のいわゆるフーゾクではなくて、「その時代や地域を特徴づける生活上のしきたり」(角川書店・類語国語辞典)なんかのことである。
丸谷才一は小説は風俗を重視すべしみたいな意見の持ち主なんだけど、
>生き生きとした態度で生きていくためには、どんなつまらないことであろうと、現世の風俗というものに関心を持つべきですね。僕はそれは、非常に大事なことだと思いますよ。それをやらないと老けちゃうんですね。小説家が、わりに老けないのは、それなんじゃないかな。くだらないことに関心を持つから気が若い。(p.57「文壇は“オール・カマーズ!!”」)
なんて本書でも言ってたりする。
んで、対談相手の山口瞳に向かって、あなたの書いたものの愛読者だと告げたうえで、
>山口さんは、風俗を観察する人間として非常に向いているんだな。僕はそれを手がかりにして、いろいろ考える。(p.46「山口瞳の会社員論――その読み方」)
だなんて言ってみたりする。
そういうふうに、どっちかっていうと丸谷氏が山口氏をもちあげるような展開が多いんだけど、それに対して、山口氏は最初はよくわからん的な態度にみえてたんだが、
>丸谷さんと話をしていると自分のだめなところが見えてくる。とてもタメになる。(p.112「早く故郷を忘れたい」)
とかって、だんだん理解が深まってくる感じになる。終盤のほうになると、
>あなたもだんだん僕と似てきたな、そういうふうに断言するところが(笑)。やっぱりこれは、うつるんだね。(p.172「本棚のあるホテルの話」)
って具合に山口氏の側からも波長が合ってきたことを認めるんだが、この言葉に対する丸谷氏の返しが、
>江戸後期の俳句に「うら枯れの人に欠伸をうつしけり」というのがありますけど、さしずめ僕が、うら枯れの人だな(笑)。
っていうのが、しゃれているったらありゃしない。
ほかにも、例によってところどころに丸谷才一のいろんなこと知ってる一面がでてきて、それがおもしろかったりする。
山口瞳が「イギリスなんか、小学校くらいまで歯列矯正がタダなんですってね」と言うと、
>歯が悪いと、西洋では社交界にぜったい出入りできないらしいですね。つまり全くの下層階級ということになってしまい、仕事にも差しつかえる。日本人は、西洋に行ったときそれでかなり失敗するという話を聞いたことがあります。(p.34「歯並びも男の風俗だね」)
とか。
イギリスを旅行したら、鉄道の案内が非常に不親切で、車掌も来ないから他の乗客に聞くしかないんだけど、
>そのうち、クロスワード・パズルをやっている客に聞けば、ちゃんと安心できる返事が返ってくるということがわかってきた。つまり安心しているからクロスワード・パズルができるわけで、これは、いつも乗っているイギリス人なんですね(笑)。(p.154「お節介な日本人」)
とか。
ホテルや旅館のよしあしの話では、
>なるほどな。僕には悪い日本旅館の見分け方というのがあって(笑)、玄関入ってすぐに階段があるというやつ、これはダメ。(p.169「いい日本旅館、悪い日本旅館」)
とか。
本書の大きな章立ては、以下の三つだけ、そのなかで短く細かくけっこう分かれてはいる。まえがきが山口瞳、あとがきが丸谷才一。
「男の酒」
「東京を語る」
「旅の楽しみ」