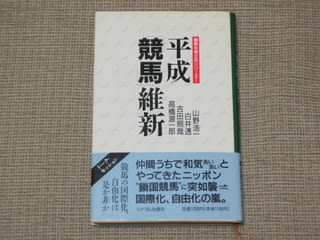乗馬に行く。
寒いと言えば寒いけど、キリキリするような冷たさはない。春はもうすぐそこだ。

さてさて、きょうの馬は誰かな? サンダルフォン? 初めて(喜)
もう乗馬もうまくならないし、毎回毎回進歩もないから、潮時かなあ、なんて思ってると、初めての馬がまわってきたりするから、ヤメられない。
ほんと2,3か月にいっぺん新しい馬でも当たれば、楽しくてまたゼンマイが巻き直されちゃうんだよな、私の場合。
私のやる気はともかく、とりあえず馬房から出して、ブラシかけたり、汚れついてるとこ拭いたりしてから、馬装するんだけど。初めての馬のときは、警戒しながらやることになる。(そのことは、なるべく馬には悟られないように。)
でも、身体でっかくて、見た目ちょっと怖そうなわりには、なんかおとなしい。ブラシでおなかさわったりすると嫌がるくらいで、あとは別になにもしない。

さあ、ちょっと遅れをとったけど、馬場へ。ずんずん歩いてく、特に挙動不審とかそういうことはない、いいぞいいぞ。
常歩でウォーミングアップ。前に出るぶんには申し分ないので、しばらく元気よく歩かせたら、ちょっとだけ拳を使う。わりとすぐこっちにくるようなとこあるんで、すぐかえしてやって、しばらく力を入れずに歩けたのを確かめて、ホメる。
拳そーっと使う、ゆずる、かえす、手綱伸ばしてやってクビが下がるようにしてやる。繰り返し。乗りやすそうな馬だけど、まだ油断は禁物かなと思う。(サラブレッドを信用していない私。)
んなことやってると、「部班入るんですか?広いほうで乗ってていいですよ」と言われるんだが、いやあ柵のなかで隊列に入りますよ。
(それとも、この馬乗ったら、広いとこで難しいことしなきゃいけないのかな。難しいことやる気はさらさらないんだけど。)

そんなこんなで先頭に立たされるんだが、とりあえず部班に入れてもらえる。
「部班をしばらくやったら、そのあとで障害やりたいひとは飛びましょうか」と言われる。
私は飛んでも飛ばなくてもいいんだけど、初めての馬だから、そこはフラットワーク次第かなあと思う。
速歩スタート。とてもよく動く。すこし速いと言われて、やや抑える。
脚には敏感に反応する、あまり派手に蹴飛ばさないように気をつけなきゃいけないくらい。
ときどきハミうけを求めて拳をじわっと使ってみる。一瞬イーッと抵抗感じるけど、やがてフワンとなるので、明確にかえすようにして、落ち着いたペースを保てて進め続けたら、ホメる。
先頭だけ巻乗り、最後尾にまわって、ということで隊列のうしろに。あー後方のほうが正直ラクだ。あんまり脚を急に使ったり、がちゃがちゃと無遠慮にハミをあてたりしないように気をつけながら、ついていく。
三湾曲の蛇乗りでは、途中まっすぐにしてから姿勢を入れ替えるように気をつけるんだけど、馬が外向いたまんま回っちゃったりして、うまくいかない。それにしても正反撞だと、いい速歩するなあ。

んぢゃ、しばらく各個で乗ってということになったんで、蹄跡の半分で輪乗りする。
最初軽速歩で詰めたり伸ばしたりする。詰めておとなしくペースを保てるのを確かめたら、伸ばしてみる。とても良い反応、勢いよく前に出る、そのあとは必ず詰める、詰められること確認してホメる。
大丈夫そうなんで、駈歩する。とても軽く発進、輪乗り。
いい駈歩だ、前へ伸びていく感じぢゃなくて、上へあがってくる感じがする、とてもサラブレッドぢゃないみたい。
たぶん踏込がいいんだと思うんだけど、座ってる真下から持ち上げられるような、こういう駈歩に出会うと楽しくなる。
駈歩でも詰め伸ばしする。伸ばした後に明確に詰めて、その状態をキープできるのを確かめて、ホメる。
ぢゃあ障害やりますよということで、結局みんなやる。

まずは長蹄跡に横木を5本置いて、駈歩で通過。部班の駈歩と何も変わらずに入ってきて通過するだけと言われる。
それでも最初元気よく入ってったら、「速過ぎ!もっとゆっくり」とダメ出し。ある程度前に出さないと歩幅が合わないかなと思っただけなんだけど。
二回目以降は、すこしおさえるくらいな感じ。横木に入って途中から速くなっちゃうとしたら、最初が遅いんだってことらしい。
サンダルフォンは、それほどエキサイトする感じでもないけど、やっぱ横木またいでくと勢いついてく感じはする。
横木を通り抜けた後も元気よく走るので、壁に向かって真っすぐ止める。次回からは速歩に落とすようにと言われる。
駈歩のリズムを保つ、隅角をちゃんとまわって、まっすぐ横木の真ん中に誘導する、横木を通り抜けた後に勝手に走られたり回転されたりしない、それが大事。
ぢゃあ高さをつけてくことになる。真ん中の横木はクロス障害に変わる。2本目の横木は取り除かれて、1本横木を通過して2歩でクロス、クロスの向こうに横木が2つあるという形。
クロスといっても超低空なので、横木のときと何も変えずに、駈歩のリズムを保って、通り抜けてくように。確かにふつうの駈歩のまま跨いでいくだけ。
こんどはクロスを一段上げると、入り口の横木跨いだらアブミに立つようにと。アブミに立って、軽い前傾を意識、クロスのあとの横木もそのまま、全部通過したらしっかり座る、拳を上げたりしないで、速歩におとすところまで丁寧に。
一回やるたんびに、止めたあと、よーくホメる。ほかの人馬がやってて待ってる間も、ラクにしてやってホメつづける。
それにしてもみんな静かだなあ。私は、障害入っていくときにも、「ゆっくりなー、そう、そんなペースで」とか声に出して馬に聞かせることが多いし、ホメるときも「じょうずだなー、今の良かったぞー」とか「おまえはいい馬だなー」とか大きな声で言うんで、周りが静かなここだと一人だけブツブツ言ってアブナイ人みたいである。

クロスの高さは一回ごとに上がっていき、とうとう垂直へ、40センチくらいかな。障害飛ばしに行ったりしないで、いままでと同じように駈歩のベースを守る。
最後にもう少しだけ高さを上げて、飛ぶ。サンダルフォンは落ち着いた感じで、飛越、飛んだあともエキサイトしないで、ブレーキかけるとおとなしく速歩になる。
「馬がよくなりました」とお褒めの言葉を賜る。うれしゅうございますねえ、いつも馬を混乱させて、できあがった教育を破壊するようなことばっかしてるんで、たまには少しでも馬のためになることができたとしたら。
比べると、たしかに初めのころは、横木を覗き込むような感じの動きがあって、そこんとこでちょっと速くなるような感じもしたんだけど、後半では上に向けた弾むようなステップのまま通り抜けることができた。
それはいいんだけど、駈歩の発進のときに、バタバタっとしちゃうときがあって、それは私の脚や拳が強く当たりすぎてたんだと思う。もうちょっとスラっと走り出したい、反省。
その馬むずかしくない、って言ってたひともいたけど、素直で一生懸命だと思いました、私は、サンダルフォン。
練習終了。クールダウンの常歩してから帰る。

手入れしてるあいだも、とてもおとなしい。いい馬だな、サンダルフォン。
リンゴの味は知ってるかなと思いながらやると、知ってます、もっとくださいとばかりの勢いで食べる、よしよし。

寒いと言えば寒いけど、キリキリするような冷たさはない。春はもうすぐそこだ。

さてさて、きょうの馬は誰かな? サンダルフォン? 初めて(喜)
もう乗馬もうまくならないし、毎回毎回進歩もないから、潮時かなあ、なんて思ってると、初めての馬がまわってきたりするから、ヤメられない。
ほんと2,3か月にいっぺん新しい馬でも当たれば、楽しくてまたゼンマイが巻き直されちゃうんだよな、私の場合。
私のやる気はともかく、とりあえず馬房から出して、ブラシかけたり、汚れついてるとこ拭いたりしてから、馬装するんだけど。初めての馬のときは、警戒しながらやることになる。(そのことは、なるべく馬には悟られないように。)
でも、身体でっかくて、見た目ちょっと怖そうなわりには、なんかおとなしい。ブラシでおなかさわったりすると嫌がるくらいで、あとは別になにもしない。

さあ、ちょっと遅れをとったけど、馬場へ。ずんずん歩いてく、特に挙動不審とかそういうことはない、いいぞいいぞ。
常歩でウォーミングアップ。前に出るぶんには申し分ないので、しばらく元気よく歩かせたら、ちょっとだけ拳を使う。わりとすぐこっちにくるようなとこあるんで、すぐかえしてやって、しばらく力を入れずに歩けたのを確かめて、ホメる。
拳そーっと使う、ゆずる、かえす、手綱伸ばしてやってクビが下がるようにしてやる。繰り返し。乗りやすそうな馬だけど、まだ油断は禁物かなと思う。(サラブレッドを信用していない私。)
んなことやってると、「部班入るんですか?広いほうで乗ってていいですよ」と言われるんだが、いやあ柵のなかで隊列に入りますよ。
(それとも、この馬乗ったら、広いとこで難しいことしなきゃいけないのかな。難しいことやる気はさらさらないんだけど。)

そんなこんなで先頭に立たされるんだが、とりあえず部班に入れてもらえる。
「部班をしばらくやったら、そのあとで障害やりたいひとは飛びましょうか」と言われる。
私は飛んでも飛ばなくてもいいんだけど、初めての馬だから、そこはフラットワーク次第かなあと思う。
速歩スタート。とてもよく動く。すこし速いと言われて、やや抑える。
脚には敏感に反応する、あまり派手に蹴飛ばさないように気をつけなきゃいけないくらい。
ときどきハミうけを求めて拳をじわっと使ってみる。一瞬イーッと抵抗感じるけど、やがてフワンとなるので、明確にかえすようにして、落ち着いたペースを保てて進め続けたら、ホメる。
先頭だけ巻乗り、最後尾にまわって、ということで隊列のうしろに。あー後方のほうが正直ラクだ。あんまり脚を急に使ったり、がちゃがちゃと無遠慮にハミをあてたりしないように気をつけながら、ついていく。
三湾曲の蛇乗りでは、途中まっすぐにしてから姿勢を入れ替えるように気をつけるんだけど、馬が外向いたまんま回っちゃったりして、うまくいかない。それにしても正反撞だと、いい速歩するなあ。

んぢゃ、しばらく各個で乗ってということになったんで、蹄跡の半分で輪乗りする。
最初軽速歩で詰めたり伸ばしたりする。詰めておとなしくペースを保てるのを確かめたら、伸ばしてみる。とても良い反応、勢いよく前に出る、そのあとは必ず詰める、詰められること確認してホメる。
大丈夫そうなんで、駈歩する。とても軽く発進、輪乗り。
いい駈歩だ、前へ伸びていく感じぢゃなくて、上へあがってくる感じがする、とてもサラブレッドぢゃないみたい。
たぶん踏込がいいんだと思うんだけど、座ってる真下から持ち上げられるような、こういう駈歩に出会うと楽しくなる。
駈歩でも詰め伸ばしする。伸ばした後に明確に詰めて、その状態をキープできるのを確かめて、ホメる。
ぢゃあ障害やりますよということで、結局みんなやる。

まずは長蹄跡に横木を5本置いて、駈歩で通過。部班の駈歩と何も変わらずに入ってきて通過するだけと言われる。
それでも最初元気よく入ってったら、「速過ぎ!もっとゆっくり」とダメ出し。ある程度前に出さないと歩幅が合わないかなと思っただけなんだけど。
二回目以降は、すこしおさえるくらいな感じ。横木に入って途中から速くなっちゃうとしたら、最初が遅いんだってことらしい。
サンダルフォンは、それほどエキサイトする感じでもないけど、やっぱ横木またいでくと勢いついてく感じはする。
横木を通り抜けた後も元気よく走るので、壁に向かって真っすぐ止める。次回からは速歩に落とすようにと言われる。
駈歩のリズムを保つ、隅角をちゃんとまわって、まっすぐ横木の真ん中に誘導する、横木を通り抜けた後に勝手に走られたり回転されたりしない、それが大事。
ぢゃあ高さをつけてくことになる。真ん中の横木はクロス障害に変わる。2本目の横木は取り除かれて、1本横木を通過して2歩でクロス、クロスの向こうに横木が2つあるという形。
クロスといっても超低空なので、横木のときと何も変えずに、駈歩のリズムを保って、通り抜けてくように。確かにふつうの駈歩のまま跨いでいくだけ。
こんどはクロスを一段上げると、入り口の横木跨いだらアブミに立つようにと。アブミに立って、軽い前傾を意識、クロスのあとの横木もそのまま、全部通過したらしっかり座る、拳を上げたりしないで、速歩におとすところまで丁寧に。
一回やるたんびに、止めたあと、よーくホメる。ほかの人馬がやってて待ってる間も、ラクにしてやってホメつづける。
それにしてもみんな静かだなあ。私は、障害入っていくときにも、「ゆっくりなー、そう、そんなペースで」とか声に出して馬に聞かせることが多いし、ホメるときも「じょうずだなー、今の良かったぞー」とか「おまえはいい馬だなー」とか大きな声で言うんで、周りが静かなここだと一人だけブツブツ言ってアブナイ人みたいである。

クロスの高さは一回ごとに上がっていき、とうとう垂直へ、40センチくらいかな。障害飛ばしに行ったりしないで、いままでと同じように駈歩のベースを守る。
最後にもう少しだけ高さを上げて、飛ぶ。サンダルフォンは落ち着いた感じで、飛越、飛んだあともエキサイトしないで、ブレーキかけるとおとなしく速歩になる。
「馬がよくなりました」とお褒めの言葉を賜る。うれしゅうございますねえ、いつも馬を混乱させて、できあがった教育を破壊するようなことばっかしてるんで、たまには少しでも馬のためになることができたとしたら。
比べると、たしかに初めのころは、横木を覗き込むような感じの動きがあって、そこんとこでちょっと速くなるような感じもしたんだけど、後半では上に向けた弾むようなステップのまま通り抜けることができた。
それはいいんだけど、駈歩の発進のときに、バタバタっとしちゃうときがあって、それは私の脚や拳が強く当たりすぎてたんだと思う。もうちょっとスラっと走り出したい、反省。
その馬むずかしくない、って言ってたひともいたけど、素直で一生懸命だと思いました、私は、サンダルフォン。
練習終了。クールダウンの常歩してから帰る。

手入れしてるあいだも、とてもおとなしい。いい馬だな、サンダルフォン。
リンゴの味は知ってるかなと思いながらやると、知ってます、もっとくださいとばかりの勢いで食べる、よしよし。