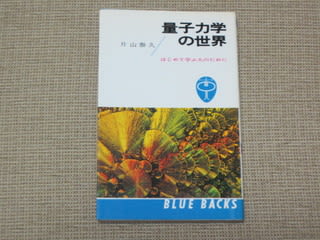都築卓司 1970年 講談社ブルーバックス
きのうのつづき、もうひとつ物理の本。
難しいこと軽くわかろうと、私のような無精者が目論んだとき手にとったもの。
副題の「運命への挑戦」ってのは、現在の状態を把握して、因果律となる物理法則を研究すれば、未来のことは全部ぴたりと予測できるっていう、ラプラスの悪魔的なものがホントに成り立つのか、現実はそうぢゃないのか=不確定なものがあるのかってことを指してる。
持ってるのは1989年の第38刷なんで、量子力学に関心もったのと同じころ読もうとしたんだろう。
こっちのほうが、数式はいくつか出てくるけど、書いてあることの書き方がおもしろい。
たとえば、1900年のプランクの輻射の公式(?)について、ウィーンの式を手直しして分母から1を引いたことを、
>なぜ1を引けば実験と合うのか、プランク自身にもよくわからない。しかし大学は夏期休暇の直前でもあり、何ヵ月かをのんびり過そうと思っていた……のかどうか、ともかくプランク教授は
>「1を引きさえすればいいというなら、今度の講演はそれでいこうじゃあないか」
>とあっさりきめてしまった。
ってホントかウソかわかんない調子で書いてるとこなんかは、今回読み直してて思わず笑った。
全編そういう“お話”調なとこがあって、読み物としては楽しい。
肝心な中身、物理の理屈は、やっぱり私にはまったく理解できないけど。
序章が「巨人の星」と題して、大リーグボール2号=消える魔球をとりあげているんだが、これが秀逸。
大リーグボール1号、バットに当てる魔球については、打者を観測すれば、その後のバットの動く位置はわかるっていう、いわば古典物理的なボール。
それに対して、大リーグボール2号は、ボールがストライクゾーンのどこを通るのか不確定、あらゆる場所を通り抜けてくる波のようなものという、いわば量子論的なボールだと言う。
それはいいんだけど、この本は巨人の星が連載中で、まだ大リーグボール2号の消える理屈がマンガのなかでも説明されていない時点で書かれたものらしいんだが、この序章の最後に、物理学的には、
>「(略)波長の長い波を打者に送れば、いくらバットをスイングしても、波はす通りしてしまいます」
として、超スローボールを投げればバットではねかえされない、という論を展開している。
これって、大リーグボール3号の予言である、すごい。

きのうのつづき、もうひとつ物理の本。
難しいこと軽くわかろうと、私のような無精者が目論んだとき手にとったもの。
副題の「運命への挑戦」ってのは、現在の状態を把握して、因果律となる物理法則を研究すれば、未来のことは全部ぴたりと予測できるっていう、ラプラスの悪魔的なものがホントに成り立つのか、現実はそうぢゃないのか=不確定なものがあるのかってことを指してる。
持ってるのは1989年の第38刷なんで、量子力学に関心もったのと同じころ読もうとしたんだろう。
こっちのほうが、数式はいくつか出てくるけど、書いてあることの書き方がおもしろい。
たとえば、1900年のプランクの輻射の公式(?)について、ウィーンの式を手直しして分母から1を引いたことを、
>なぜ1を引けば実験と合うのか、プランク自身にもよくわからない。しかし大学は夏期休暇の直前でもあり、何ヵ月かをのんびり過そうと思っていた……のかどうか、ともかくプランク教授は
>「1を引きさえすればいいというなら、今度の講演はそれでいこうじゃあないか」
>とあっさりきめてしまった。
ってホントかウソかわかんない調子で書いてるとこなんかは、今回読み直してて思わず笑った。
全編そういう“お話”調なとこがあって、読み物としては楽しい。
肝心な中身、物理の理屈は、やっぱり私にはまったく理解できないけど。
序章が「巨人の星」と題して、大リーグボール2号=消える魔球をとりあげているんだが、これが秀逸。
大リーグボール1号、バットに当てる魔球については、打者を観測すれば、その後のバットの動く位置はわかるっていう、いわば古典物理的なボール。
それに対して、大リーグボール2号は、ボールがストライクゾーンのどこを通るのか不確定、あらゆる場所を通り抜けてくる波のようなものという、いわば量子論的なボールだと言う。
それはいいんだけど、この本は巨人の星が連載中で、まだ大リーグボール2号の消える理屈がマンガのなかでも説明されていない時点で書かれたものらしいんだが、この序章の最後に、物理学的には、
>「(略)波長の長い波を打者に送れば、いくらバットをスイングしても、波はす通りしてしまいます」
として、超スローボールを投げればバットではねかえされない、という論を展開している。
これって、大リーグボール3号の予言である、すごい。