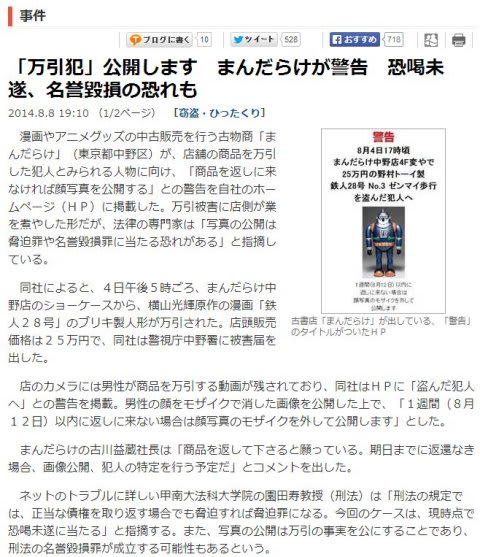転勤生活が多く、いくつもの地方都市に住んだことがありますが、それなりの役職になって、地域の人たちの支持と共感を得なくてはやっていけないな、と感じたのは、長野県松本市で、国営アルプスあづみの公園の事務所長になったときでした。
そもそも長野県というところは、県民性として「勤勉、頑な、本物でなくては信じない」というような傾向が強いところだと感じました。
そういう場所では、「国の公園の事務所長でござい」と言ったところで、役職ではなくその「人となり」をじっくりと見られます。おべっかは使ってこないし、こちらがおべっかを使ったところで何の役にも立ちません。その人が本物かどうかだけを冷徹に見抜かれてしまうのです。
そんな場所では会話の中で「信州は良いところですね」と言ったりすると、「ほう、どこが良いですか?」と質問が返ってきます。
そのときに言葉に詰まるようでは単におべっかをいったことにしかなりません。
「いや、蕎麦が美味しいでしょう」と言うと、「ほう、ではどこの蕎麦屋が美味しいとお思いですか」と来る。
それに確たる自信がなく、思いつくままに「○○屋なんていいですよね」などと適当に答えたりすると、「あの蕎麦屋を美味しいと思っておられるようではだめですね」と言われます。
褒める言葉ひとつ発するのにも、相当の覚悟と自信を持って言わなくては誠の心があるとは言えないのです。
◆
さてさて、こういう人たちの共感と信頼を真に得るためには、信州の良いところが自分の中でちゃんと"腹落ち"して、納得してなぜ良いかを説明できるくらいにならないといけないと思いました。
そのときのポイントは、地元の人たちが誇りに思い自慢に思っているものに対してそれを敬いそれにこちらが共感することです。
では松本市周辺の安曇野の人たちの誇りと自慢とはなにか、と観察を続けていると、どうやらそれが「蕎麦」と「北アルプス」であるということが分かってきました。
それが分かったのなら、こちらもそれに徹底してのめり込むことです。
そこで信州の中で「蕎麦屋さんを百軒巡る」という志を立てて、まあ蕎麦屋さんを訪ね歩いて食べ歩きました。結局2年間で百と五軒に達したのですが、さすがにその過程で四~五十軒くらい美味しいと言われる蕎麦屋さんを巡ってみると、蕎麦が美味しいとはどういうことなのかが感覚として分かってきます。
そして、「あそこは行きましたか?」と言われるような蕎麦屋にも大抵「はい、行きました。あそこは美味いし、これこれこういうところがいいですね」と確信を持った答えを出せるようになります。
蕎麦だけでもそれくらいになっているとこちらも自信を持って会話ができるようになり、周りからも「この人はどうやら本気だ」という目で見られるようになり、その後のやりとりがとてもスムースになりました。
もちろん北アルプスは登山もし、槍ヶ岳の山頂にも上ってきました。一度登っておきさえすれば、経験談として語れるので山の会話にもついて行くことができます。
つまり、そのような地域をリスペクトして、だからこそわが身を没入させるような時間を過ごさなくてはなりません。
そして自分の経験値を上げそれがまた楽しいとか、自分自身の喜びに繋がっている、という生き方をしなくては人は決して信頼してくれることはないのだ、ということを私は信州安曇野で学びました。
「Trust me.=どうぞ信頼してください」と口でいうことほど世の中をなめた言葉はありません。信頼に足る自分になれたなら、信頼は自動的に集まってくるものです。
もし信頼されないのならそれはまだ自分が未熟だからだと内省しなくてはいけない。
こういうことが「なるほど」と自分の中に"腹落ち"して実践できれば転勤生活が多くてもその人の人生は幸せに満ちることでしょう。
そしてそれが分からなかったり、分かったとしても実践できなくては移り変わる生活は苦労が多いものになるに違いありません。
転勤生活が多い方が人生を楽しむちょっとしたコツのご紹介でした。