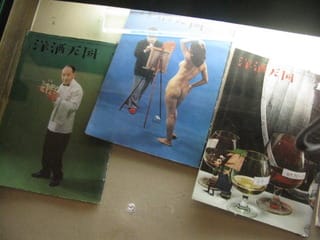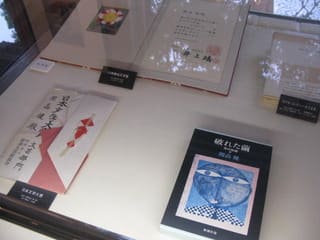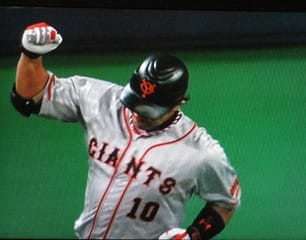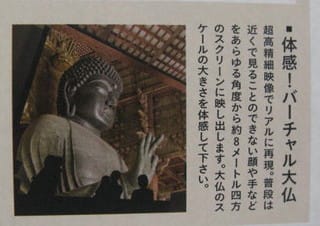横浜のそごう美術館で、手塚雄二画伯自身によるギャラーリートークが、まるで噺家のように面白かったことは、昨日述べた。そのときに、手塚さんが鎌倉市の二階堂で生まれたことを知った。それで、二階堂方面に散歩に出かけたというわけだ。二階堂といえば、手塚さんのお師匠さん、平山郁夫さんも、鎌倉宮から瑞泉寺に向かう通り沿いに住んでいた。
ここら辺りは、鎌倉時代に、奥州合戦で、亡くなった義経らの慰霊のために造られた、平泉の二階堂大長寺院を模した、永福寺という大寺院のあったところで、その後、焼失し、”二階堂”の地名だけが残っている。まだ空き地で、秋のすすきの見どころになっている。この近くに平山邸があり、シルクロードの文化遺跡の保存に力を尽くし、多くの絵画作品も残した根城である、”シルクロード研究所”の看板がかかっている。

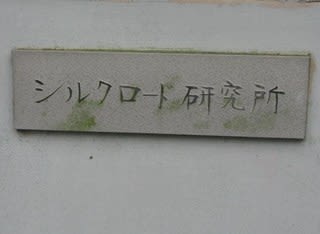
瑞泉寺は、早春の梅と水仙で有名だが、今頃の秋明菊のうつくしさはあまり知られていない。今が真っ盛りだが、観光客は数えるほどしかいない。白、赤、ピンクと三種類揃って、あちこちに咲いている。



梅は古木ばかりで、枝にウメノキゴケがはびこっている。梅の花の季節には、白っぽくなって、あまり目立たないというか、うつくしさを感じないが、今の季節は、青々として、わが世の春を楽しんでいるようにみえる。ウメノキゴケの見頃だ。


そして、冬桜が咲き始めていた。水戸の黄門さま、お手植えの由緒ある桜である。

なんと、ツワブキも咲き始めていた。

手塚雄二画伯好みの、何気ない景色もあった。蜘蛛の巣にひっかった枯葉。横浜で展示されていた、絵にもそんなのがあった(右図)。


よくみれば はきだめ菊咲く 古寺かな (汗)

秋の瑞泉寺は、静まりかえっていた。こんな贅沢な散歩はないなと、ぼくは、ひとり、ほくそ笑んだのだ。
ふと振り向くと、山門前でインナー丸出しの女性が写真を撮っていた。ぼくは、また、ほくそ笑んだのだった。

ここら辺りは、鎌倉時代に、奥州合戦で、亡くなった義経らの慰霊のために造られた、平泉の二階堂大長寺院を模した、永福寺という大寺院のあったところで、その後、焼失し、”二階堂”の地名だけが残っている。まだ空き地で、秋のすすきの見どころになっている。この近くに平山邸があり、シルクロードの文化遺跡の保存に力を尽くし、多くの絵画作品も残した根城である、”シルクロード研究所”の看板がかかっている。

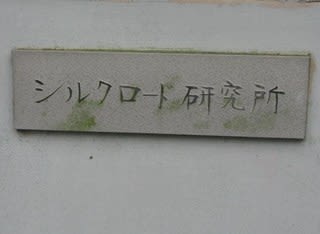
瑞泉寺は、早春の梅と水仙で有名だが、今頃の秋明菊のうつくしさはあまり知られていない。今が真っ盛りだが、観光客は数えるほどしかいない。白、赤、ピンクと三種類揃って、あちこちに咲いている。



梅は古木ばかりで、枝にウメノキゴケがはびこっている。梅の花の季節には、白っぽくなって、あまり目立たないというか、うつくしさを感じないが、今の季節は、青々として、わが世の春を楽しんでいるようにみえる。ウメノキゴケの見頃だ。


そして、冬桜が咲き始めていた。水戸の黄門さま、お手植えの由緒ある桜である。

なんと、ツワブキも咲き始めていた。

手塚雄二画伯好みの、何気ない景色もあった。蜘蛛の巣にひっかった枯葉。横浜で展示されていた、絵にもそんなのがあった(右図)。


よくみれば はきだめ菊咲く 古寺かな (汗)

秋の瑞泉寺は、静まりかえっていた。こんな贅沢な散歩はないなと、ぼくは、ひとり、ほくそ笑んだのだ。
ふと振り向くと、山門前でインナー丸出しの女性が写真を撮っていた。ぼくは、また、ほくそ笑んだのだった。