
横浜の歴史博物館で”天狗推参!”展をみて、みなとみらい方面に向かって、歩いていたら、日本丸の傍の横浜みなと博物館で、表記の展覧会をやっていた。歌も映画も小説も嫌いな方ではないので、ついふらふらと入ってしまった(汗)。
横浜の港を歌ったものとしては、ぼくでもすぐ思いつく、三つの歌の歌詞のパネルが入場してすぐの壁に掛けられていた。野口雨情の”赤い靴”と石田あゆみの”ブルーライトヨコハマ”そして美空ひばりの”港町十三番地”だ。
展示構成は、ほぼ年代順に6章に分けてある。第一章は”八十日間世界一周と霧笛/開港と外国人居留地”である。八十日間世界一周の船は、まず横浜港に寄港した。関連のものとして、川島忠之助訳の"新八十日間世界一周の上下二巻"、横浜居留地の商人と日本の若者の愛憎劇の小説、大仏次郎の”霧笛”、長谷川伸の本の他、当時の横浜地図や三代目広重の浮世絵があった。
第二章は”鴎外の桟橋と赤い靴/新港埠頭の建設”。鴎外の”桟橋”に、伯爵夫人がロンドンへ赴任する夫を見送るシーンがあるそうだ。本は、その他、獅子文六の”父の乳”、有島武郎の”或る女”、野口雨情の童話”青い目の人形”、”赤い靴”など展示されている。知らなかったが、大正9~12年に大正活映撮影所が山手にあったらしい。その写真もあった。
第三章”横浜行進曲と別れのブルース” やっと歌謡曲が出てきた。ブルースの女王、淡谷のり子の”別れのブルース”。♪窓をあければ 港が見える メリケン波止場の 灯が見える♪
ちあきなおみに歌わせると、絶品ですよ。映画ポスターも。勝新太郎の”かんかん虫は歌う”そして、日活ロマンポルノ”赤線本牧/チャブの女”。どちらもみたことはない。後者はとくにみたかった(汗)。
第四章”美空ひばりデビュー”。横浜出身の歌手といえば美空ひばり。横須賀出身の歌手といえば山口百恵(誰も聞いてないって?)。伊勢佐木町にひばりさんのブロンズ像があります。向かいの劇場が初舞台だった。最近、生誕地の磯子区役所にも、美空ひばりの碑ができました。でも、横浜の歌は少ない。前述の港町十三番地のほか、悲しき口笛(横浜関係?),港のみえる丘(カバー曲)のレコードジャケットが展示されていた。ひばりのマドロス、波止場シリーズは結構あるのだから、全部、横浜波止場にしてしまえばいいのにと思った。ぼくの好きな”波止場だよお父っあん”も入れてほしかった。

そして、第五章”裕次郎登場/そしてブルーライトヨコハマ。ここが、メイン。映画、歌謡曲の全盛期だ。ぼくらの時代だ。裕次郎の”錆びたナイフ、俺は待ってるぜ、赤いハンカチ”。赤木圭一郎の”霧笛が俺を呼んでいる”。小百合ちゃんのも、あった。”黒い傷あとのブルース”、”さようならの季節(浜田光夫共演)”その他、たくさんの横浜を舞台にしたた映画ポスターがずらりと並んでいた。
この展示室のコーナーに映写室があって、予告編だけど、先日亡くなれらた池部良と三船敏郎のやくざ映画が上映されていた。若い池部良だった。歌謡曲のジャケットも、百枚以上、あっただろうか。ブルーライトヨコハマ、ヨコハマたそがれ(五木ひろし)、伊勢佐木町ブルース(青江美奈)、女の波止場(森進一)、前述の裕次郎の映画の主題歌等々。
そして、最終章は、”港のヨーコ・ヨコハマからLOVE AFFAIRへ”。映画では健さんの”冬の華”、松坂慶子主演の”港のヨーコ・ヨコハマ”、館ひろし、柴田恭平の”あぶない刑事”、舞台では五大路子の”ヨコハマメリー”。歌では、ダウンタウンブギブギの、港のヨーコ・ヨコハマ、サザンオールスターズの”LOVE AFFAIR、マルシアの”ふりむけばヨコハマ”等々。このコーナーでは、あまり知る歌は少なかったがジャケットは、たくさん貼られていた。若い人なら知っているだろう。
さすが、ヨコハマだ。ぼくの実家のあったカワサキでは、ヒット曲はなにもない(汗)。ベイスターズもはじめは大洋ホエールズとして、川崎がフランチャイズだったが、ヨコハマにとられてしまった。でも最近、文化都市として売り出しているらしいし、住宅地としても評価が上がり、ヨコハマを猛追しているらしい。”ヨコハマたそがれ”になるのも時間の問題だ。

(ヨコハマ市民の気持ち)。カマクラは永遠に不滅です。

と言いたいけど、年寄りばかりで税収は上がらず、そのうち破綻するだろう。



























































 天狗になるな
天狗になるな











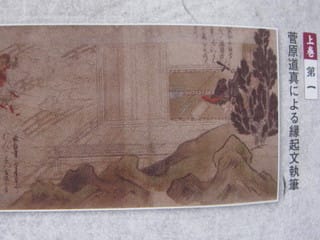
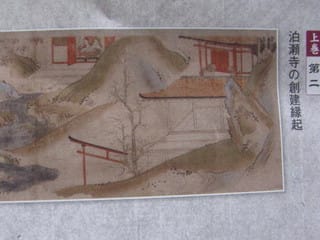















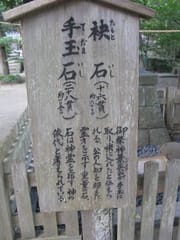












 (ヨコハマ市民の気持ち)。カマクラは永遠に不滅です。
(ヨコハマ市民の気持ち)。カマクラは永遠に不滅です。 と言いたいけど、年寄りばかりで税収は上がらず、そのうち破綻するだろう。
と言いたいけど、年寄りばかりで税収は上がらず、そのうち破綻するだろう。




