”図書館納め”をしたつもりだったが、昨日の日曜日、また行ってしまった。行くつもりはなかったが、野毛の動物園へ行く途中の、横浜市立中央図書館のポスターをみたからだ。表記の展示会を館内でやっているというので、つい覗いてしまった。
今年も多くの作家たちが逝った。井上ひさし、清水一行、立松和平、つかこうへいそして三浦哲郎。この五人の足跡を紹介するとともに、当図書館が所蔵している彼らの本を自由に読めるコーナーをつくってあるのだ。立松和平、つかこうへい、とも、62歳と早すぎる死だった。
先日、テレビでつかこうへいのドキュメント番組をみた。演出法がきわめてユニークで、脚本家でありながら、台本をほとんど無視して、役者の心から出る言葉が大事だと、その場で台詞をつくり演技を指示していた。それについては、展示室でも紹介されていて、これは、”口立て”という演出法で、むかしから旅役者も、この方法だったそうだ。”おれの書ける台本は4割、あとの6割は役者さんが書いてくれる”と、いつも言っていた。つかこうへいというと、映画の”蒲田行進曲”を思い出す。とくに大部屋俳優がスター俳優に切られ、階段を転げ落ちるシーンは忘れられない。弱者と強者のいびつな関係を表したものだった、という。彼は在日二世で、日本でも韓国でも認められなかった、暗い過去を背負っていてる。”弱者”の気持ちがよくわかるのだろう。
一方、井上ひさしは、役者には、台本通りの台詞で、一字一句変えてはならない主義だと、きいたことがある。遅筆堂と自ら名乗るほど、開演ぎりぎりまで、最良の言葉を紡いでいた。だから、そんな簡単に変えてもらっては困るということだろう。彼の多彩な著作には驚いてしまう。ひょっこりひょうたん島があると思えば、吉里吉里人があり、父と暮らせばがあり、お米を考える本がある。大江健三郎との対談もあれば、司馬遼太郎も尊敬している。日比谷公会堂での”菜の花忌”でのトークを聞きに行ったことがある。浅草のストリップ劇場”フランス座”が仕事はじめだったこともあり、ここから多くの著名な芸人が出たことから、”フランス座はストリップ界の東京大学(たいした大学ではないとおもうけど)だ”と言ったり、地元鎌倉では”広町・台峯の自然を守る会”の初代理事長や”九条の会”など政治的な会合にも参加している。鎌倉では喫茶店”門”の常連だったそうだ。窓際に座り、小町通りを歩く人々を観察するのが好きだったらしい。展示中の”東海道五十三次”という作品を取り、読み出したら、笑いころげそうになってしまった。また、ゆっくり読んでみよう。
立松和平は道元さんの本を読んだことがある。彼の書斎には空のインク瓶がたくさんころがっていたという。文学くらい効率を求めなくていいだろう、とワープロを生涯使わなかったとのことだ。和平さんのあのやさしい語り口を思い出してしまった。
清水一行は経済小説で有名だが、ぼくが読んだ本はない。ある雑誌(”財界”だったとおもう)の、かれの対談集のページが開いてあってこんな言葉が載っていて笑ってしまった。”証券マンの体質は変わらないよ、みなうそつきだ、どういう嘘つきかというと、知識が豊かでない、勉強していないという嘘つきなんだ。こうゆう人たちの投資信託などにお金をまとめて預けるなんて本当に危険きわまりないよ” ぼくもだまされた口だ、もう絶対預けない(爆)。
三浦哲郎も読んだ本がない。”故郷南部(一戸町)の家で、母が火鉢の前でよく泣いていた。その涙を吸った灰を火箸でとり、壺に入れ、涙壺と呼んだ”そんな文章があった。兄弟のほとんどが、子供の頃、自殺したり、失踪したりした、悲しい血をもつ家族だった、という。”白夜を旅する人々”がこの家族の鎮魂歌として書かれたとのことだ。是非、読んでみよう。
2010年も終わろうしている。亡き作家のみなさんを偲ぶことができた。ありがとう、横浜市立中央図書館。














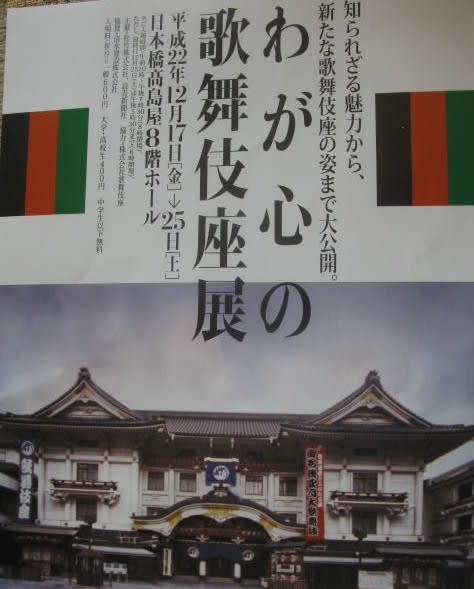





 それぞれ、3位、4位と、お姉さんたちを抑えた、見事な演技だった。次の五輪では、この娘(こ)たちが主役になるかもしれない。真央ちゃんも、うかうかできないぞ。
それぞれ、3位、4位と、お姉さんたちを抑えた、見事な演技だった。次の五輪では、この娘(こ)たちが主役になるかもしれない。真央ちゃんも、うかうかできないぞ。

 若手が伸びてくるのをみるのはうれしいことだ。
若手が伸びてくるのをみるのはうれしいことだ。

























