上野千鶴子さんの最新刊『上野千鶴子のサバイバル語録』。
先日、東京に行ったときにいただいたのですが、
とてもおもしろくて、あっという間に読んでしまいました。
編集者が選んだ言葉(語録)ということですが、
著書ごとに、わたしの好きなことば、共感したことばが
はいっていたり、いなかったり。
上野さんの本は、折りにふれて読み返しているのですが、
この語録を思い出しながら読むのも、また楽し、ですね。
クリック してね



最後まで読んでくださってありがとう
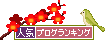
人気ブログランキング クリック してね


 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね

先日、東京に行ったときにいただいたのですが、
とてもおもしろくて、あっという間に読んでしまいました。
編集者が選んだ言葉(語録)ということですが、
著書ごとに、わたしの好きなことば、共感したことばが
はいっていたり、いなかったり。
上野さんの本は、折りにふれて読み返しているのですが、
この語録を思い出しながら読むのも、また楽し、ですね。
 上野千鶴子のサバイバル語録(上野千鶴子/文芸春/2016年01月) 毀誉褒貶のなか、長きにわたり戦い続けてきたフェミニストであり 人生お悩み相談の名手でもある著者による、初の「語録」。 過去30余年の著作群から抜粋した、名言の数々を収録。 「人生の勝負は、短期間では決まらない」 「万人に感じよく思われなくてもいい」 「人は、自分の器でしか理解しない」 「相手のとどめを刺さず、もて遊びなさい」 「どの年齢にも、よいことも悪いこともある」 ほか 家族との関係に悩んだら? 結婚、子育て、どう乗り越える? 会社と心中しないためには? ハラスメントに負けないためには? 老後、ひとりをどう過ごすか? 人生の優先順位をどうつけるか? など。 過酷な時代と人生を生き抜くための「140の金言」!  【自著を語る】とどめを刺さず、もてあそべ。そのモヤモヤは上野千鶴子のひとことで解決~『上野千鶴子のサバイバル語録』 (上野千鶴子 著)(文芸春秋:本の話WEB 2016.01.29) |
クリック してね




| 読書日記 ピックアップ 「上野千鶴子のサバイバル語録」ほか 毎日新聞 2016年3月1日 ■上野千鶴子のサバイバル語録(上野千鶴子著・文芸春秋・1350円) 日本のジェンダー研究のパイオニアがこれまでの著作で語ってきたさまざまな“語録”を抽出。その言葉に著者自身の思いを添える。「助手席から運転席へ」「友情にはメンテナンスが必要」「人生の勝負は短期では決まらない」「50代で新しい分野に参入せよ」。数々の語録は女性のみならず男性たちにも勇気と知恵をもたらしてくれる。 ■爆買いの正体(鄭世彬著、中村正人構成・飛鳥新社・1400円) 中国人や台湾人に日本の薬やコスメ商品を紹介し、“爆買いの仕掛け人”と呼ばれる著者が、中国人や台湾人はなぜこれほど日本の薬や化粧品を求めるのか、「爆買い」の背景にある彼らの文化、さらに人気の日本商品とその理由を分析、解説する。品質が高くサービス精神にあふれた日本製品の人気はこれからも収まらないと断言する。 ■個人を幸福にしない日本の組織(太田肇著・新潮新書・799円) 組織論の専門家が個人の創造性や意欲を抑圧する日本の組織の在り方に警告する。「組織はバラバラなくらいがよい」「年功制が脳を老化させる」「厳選された人材は伸びない」。グローバル化、ハイテク化、少子高齢化が進む社会に適した組織を提唱する。 |
| (北陸六味)上野千鶴子さん 老後、なんと独居が幸せ 2016年3月1日 朝日新聞 新刊『おひとりさまの最期』(朝日新聞出版、2015年)を出した。『おひとりさまの老後』『男おひとりさま道』と続いて、「おひとりさまシリーズ」3部作が完結したことになる。 刊行後、めちゃめちゃおもしろい本を見つけて、本を書く前に読んでおけばよかった、と後悔した。大阪府門真市の開業医、辻川覚志さんによる『老後はひとり暮らしが幸せ』(水曜社、13年)。60歳以上の高齢者460人を対象に調査した結果から、結論を引き出している。なにしろデータにもとづいているから説得力がある。 それによると、独居高齢者の生活満足度のほうが同居者より高く、その満足度は心身の状況が変化しても変わらない。しかも子どものある人とない人とでは満足度はほとんど変わらないことがわかった。娘が近居していると満足度はやや高くなるが、それ以外では子どもの有無が老後の満足度に関係しない、という結果が出た。 同居の家族数と満足度の関係を調べると、もっとも満足度が高いのはひとり暮らし、最低がふたり暮らし。この中には夫婦世帯が入る。あいだに緩衝地帯のないふたり暮らしはストレスが高そうだ。3人になるとやや満足度が高くなり、4人以上の3世代同居の満足度は、ほぼひとり暮らしに匹敵する。 なら3世代同居がよいか、と言えば、同居者が増えるほど、反対に満足度を減点する「悩み」が増える。カラダの不調は家族に言っても詮(せん)ないことと、同居者のいる高齢者もあきらめがついている。悩みの出処(でどころ)はすべて家族から。ひとり暮らしにはその減点要素がない。なるほど。 辻川先生の処方箋(せん)は以下の三つ。第一に、高齢になったら、生活環境を変えないことが大事。慣れ親しんだ家や土地を離れないことである。第二に、真に信頼のおける友を持つこと。心を開いて話せる友はたくさんは要らないし、遠くに離れていてたまに会うだけでもいい。反対に、近くにいて挨拶(あいさつ)を交わしたり助け合ったりする「ゆる友」ことゆるやかな交友関係では、互いに内面に踏みこむような話をしなくてもいい。 第三に、ひとり暮らしの満足度の源は、なんと言っても家族に気を使わずにすむ自由な暮らしができること。同居家族がいればいるだけ、気を使う相手が増える。また期待した分だけ、期待がはずれると傷ついたりつらい思いをしたりする。それなら最初から期待しないで、ひとり暮らしをしている高齢者のほうが、穏やかな気持ちで暮らせるようだ。 先生の結論はこれ。「満足のいく老後の暮らしを追いかけたら、なんと独居に行き着いたのです」 ほんとはわたしもこの一言を自分の本に書きたかった……のに、おひとりさまのわたしがこう言えば「負け犬の遠吠(ぼ)え」になってしまう。その点、辻川先生の主張は、エビデンス(証拠)にもとづいているから、強い。この本を読んで、子どもと同居したり施設に入ろうかと思っていたが、やめた、というお年寄りもあらわれるだろうか。(社会学者) |
| 「おひとりさま」で生きるとは 大阪YWCAで社会学者・上野千鶴子さんが講演 2016年2月29日 christiantoday 公益財団法人大阪YWCA(大阪市北区)は21日、社会学者の上野千鶴子さんを講師に迎え、「『私』を生きる~『おひとりさま』で生きるとは~」と題した講演会を開催し、約150人が参加した。「『おひとりさま』とはシングルで生きる人という意味ではなく、自立した個として生きていこうとする人です」と上野氏。会場では、女性の姿が目立ったが、夫婦で訪れたとおぼしき男性の姿もあった。 上野さんは元東京大学教授(現在は立命館大学特別招聘教授)で、女性学、ジェンダー研究の代表的な理論家であり、近年は高齢者の介護をテーマにした『おひとりさまの老後』『ケアのカリスマたち―看取りを支えるプロフェッショナル』など多くの著作を出版、2011年からは女性をつなぎエンパワメントするための認定NPO法人「ウィメンズアクションネットワーク」の理事長としても活動している。 冒頭「最近、家に民生委員の人から訪問の問い合わせがあって、自分が見守りの対象の独居老人であることを知りました」と語ると、会場からは大きな笑い声が起こった。全国の福祉や介護の現場を実際に訪ねて目にした実例を交え、シリアスでリアルながらも、時に関西弁も交えながらのユーモア溢れる"上野節"の講演に、参加者は熱心に耳を傾けた。 死・看取りへの社会の関心の高まり 上野さんは、死や葬式、遺体など、以前は語ることがタブーだと思われていたことについてオープンに論じられることが増えたと述べた。『おひとりさまの老後』を出版して話題となった2007年から現在までの間にも、社会は大きく変わり、今や高齢者の4人に1人が独居している。いまや「おひとりさまは少数派から多数派になりつつあります」と語った。 独居の理由は死別、離別に加えて非婚化だ。統計では生涯非婚率(50歳まで未婚の人の割合)は、男性で約2割、女性は約1割に上る。上野さんと同世代に当たる団塊世代では、女性の非婚率は約3パーセント、ピークだった1960年代には生涯結婚率は男性97パーセント、女性98パーセントだったという。20年後にこの比率は、男性は3人に1人、女性は5人に1人になると推測されている。「全員結婚社会は終わりました」と上野さんは話す。 家族の形も急速に変わった。かつて日本では、女性は当然のように家族介護の担い手とされていたが、上野さんは「介護力としての嫁は、今や絶滅危惧種です」「息子の嫁に老後の世話を期待することもできなくなりました」と話す。 独居高齢者の数も増えている。社会学者の河合克義さんは「社会的孤立」の実数を調べる尺度として「正月三が日を一人で過ごしたか」を調査したところ、前期高齢者では男性61・7パーセント、女性26・5パーセント、後期高齢者では男性46・8パーセント、女性32・0パーセントが「はい」と答えたという。 いわゆる「孤独死」は男性が多く、特に民生委員による見守りの対象となる65歳以降の高齢者よりも、それ以前の50代後半から60代前半の高齢者直前の世代に集中しているのだという。 「おひとりさまの老後」の課題と新しい取り組み 一方で、女性で最大の問題は経済問題で、単身高齢者女性の貧困率は5割以上になるという。これは高度成長期の予測を超えた超高齢社会の到来に年金制度の整備が追いついていないこと、介護が家族頼みのものとして設計されていたことに原因があると上野さんは述べた。 しかし、さまざまな新しい老後の在り方も見られると、自ら訪ねた実例を紹介した。 高齢者は住宅弱者と思われているが、実際は持ち家率が高く(統計では65歳以上で8割以上)、人口減少社会を迎える中「住宅あまり現象」も生じている(空家率は全国で13パーセント、東京都で11パーセント、約75万戸)。施設ではなく「居住福祉」が注目され、民間ではパイオニア的なさまざまな取り組みが増えているという。新潟県の長岡市では、施設を解体し、地域の空いた土地や建物を活用して介護サービスをデリバリーし「住み慣れた地域」「家族の近くで暮らす」という取り組みを進めている特養があるという。 また、気心の知れた仲間と共にまず住まいをつくり、共に生活する「コレクティブ・リビング」という施設も生まれてきた。東京の日暮里には、中学校の跡地を利用した高齢者住宅とコレクティブハウスの入った施設があり「コレクティブクッキング」という共同食堂がある。ここにはシングルマザーも入居しており、年配の女性たちに子どもの世話を手伝ってもらえるため「こんなに子どもが育てやすいならもう一人産んでもいいわよ」という母親の声も聞いたという。 これら新しいタイプの事業には費用がかかるが、地域の250人から市民ファンドを募り、4億円を集めて施設を始めた女性など、日本各地の新しい動きが紹介された。一方でまだまだ施設によってはサービスの質の差も大きいとの課題もあるという。 死と看取りの選択肢 上野さんは、施設を訪ねるとき「お看取りはなさいますか?」と必ず聞くという。最期をどこで迎えるかは、人生の最後となる重要な選択だと考えるからだ。かつて日本では、ほとんどが家で最期を迎えたが、現在は病院が80パーセント、在宅死が13パーセント、そして施設が6パーセント。「死の病院化」が進んだ。 「現代の社会では在宅死の選択肢が(示されて)ないが、介護力があれば在宅死は可能です」と上野氏は話す。2015年に定められた「医療介護一括法」も、社会保障費削減の大勢の中、病床数や入院期間の抑制、介護老人施設の建設制限や民営化と同時に、在宅誘導を進めており「ほぼ在宅、ときどき病院」が国の方針なのだという。さらに近年は一人で老後を暮らすための制度ができ始めている。 「高齢者が家にいたいというのは、家族と一緒にいたいのか、自分の家にいたいのかをまず考えるべきです」と上野さん。多くの場合、高齢者が施設に入るかどうかの意思決定は、家族が握っているという。暮らし慣れた、思いの詰まった家で暮らしたくても、同居家族に迷惑をかけないようにと施設に入るお年寄りは多い。それならば、一人で最期まで家で暮らすことも尊重されるべきではないかというのが、上野さんの考え方だ。現在、がんの場合はペインコントロールの技術などが進み、すでに在宅看取り率95パーセントを達成している訪問診療所もある。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(以下略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
最後まで読んでくださってありがとう

人気ブログランキング クリック してね



 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。明日もまた見に来てね













 寺町みどり @midorinet002
寺町みどり @midorinet002





