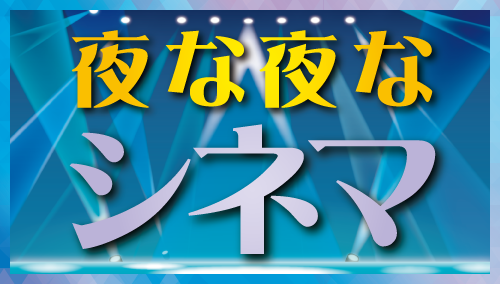『バッド・ティーチャー』(原題:Bad Teacher)
監督:ジェイク・カスダン
出演:キャメロン・ディアス,ジャスティン・ティンバーレイク,ジェイソン・シーゲル,
ルーシー・パンチ,ジョン・マイケル・ヒギンズ,フィリス・スミス他
数カ月前に劇場で観そびれて、DVD化を楽しみにしていました。
10月初めにレンタル開始になり、すぐに観たのに今頃アップ。
中学教師のエリザベスは、教育への熱意も生徒への愛情も皆無。
目標は早く玉の輿に乗ってこの学校を去ることだけ。
金持ちの男を騙くらかしてようやく結婚にこぎつけたつもりが、
目論見がバレて派手に別れを告げられてしまう。
辞めるはずだった学校に逆戻り。やる気がないのは変わらない。
ところがそこへ現れたのが、イケメンぼんぼん代理教師のスコット。
なんとしてでも彼を落とさなければ。エリザベスの目はランラン。
この歳でライバルに勝つには、もう胸をデカくするしかない。
豊胸手術を受けようと整形外科を訪れるが、予約は前払いが条件らしい。
クレジットカードはすべて使用停止、貯金も当然ない。
手術費用を稼ぐため、エリザベスはなりふりかまわず行動を始める。
最初のうちはまるでいただけません。
40歳になってもキュートなキャメロン・ディアスとはいえ、
これだけ女のやらしさを全開にされるとドン引き。
異性から見ればこれも可愛くて許せる範囲なのかもしれませんが、
同性から見るとちょっと辟易してしまうほど。
とはいうものの、見ていられないこともなくて、やっぱり可笑しい。
生徒が父兄らの車を洗って金をもらうという洗車デーには、
目のやり場に困るいでたちで登場します。
で、通常はこの日の儲けはすべて学校行事に回されるところ、
エリザベスはそのうちのなんぼかをしっかりポケットへ。
公開テストで1位だったクラスには報奨金が出ると聞けば、
担任するクラスの授業は打って変わって厳しいものに。
この授業の様子はかなり笑えます。
いくら頑張ったところで1位は無理だと気づいたら、
今度はテスト内容を事前に知るほうへと方向転換。
アホではありませんから、やることなすことずるくて憎たらしい。
彼女と張り合うリンも最初は気の毒なのですが、
止めておけばいいものを同じ土俵へ上がった頃から、
どっちがマシかわからなくなってしまいます。
エリザベスが唯一心を許しているというのか、
どうでもいいからありのままを見せている相手が体育教師のラッセル。
その役のジェイソン・シーゲルは冴えない男ではありますが、
『寝取られ男のラブ♂バカンス』(2008)もそうだったように、
なかなかイイ奴を演じさせるとピッタリです。
ジャスティン・ティンバーレイク演じるスコットのほうが実はキモく、
ジェイソン・シーゲルがオイシイところをかっさらった印象。
これだけ悪態をついておいて、最後が素直すぎるんだよと思わないでもないですが、
そこがやっぱりキャメロン・デイアス!?
アホくさいけど、観終わったときは爽やかなのでした。
監督:ジェイク・カスダン
出演:キャメロン・ディアス,ジャスティン・ティンバーレイク,ジェイソン・シーゲル,
ルーシー・パンチ,ジョン・マイケル・ヒギンズ,フィリス・スミス他
数カ月前に劇場で観そびれて、DVD化を楽しみにしていました。
10月初めにレンタル開始になり、すぐに観たのに今頃アップ。
中学教師のエリザベスは、教育への熱意も生徒への愛情も皆無。
目標は早く玉の輿に乗ってこの学校を去ることだけ。
金持ちの男を騙くらかしてようやく結婚にこぎつけたつもりが、
目論見がバレて派手に別れを告げられてしまう。
辞めるはずだった学校に逆戻り。やる気がないのは変わらない。
ところがそこへ現れたのが、イケメンぼんぼん代理教師のスコット。
なんとしてでも彼を落とさなければ。エリザベスの目はランラン。
この歳でライバルに勝つには、もう胸をデカくするしかない。
豊胸手術を受けようと整形外科を訪れるが、予約は前払いが条件らしい。
クレジットカードはすべて使用停止、貯金も当然ない。
手術費用を稼ぐため、エリザベスはなりふりかまわず行動を始める。
最初のうちはまるでいただけません。
40歳になってもキュートなキャメロン・ディアスとはいえ、
これだけ女のやらしさを全開にされるとドン引き。
異性から見ればこれも可愛くて許せる範囲なのかもしれませんが、
同性から見るとちょっと辟易してしまうほど。
とはいうものの、見ていられないこともなくて、やっぱり可笑しい。
生徒が父兄らの車を洗って金をもらうという洗車デーには、
目のやり場に困るいでたちで登場します。
で、通常はこの日の儲けはすべて学校行事に回されるところ、
エリザベスはそのうちのなんぼかをしっかりポケットへ。
公開テストで1位だったクラスには報奨金が出ると聞けば、
担任するクラスの授業は打って変わって厳しいものに。
この授業の様子はかなり笑えます。
いくら頑張ったところで1位は無理だと気づいたら、
今度はテスト内容を事前に知るほうへと方向転換。
アホではありませんから、やることなすことずるくて憎たらしい。
彼女と張り合うリンも最初は気の毒なのですが、
止めておけばいいものを同じ土俵へ上がった頃から、
どっちがマシかわからなくなってしまいます。
エリザベスが唯一心を許しているというのか、
どうでもいいからありのままを見せている相手が体育教師のラッセル。
その役のジェイソン・シーゲルは冴えない男ではありますが、
『寝取られ男のラブ♂バカンス』(2008)もそうだったように、
なかなかイイ奴を演じさせるとピッタリです。
ジャスティン・ティンバーレイク演じるスコットのほうが実はキモく、
ジェイソン・シーゲルがオイシイところをかっさらった印象。
これだけ悪態をついておいて、最後が素直すぎるんだよと思わないでもないですが、
そこがやっぱりキャメロン・デイアス!?
アホくさいけど、観終わったときは爽やかなのでした。