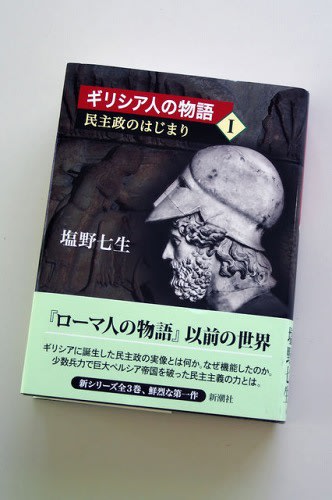
塩野さんの「ギリシア人の物語」を一昨日読みおえたので、印象がうすれないうちに、感想を書いておく。
塩野さんといえば、歴史と文学の双方にまたがるジャンルで大きな仕事をしていて、評価もほぼ定まっている。ご高齢になったいまでも、物書きとしては、最高レベルの水準を維持しているといっていい。ファンも大勢いるから、ベストセラーにはならないまでも、売れゆきは芳しいものがあるだろう。
単行本で全15巻にもおよぶ「ローマ人の物語」は、この人の畢生の大作。わたしは単行本で読み、文庫本で再読している。
人間に対する洞察力がじつに鋭利。ときには峻烈極まりない。このひとはなんといっても「マキュアベリの徒」なのである。なにものにも曇らされることない、クリアな眼を、つねに資料の背後にいたるまで光らせている。足りないとあれば想像力で補ってあるが、むろん恣意的なフィクションとなりそうな記述は避けている。
こういう人が書いた本が、おもしろくないはずはない。このところブレイクしている観のある佐藤優さんも、塩野さんとは異質な「マキュアベリの徒」である。まだ評価が定まるところまではいっていないが、現在の論壇人の中では、飛びぬけた仕事をしているようだ。しかし、書き過ぎが災いし、やや玉石混淆だな・・・とわたしは睨んでいる。
それに比べると、ローマ滞在中の塩野七生さんは、年に1冊というペースをしっかり守っているようである。文体はいたって簡潔、しかも選ばれていることばの精度は高いから、説得力があり、叙述の的をはずすことはない。流麗とはいえないが、テンポがいいので、慣れてくれば、とても読みやすく、うまいこと「ヤマ場」を設けているため、つぎのページを繰らずにはいられない。これは大著「ローマ人の物語」から一貫している。よき編集者(あるいは読者)がそばにいて、彼女の原稿に、的確なアドバイスをしているのかもしれない。
さて、本書もまた秀逸なドキュメンタリーである。個人と集団。集団は民衆であり、民主制都市国家群。その中で彼女が終始丹念に追跡しているのは、アテネとスパルタ。この二国が、古代ギリシアを代表する国家だからである。
古代ギリシヤにおいて、民主制とはなんであったのか? それはどう誕生し、引き継がれ、運用されてきたのか? そして、そもそも「国家」とは人間にとって、何であるのか?
本書にも多くの登場人物が存在するが、彼女がいちばん強烈なスポットライトを浴びせているのは、対ペルシア戦役の立役者テミストクレス。
塩野さんは、英雄は好きだが、たぶん、豪傑は好きではない。国家存亡の危機を、アテネのテミストクレスやスパルタのパウサニアスがどう乗り切ったのか、まさに手に汗にぎる人間ドラマが展開される。その戦役での英雄は、やがては追放されたり、牢獄で餓死したりする。独裁者を嫌った社会は、独裁者になりそうな人に対し、じつに過酷なふるまいをするのである。「危機は去った。あんたらはもう用済みになったのだから、立ち去れ」ということである。テミストクレスがいなかったら、ギリシアはペルシアの属国に落とされていただろうに。
民衆と、その民衆に基礎を置く民主主義とは、かくも残酷なふるまいをするものなのかと、わたしは胸がふるえた。
塩野さんは、その時代を生きた人間の“真実”に迫りたいのである。近・現代の文献にはあらかた眼を通している。それらを参照しながら、単に祖述するだけなら、凡庸な大学教授にもできる。そこからさきが、作家塩野七生の腕の見せ所。本書が十分な文献批判の上に成り立っていることを、わたしは信じて疑わない。
同時代の歴史・・・、ヘロドトスの「歴史」であろうが、トゥキディデスの「戦史」であろうが、疑わしいとなれば、塩野さんの鋭い批判をまぬがれない。
本書ばかりでなく、彼女の著作の多くは、歴史書、文学書というジャンルを超えた、政治や戦争の指南書でもある。リアルポリティクスの神髄をわきまえている人のことばが、各章ごとに刻みこまれている。爬虫類のような冷徹な眼。しかし、その裏で、人間に対する、熱い共感が脈打っている。
本書を読みながら、わたしは幾度か涙をこらえることができなかった。読み終わってもいないのに、また数ページ、数十ページ前にもどって、なにが書かれていたか、確かめたくなった。それは本書が、イメージの喚起力と、真情への訴求力をそなえている証拠であるとはいえないだろうか?
ギリシアの都市国家群と、大国ペルシアとの死闘。前にも書いたが、ここから学ばねばならないことは、あまりに多い。
戦争までと、戦争のあと。なにが生まれ、なにが失われたのかを、わたしも見届ける。膨大な数の指揮官、戦士、市民、奴隷の血が流されたのである。
こういう本を、塩野さんが、日本語で、日本人のために著述してくれたことを、こころの底からわたしは感謝せずにいられない。とはいえ、まだ第1巻が2015年12月に刊行されたばかり。続編の刊行が待たれる。ギリシア文化の爛熟期を、彼女はどう描きだしてくれるのだろう?
※評価:☆☆☆☆☆(5点満点)
塩野さんといえば、歴史と文学の双方にまたがるジャンルで大きな仕事をしていて、評価もほぼ定まっている。ご高齢になったいまでも、物書きとしては、最高レベルの水準を維持しているといっていい。ファンも大勢いるから、ベストセラーにはならないまでも、売れゆきは芳しいものがあるだろう。
単行本で全15巻にもおよぶ「ローマ人の物語」は、この人の畢生の大作。わたしは単行本で読み、文庫本で再読している。
人間に対する洞察力がじつに鋭利。ときには峻烈極まりない。このひとはなんといっても「マキュアベリの徒」なのである。なにものにも曇らされることない、クリアな眼を、つねに資料の背後にいたるまで光らせている。足りないとあれば想像力で補ってあるが、むろん恣意的なフィクションとなりそうな記述は避けている。
こういう人が書いた本が、おもしろくないはずはない。このところブレイクしている観のある佐藤優さんも、塩野さんとは異質な「マキュアベリの徒」である。まだ評価が定まるところまではいっていないが、現在の論壇人の中では、飛びぬけた仕事をしているようだ。しかし、書き過ぎが災いし、やや玉石混淆だな・・・とわたしは睨んでいる。
それに比べると、ローマ滞在中の塩野七生さんは、年に1冊というペースをしっかり守っているようである。文体はいたって簡潔、しかも選ばれていることばの精度は高いから、説得力があり、叙述の的をはずすことはない。流麗とはいえないが、テンポがいいので、慣れてくれば、とても読みやすく、うまいこと「ヤマ場」を設けているため、つぎのページを繰らずにはいられない。これは大著「ローマ人の物語」から一貫している。よき編集者(あるいは読者)がそばにいて、彼女の原稿に、的確なアドバイスをしているのかもしれない。
さて、本書もまた秀逸なドキュメンタリーである。個人と集団。集団は民衆であり、民主制都市国家群。その中で彼女が終始丹念に追跡しているのは、アテネとスパルタ。この二国が、古代ギリシアを代表する国家だからである。
古代ギリシヤにおいて、民主制とはなんであったのか? それはどう誕生し、引き継がれ、運用されてきたのか? そして、そもそも「国家」とは人間にとって、何であるのか?
本書にも多くの登場人物が存在するが、彼女がいちばん強烈なスポットライトを浴びせているのは、対ペルシア戦役の立役者テミストクレス。
塩野さんは、英雄は好きだが、たぶん、豪傑は好きではない。国家存亡の危機を、アテネのテミストクレスやスパルタのパウサニアスがどう乗り切ったのか、まさに手に汗にぎる人間ドラマが展開される。その戦役での英雄は、やがては追放されたり、牢獄で餓死したりする。独裁者を嫌った社会は、独裁者になりそうな人に対し、じつに過酷なふるまいをするのである。「危機は去った。あんたらはもう用済みになったのだから、立ち去れ」ということである。テミストクレスがいなかったら、ギリシアはペルシアの属国に落とされていただろうに。
民衆と、その民衆に基礎を置く民主主義とは、かくも残酷なふるまいをするものなのかと、わたしは胸がふるえた。
塩野さんは、その時代を生きた人間の“真実”に迫りたいのである。近・現代の文献にはあらかた眼を通している。それらを参照しながら、単に祖述するだけなら、凡庸な大学教授にもできる。そこからさきが、作家塩野七生の腕の見せ所。本書が十分な文献批判の上に成り立っていることを、わたしは信じて疑わない。
同時代の歴史・・・、ヘロドトスの「歴史」であろうが、トゥキディデスの「戦史」であろうが、疑わしいとなれば、塩野さんの鋭い批判をまぬがれない。
本書ばかりでなく、彼女の著作の多くは、歴史書、文学書というジャンルを超えた、政治や戦争の指南書でもある。リアルポリティクスの神髄をわきまえている人のことばが、各章ごとに刻みこまれている。爬虫類のような冷徹な眼。しかし、その裏で、人間に対する、熱い共感が脈打っている。
本書を読みながら、わたしは幾度か涙をこらえることができなかった。読み終わってもいないのに、また数ページ、数十ページ前にもどって、なにが書かれていたか、確かめたくなった。それは本書が、イメージの喚起力と、真情への訴求力をそなえている証拠であるとはいえないだろうか?
ギリシアの都市国家群と、大国ペルシアとの死闘。前にも書いたが、ここから学ばねばならないことは、あまりに多い。
戦争までと、戦争のあと。なにが生まれ、なにが失われたのかを、わたしも見届ける。膨大な数の指揮官、戦士、市民、奴隷の血が流されたのである。
こういう本を、塩野さんが、日本語で、日本人のために著述してくれたことを、こころの底からわたしは感謝せずにいられない。とはいえ、まだ第1巻が2015年12月に刊行されたばかり。続編の刊行が待たれる。ギリシア文化の爛熟期を、彼女はどう描きだしてくれるのだろう?
※評価:☆☆☆☆☆(5点満点)


























