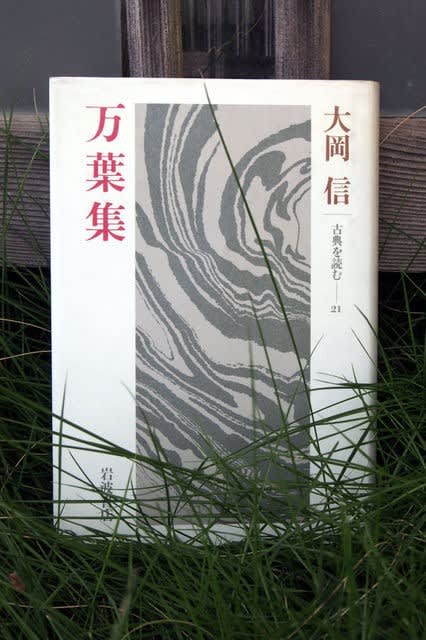
天(あめ)の海に雲の波立ち月の船星の林に漕ぎ隠る見ゆ
「万葉集」(古典を読む21 岩波書店)で、大岡信さんは《さて巻の七を開いて巻初にこの歌を見出したときの新鮮な驚きは忘れがたい》と述べている。
わたしも同じである。
月の船ですよ、
星の林ですよ。
これを書いたのは柿本人麻呂!
これまで「万葉集」は、ぱらりぱらりと必要なところだけを、虫が食うように読んできただけなので、この歌は視野には入ってこなかった。
ここしばらく、またしても「万葉集」の周辺をうろついている(~o~) 「古今和歌集」や「新古今和歌集」よりも、普通の読者として「万葉集」の方がおもしろいのだ。
令和になったとき、巻の五だけは一通り読んだ。しかし、巻の七はこれまで読んだ経験がなかった。
やや長文となるが、大岡さんのコメントを書き写しておこう。
《さて今の天の大海を詠んだ歌、よくもまあこれだけ天象を並べたてて破綻をきたさなかったものと感心させられる。その秘密は、なんといっても、月の船が星の林に「漕ぎ隠る見ゆ」という印象鮮やかな結句にあることはいうまでもない。
これは注釈書にも時に指摘されているように、おそらく七夕(たなばた)伝説を詠んだ歌ではなかろうかと思われる。七夕伝説は、天象をめぐる説話のうち例外的に古代日本人に深く訴えるところのあったもので、平安朝和歌にも作例はおびただしい。
それはたぶん、日本における恋愛、結婚の形態が、鎌倉期に入るまでは、男が女のもとに夜だけ通ってゆくいわゆる通い婚の形態をとっていたことと、深い関わりのあることだろう。
女はもちろん、男にとっても、七夕の牽牛と織姫の哀話は、自分たちの生活体験に即してみても十分感情移入できる伝説だった。
「星の林に漕ぎ隠る見ゆ」という空想は、一年に一度逢うことのできた男と女が、一艘の船の中に相擁しつつ、林の奥へ漕ぎ隠れてゆく情景を思わせないではおかない。》(「七 柿本人麻呂歌集秀逸」191ページ)
もう一度、引用しておく。
天(あめ)の海に雲の波立ち月の船星の林に漕ぎ隠る見ゆ
どういったらいいのか・・・、明治以降の近代短歌と比べても、まったく古さを感じさせない。
天空を海原に喩えているのだ。それ自体はさほどめずらしくはないのかもしれないが、この歌がほんとうに「万葉集」の歌なのか!?
壮大な情景を、五七五七七の韻律のなかへ見事に封じ込めてしまった。
「うーむ、お見事!」
立ち上がって、手を叩きたくなった。手を叩くかわりに、割り込み記事としてこの一章を書いておく(^^♪
現に詩をを書いているわたし・・・が驚倒している。
いやはや、柿本人麻呂、心底畏るべし!

(ネット上の画像を拝借しています)
※ いつものことですが、引用文はわたしの判断により改行しています。
「万葉集」(古典を読む21 岩波書店)で、大岡信さんは《さて巻の七を開いて巻初にこの歌を見出したときの新鮮な驚きは忘れがたい》と述べている。
わたしも同じである。
月の船ですよ、
星の林ですよ。
これを書いたのは柿本人麻呂!
これまで「万葉集」は、ぱらりぱらりと必要なところだけを、虫が食うように読んできただけなので、この歌は視野には入ってこなかった。
ここしばらく、またしても「万葉集」の周辺をうろついている(~o~) 「古今和歌集」や「新古今和歌集」よりも、普通の読者として「万葉集」の方がおもしろいのだ。
令和になったとき、巻の五だけは一通り読んだ。しかし、巻の七はこれまで読んだ経験がなかった。
やや長文となるが、大岡さんのコメントを書き写しておこう。
《さて今の天の大海を詠んだ歌、よくもまあこれだけ天象を並べたてて破綻をきたさなかったものと感心させられる。その秘密は、なんといっても、月の船が星の林に「漕ぎ隠る見ゆ」という印象鮮やかな結句にあることはいうまでもない。
これは注釈書にも時に指摘されているように、おそらく七夕(たなばた)伝説を詠んだ歌ではなかろうかと思われる。七夕伝説は、天象をめぐる説話のうち例外的に古代日本人に深く訴えるところのあったもので、平安朝和歌にも作例はおびただしい。
それはたぶん、日本における恋愛、結婚の形態が、鎌倉期に入るまでは、男が女のもとに夜だけ通ってゆくいわゆる通い婚の形態をとっていたことと、深い関わりのあることだろう。
女はもちろん、男にとっても、七夕の牽牛と織姫の哀話は、自分たちの生活体験に即してみても十分感情移入できる伝説だった。
「星の林に漕ぎ隠る見ゆ」という空想は、一年に一度逢うことのできた男と女が、一艘の船の中に相擁しつつ、林の奥へ漕ぎ隠れてゆく情景を思わせないではおかない。》(「七 柿本人麻呂歌集秀逸」191ページ)
もう一度、引用しておく。
天(あめ)の海に雲の波立ち月の船星の林に漕ぎ隠る見ゆ
どういったらいいのか・・・、明治以降の近代短歌と比べても、まったく古さを感じさせない。
天空を海原に喩えているのだ。それ自体はさほどめずらしくはないのかもしれないが、この歌がほんとうに「万葉集」の歌なのか!?
壮大な情景を、五七五七七の韻律のなかへ見事に封じ込めてしまった。
「うーむ、お見事!」
立ち上がって、手を叩きたくなった。手を叩くかわりに、割り込み記事としてこの一章を書いておく(^^♪
現に詩をを書いているわたし・・・が驚倒している。
いやはや、柿本人麻呂、心底畏るべし!

(ネット上の画像を拝借しています)
※ いつものことですが、引用文はわたしの判断により改行しています。



























