

まるで時空の狭間に落ちてしまってその場から這い上がれずに周囲の時流から取り残されたかの如く、温泉街全体が寂しく鄙びきっている信州の霊泉寺温泉。当地を思い出してその風景を描いてみよと命じられても、その絵はつげ義春の作品のように陰鬱なモノトーンの世界となってしまうでしょう。そんな温泉街に佇む地味な趣きの公民館のような共同浴場が今回の主役であります。建物の前に立っている赤い寸胴型のポストが良い味出してますね。ここを訪れるのは5年ぶりか…。


潰れた理容店のようなくすんだ色合いの入口ドアを開けると、(男湯の場合は)すぐ左手に番台があり、カウンターに置かれた料金箱に100円玉2枚を投入します。番台の小窓を覗いて挨拶したら、中ではおばあちゃんがコタツに入ってテレビを視ていました。

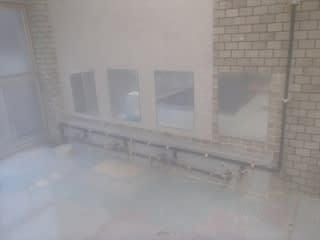
脱衣室は棚があるばかりでこぢんまりとした造りですが、その一方で浴室は意外と広く、横長のガラス窓に面して長方形の大きな浴槽がひとつ据えられています。洗い場には湯と水のカランが4組設置されており、カランから出てくるお湯はおそらく源泉使用かと思われます。

一般的に浴室で時計を設ける場合は室内の壁に金具などで引っ掛ける場合が多いかと思いますが、こちらでは窓の外のコンクリ土台の上に置かれていました。


青いタイルが敷き詰められた浴槽には無色透明のお湯が張られ、そのタイルの色のためにお湯がより一層クリアに輝いているように見えました。浴槽最奥に括り付けられた玄武岩質の溶岩みたいな岩から塩ビ管が突き出ており、そこからトポトポと音を立ててお湯が注がれています。湯口のお湯をグビグビ飲む爺様もいらっしゃったので、私も手に受けて飲んでみますと、ふんわりとした石膏の味が感じられたとともにその匂いが鼻へ抜けてゆき、更には弱タマゴ感と弱砂消しゴム感を足して2で割ったような硫黄感も仄かに得られました。なお湯使いは放流式であり、館内表示によれば「塩素滅菌」を実施しているそうですが、塩素っぽさは全く感じられなかったので、おそらく毎日の換水清掃時に塩素系薬剤を用いて消毒しているということかと思われます。
入浴中の肌を擦ると石膏泉らしい弱い引っ掛かりがあり、また浴槽中でお湯を掻いてみるとトロミが伝わってきました。更には長湯していると肌にうっすらとした気泡の付着も見られました。分析表を見るとギリギリのところで石膏泉になれずに単純温泉へ分類されていますが、実質的には石膏泉(含芒硝酸石膏泉)と見做しても差し支えないかと思われます。以前は加温されていたはずですが、噂によれば数年前に同じ源泉を使用していた施設が減ったことに伴い共同浴場への供給量が増加して温度も上がったらしく、もしかしたら現在は加温していないのかもしれません。源泉のままで加水せずとも実に良い湯加減が維持されていました。

上画像のように、浴槽の脇の床には穴をパテで埋めた跡があるのですが、これは長野県の温泉施設でよく見られる独特の排湯方式、すなわち浴槽湯面より若干低い位置の洗い場床に穴があけられ、その穴と直結した浴槽内の吸入口からお湯が流れて排湯されてゆく設備が採用されていた跡であろうと思われます(浴槽内にもやはり埋められた穴がありました)。現在では浴槽縁の上をお湯が乗り越えてゆくごくごく普通のオーバーフローによって排湯されていましたが、どうして長野県ではこの手の方法を採用する温泉施設が多かったのでしょうか(何らかの理由で県から指導があったのかもしれませんね)。
鄙びた佇まいとシンプルな設備の共同浴場ですが、お湯の良さが評判を呼ぶのか、特に夕方になると車に乗って近所から次々に入浴客がやってきて混雑することが多く、混雑時間帯に利用するとお湯が濁っていることがあるので、なるべくでしたらそうしたタイミングを避けて利用することをおすすめします。ここは外観や設備が草臥れていたってお湯が良ければ人は集まってくるという好事例ですね。
霊泉寺温泉町有泉
アルカリ性単純温泉 43.8℃ pH8.9 掘削動力揚湯 溶存物質996.3mg/kg 成分総計996.3mg/kg
Na+:80.6mg(24.66mval%), Ca++:213.8mg(74.96mval%),
SO4--:620.8mg(90.70mval%),
H2SiO3:28.2mg,
(平成14年12月27日)
上田駅より千曲バスの鹿教湯線で「宮沢」バス停下車、徒歩20分(約1.8km)
長野県上田市平井2530
霊泉寺温泉ホームページ
7:00~21:00 月曜定休
200円
備品類なし
私の好み:★★★
●散策
黄昏の温泉地、霊泉寺。湯上りにその集落を彷徨して、懐かしの昭和へタイムスリップしてみました。


曹洞宗の古刹、金剛山霊泉寺。安和元(968)年の開山と伝えられ、最盛期には19もの伽藍を擁していたんだそうですが、明治前期に一部の門を残して烏有に帰してしまい、同44年に現在の本堂が再建されたんだとか。その焼け残った門が画像左(上)の不明(あかずの)門であり、保護のために屋根で覆われています。


不明門の下には巨大な根っこが印象的な切り株が残っているのですが、これは2008年7月に倒壊してしまった樹齢700年の大ケヤキのもの。境内の隅には火の見櫓が屹立しています。

私のHDDを探してみたら、大ケヤキが倒壊する4ヶ月前の2008年3月に自分で撮影した画像を発見しました(上画像)。火の見櫓をはるかに上回る巨木だったんですね。


雪道の路傍に立つ電信柱にはとってもレトロな広告看板が。とても2013年の風景であるとは思えません。


霊泉寺集落唯一のお店は既に店じまいしており、その前に立ち並んでいる自販機も使われていませんでした。


霊泉寺温泉診療所。建物は静まり返っており、扉も固く閉ざされています。まるで廃墟のような雰囲気でしたが、現在では診察していないのでしょうか。

診療所付近で見つけた旧式の道路標識「警笛鳴らせ」。標識マニアのサイトによれば、このタイプは昭和38年あたりから姿を消していったそうですが、ということはある意味でこの霊泉寺という土地は昭和38年から時が止まったままなのかもしれません。















