一昨日は、友人に招待されて文化の香り2題を訪れました。
日本橋の三井記念美術館では、「蔵王権現と修験の秘宝」として、奈良吉野の金峯山寺、鳥取の
三佛寺他からの金剛蔵王権現や国宝、重文をずらり一堂に集めた特別展でした。
これまでも、あちこちで蔵王権現像を見る機会はありましたが、これほど多体を一堂に並んだ姿は、
さすがに圧巻と言わざるを得ません。しかも、三井記念美術館そのものも重文で、このような展示場での
雰囲気は一層重厚の度合いを高めているのでした。
1階ホワイエ 美術館入口

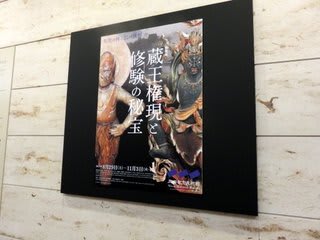
蔵王権現とは、ウイキペディアによれば、“日本独自の混淆宗教である修験道の本尊である。
正式名称は金剛蔵王権現、または金剛蔵王菩薩とよばれ、インドに起源を持たない日本独自の仏
(仏教の仏が仮の姿で現れたとする日本の神)で、金峯山寺本堂(蔵王堂)の本尊として知られる。
また、権現とは「権(かり)の姿で現れた神仏」の意であり、仏、菩薩、諸尊、諸天善神など
すべての力を包括しているという”とあります。
蔵王権現像
 (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより)
さらに、“修験道とは、日本各地の霊山を修行の場とし、深山幽谷に分け入り厳しい修行を行う
ことによって超自然的な能力「験力」を得て、衆生の救済を目指す実践的な宗教でもあり、この山岳
修行者のことを「修行して迷妄を払い験徳を得る 修行して その徳を驗わす」ことから修験者、
または山に伏して修行する姿から山伏と呼ぶ”とあり、役行者の姿を見るにつけ、その厳しさが
うかがい知れるのです。
修験道は、言い換えれば “修験道は神仏習合の信仰であり、日本の神と仏教の仏(如来・菩薩・明王)が
ともに祀られ、その表現形態として、権現がある” のです。 で、修行の場は、“日本古来の
山岳信仰の対象であった大峰山(奈良県)や白山(石川県)など、「霊山」とされた山々であり、
中でも、熊野三山(熊野の本宮・新宮・那智の3社)への信仰は、平安時代の中期から後期にかけて、
天皇をはじめとする多くの貴族たちの参詣を得て、隆盛を極めた”とありました。
また、樹氷やお釜で有名な “蔵王”(宮城県と山形県の境の連峰)は、その昔、吉野から
蔵王権現が勧請され、平安時代には修験者が修行するようになったため蔵王山と呼ばれるようになった
とか。 もともと、刈田嶺(刈田岳)と呼ばれて、山岳信仰の山であったそうですが、江戸時代には、
「蔵王大権現社」に参詣する庶民で賑わうようになり、積雪で参詣できない冬季は、麓のお旅宮に
遷座するほどになったとかで、ここが、現在の遠刈田温泉なのだそうです。
また、展示のパネルでは、修験者が山伏姿で険しい岩を辿る姿が映しだされて、山上が岳周辺の
険しい雰囲気を伝えていました。
私は、35年前に関西勤務があり、その折に数名で、山伏の先達で修験の一部を体験しましたが、
この時の印象は、当ブログ記事(2015.7.8)“蔵王堂蛙飛び”に述べています。その一部を引用しました。
“絶壁の崖をつかまるところがなく、岩に吸い付くようにして登ったり、大岩の外側を素手で回るなど、
大変怖い思いをした記憶があります。 7か所くらい、そのような怖いところがあって、それを完遂した
後は、自分自身が大変大きく感じられ、何物にも動じない強い精神力が湧いてくるのが感じられたのを
覚えています。 なるほど、修行というのはこういう事なんだ・・と。よく、大峰山の “谷底覗きの行”が
大変怖いと話しに出てきますが、こちらも体験しましたが、崖を回る行に比べると、特になんてこと
ない・・というほどのものでした。”
話はそれましたが、権現と深山幽谷の世界に引き込まれた後、近くの近代的なCOREDO室町2で
ランチを済ませて、地下鉄を乗り継いで代々木上原にある「古賀政男音楽博物館」に向かいました。
こじんまりとした、しかし、個人の博物館としてはとても立派な大きなビルのそれは、井の頭通りに
面し堂々としたものでした。 何かの催しがあったのか人の出入りが多かったですが、3階の
“古賀政男の世界”は、人影少なく静かでした。古賀政男が愛用したマンドリンやギター、作曲活動に
こもった書斎、燕尾服、靴など身近な展示の他、大衆音楽の粋が集められていました。
古賀政男音楽博物館 展示部分


企画展として、「日本歌めぐり⑤大阪」が開催されていて、こじんまりとした部屋は大阪づくしで
懐かしい思いでした。100曲以上もあるかと思う大阪の歌の中に、古賀政男作曲は3曲ありました。
服部良一などが草分けの感じでした。
我々が知る、有名な演歌の数々のほか、校歌や企業・団体の歌まで多くの歌を作曲されていたのですね。
歌めぐり、大阪編

関東地方だけ、小雨交じりのやや寒さを感じる一日でしたが、しっとりと、しかし力強い響きを
感じた一日となり、この後お茶して余韻を楽しみながらお別れとなりました。
古賀政男が在学中に発表した名曲・・ 作詞、作曲、歌
















