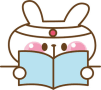今日は二十四節季の冬至です。 古い習わしでは、カボチャを食べてゆず湯に入る・・
などと言われますが、時代は変わりました。 でも、ゆず湯はほんのりといい香りがして、
ひと時穏やかな気分にさせてくれますね。 高校生は都大路を走ります。中山では有馬記念。
いよいよ今年も余すところわずかとなりました。
このところの文科省は失点が続いています。先の英語民間試験でも、地域の格差や経済的
視点から見送られましたが、今度は、読解力や表現力を判定するため国語、数学について
記述式問題を導入するとの方針が白紙に戻りました。
2013年から6年間にわたって検討・審議されてきた大学入試改革の2本柱がとん挫したこと
になります。
暗記主体の試験を見直し、要点をつかむ読解力や考える力など応用力を育む教育を目指し
た一つのターゲットとして、入試問題があると思いますから、この取り組みはしかるべきか
と納得しますが、その方法論が、今聞けばまったくお粗末極まりないのですね。このような
結論にたどり着くのに、なぜ 6年もの長い期間が必要だったのか疑問すら覚えます。
記述式は、最大120語程度の文章で回答するのだそうですが、50万人の回答を短期間のうち
に採点できるか? がポイントで、民間の教育会社がそれを請け負うとのことで、アルバイト
に採点をさせざるを得ないという、ズサン極まりないものだったのですね。 正確性、公平性
など入試の最重要事項が、一把ひとからげの “作業” とみなされたに等しいのです。
民間の教育会社からの提案がそのベース(リード)となって、延々と枝葉末節の議論ばかり
に時間が費やされ、本質的な議論のない結果であるとみなされ、まったくやりきれない思いです。
回答自体がマークシートや選択式であっても、読解力を問う問題は作成できるのではないか?
丸暗記による回答選びではなく、内容や状況などを読み取らなければ正解にたどり着け
ない・・ような問題で、ある程度代替えできるのではないか?
先に見送られた英語の民間検定の場合でも、民間検定は、自らの英語力を評価してもらい
たい人が進んで受けるというのが本来の趣旨で、これを一律パーに入試に取り込もうとする
安易な、あるいは企業寄りの発想があったのかもしれないとしたら、何をかいわんやです。

6年間も何をしていたのか! こんな連中が、多くのまじめな受験生を揺さぶっていると
したらお寒い限りです。