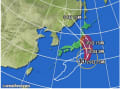死者の軍隊 中桐雅夫
俺は病人 俺のなかで
二つの世界が戦つている
俺の肉はシャベルで彫りかえされ
俺の骨はドリルで穴をあけられる
俺は病人 俺のなかで
祖先と相続人が対峙している
塵埃でできた俺のからだが
いつまでその緊張に堪えていられよう
二つの軍隊は
夜も眠らず 行進し 偵察する
俺の血と汗は
彼らの手旗信号に従つて流れる
俺は病人 俺のなかで
二つの世界が戦つている
俺の心臓は結滞し
肺は炎症を起している
俺は病人 俺のなかで
憎悪と愛が対峙している
彼らは俺の神経のはしばしに火をつけ
俺の血を燃えつきさす
この死者の軍隊
俺の骨と肉を舞台として
攻撃し 反撃する
この二つの 慈悲なき軍隊!
この詩は「荒地詩集1954」に収録されている。中桐雅夫35歳の詩である。1954年という時代、前年に朝鮮戦争が終結したが、その影響は大きかった。さらに東西冷戦か緊張を高めている時である。
1945年の終戦以降9年という時間を経ているが、緊張の続く世界情勢の中で、戦争の傷跡、その後の世界の緊張が「戦争」「軍隊」という言葉が詩人の頭の中で、思考するたびに湧き上がり、思考を中断し、戦争体験を呼び覚ます。これは多分の多くの国民に作用していたと思われる。ベトナム戦争に従軍させられた多くの米兵がその後の日常生活にその体験を引きづったように。あるいは旧大日本帝国の軍隊で視線を彷徨った日本人はさらに厳しく尾を引かざるを得なかったはずである。中桐雅夫という先端の知識人もその例外ではなかったはずである。戦争体験からの脱却は9年たっても執拗についてくる。そして世界の緊張関係がさらに個人の緊張を増幅する。
この詩を昔目にした時、分かりづらく理解できなかった。今もわからない。肉と骨、祖先と相続人、二つの軍隊、二つの世界、憎悪と愛、死者の軍隊、慈悲なき軍隊‥具体的荷イメージとして把握できない。二つの世界が一般的に東西冷戦の脾兪とは思えない。戦後の生活の中で、詩人の観念そのものが二項対立的に分裂しているのであろうか。そういってしまっても何かを言い当てたとはいえない。
判るのは軍隊に引きづられて血と汗を流させられた体験が9年たっても抜けきらないという体験の重みである。そしてそれからどのように再生しようともがいたか、そんな苦闘をさらに詩人がたどった道を追ってみたいという欲求を私にもたらす力が漂ってくる。
この詩を初めて読んた1986年8月からちょうど30年たった。今でもわからないままである。しかし戦争を引きずった詩人が何を伝えたかったか、考えさせられた30年でもある。
私の読解力の無さをさらけだすようだが、わからないまま取り上げてみた。
俺は病人 俺のなかで
二つの世界が戦つている
俺の肉はシャベルで彫りかえされ
俺の骨はドリルで穴をあけられる
俺は病人 俺のなかで
祖先と相続人が対峙している
塵埃でできた俺のからだが
いつまでその緊張に堪えていられよう
二つの軍隊は
夜も眠らず 行進し 偵察する
俺の血と汗は
彼らの手旗信号に従つて流れる
俺は病人 俺のなかで
二つの世界が戦つている
俺の心臓は結滞し
肺は炎症を起している
俺は病人 俺のなかで
憎悪と愛が対峙している
彼らは俺の神経のはしばしに火をつけ
俺の血を燃えつきさす
この死者の軍隊
俺の骨と肉を舞台として
攻撃し 反撃する
この二つの 慈悲なき軍隊!
この詩は「荒地詩集1954」に収録されている。中桐雅夫35歳の詩である。1954年という時代、前年に朝鮮戦争が終結したが、その影響は大きかった。さらに東西冷戦か緊張を高めている時である。
1945年の終戦以降9年という時間を経ているが、緊張の続く世界情勢の中で、戦争の傷跡、その後の世界の緊張が「戦争」「軍隊」という言葉が詩人の頭の中で、思考するたびに湧き上がり、思考を中断し、戦争体験を呼び覚ます。これは多分の多くの国民に作用していたと思われる。ベトナム戦争に従軍させられた多くの米兵がその後の日常生活にその体験を引きづったように。あるいは旧大日本帝国の軍隊で視線を彷徨った日本人はさらに厳しく尾を引かざるを得なかったはずである。中桐雅夫という先端の知識人もその例外ではなかったはずである。戦争体験からの脱却は9年たっても執拗についてくる。そして世界の緊張関係がさらに個人の緊張を増幅する。
この詩を昔目にした時、分かりづらく理解できなかった。今もわからない。肉と骨、祖先と相続人、二つの軍隊、二つの世界、憎悪と愛、死者の軍隊、慈悲なき軍隊‥具体的荷イメージとして把握できない。二つの世界が一般的に東西冷戦の脾兪とは思えない。戦後の生活の中で、詩人の観念そのものが二項対立的に分裂しているのであろうか。そういってしまっても何かを言い当てたとはいえない。
判るのは軍隊に引きづられて血と汗を流させられた体験が9年たっても抜けきらないという体験の重みである。そしてそれからどのように再生しようともがいたか、そんな苦闘をさらに詩人がたどった道を追ってみたいという欲求を私にもたらす力が漂ってくる。
この詩を初めて読んた1986年8月からちょうど30年たった。今でもわからないままである。しかし戦争を引きずった詩人が何を伝えたかったか、考えさせられた30年でもある。
私の読解力の無さをさらけだすようだが、わからないまま取り上げてみた。