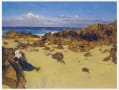「白のシンフォニー#1」(1862)

「白のシンフォニー#2:ホワイトガール」(1864)

「白のシンフォニー#3」(1865-67)

ホイッスラーという画家の名をはじめて知ったのは、1863年のマネの「草上の昼食」とともにサロンで落選の憂き目を見て物議を醸した「白のシンフォニー#1:ホワイト・ガール」の存在を知った時である。マネの絵は印象派の出発点として取り上げられることが多いが、この作品と画家についての情報は残念ながら目にすることは少なかった。
今回はこの「白のシンフォニー#1」(1862)は展示されていないが、「#2:ホワイトガール」(1864)と「#3」(1865-67)の2点が並んでいる。
当初は同じ時期の作品として見ていたが、解説を読むとホイッスラーの一連の作品の大きな曲がり角に位置する3点であることが記されている。なるほど「#1」は生々しい現実を象徴的な意匠で描かれている。白い百合、結っていない髪、白い部屋着等は当時のタブーに挑戦するようなスキャンダラスな絵画であったらしい。また白いカーテンを背景に白のグラデーションもまた技法的な挑戦であったらしい。そして当時心酔していたクールベの影響を強く示唆するものであるという。
「#2」はジャポニズム的な要素というよりもエキゾティズムとしての日本・東洋の調度品を配置している。陶器、漆器、団扇、前景にある一部だけ描かれた薄いピンクの花を配置した構図などがあげられる。クールベ的な世界からラファエル前派への傾斜をうかがわせるとのことである。
同時に横向きのモデルの顔は、鏡に映った顔とは物理的に整合性がとれない。物憂げな表情を鏡に映らせるということは多分モデルの内面を写し出しているという暗喩なのであろう。西洋絵画特有の手法のようだ。
「#1」と「#2」とでモデルと作者の関係が危機的になってきていることの暗示のように受け取れる。絵画に画家やモデルとの緊張関係、時間の累積を投影する意識を感じる。
「#3」は団扇と前景の一部だけ描かれた花、絨毯の紋様などに日本趣味が窺えるが、「#2」ほどのくどさはなく、日本的エキソティズムがジャポニズムとして画家の中で昇華されつつあることを推察させてくれる。日本的調度と構図が画面の中に違和感なく融け込んでいるように思える。さらにモデルの表情や象徴的な調度という暗喩からは抜け出し、色彩と構図、人物の配置の妙に力点が移っている。そのためにはソファーの背もたれの左側は消えており、背景の黒っぽい壁の色で顔と服の白が強調されているようだ。またソファーは奥行きが希薄で左での人物の姿勢も物理的にはちょっとあり得ない。二人のモデルはお互いに関係が希薄である。また頭の上の空間が極端に狭く、全体の空間に広がりがない。この絵から感じるのは人物と色彩との不思議なバランスである。
モデルでもあり愛人でもあったというジョーという女性の個性や感情は「#3」からは解説のとおり消失している。これが人物画として成功しているのかどうか、私にはわからないことがあるが、ラファエル前派の絵画ともまた違う側面のような気もする。
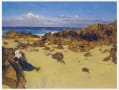
始めホイッスラーはクールベの写実主義=リアリスムに心酔していたということだが、確かに「ブルターニュの海岸(ひとり潮汐に)」(1861)などの作品では、海の波と空などにクールベを彷彿とさせるものがある。色彩の対比も鮮やかである。しかし一方で俯瞰的な構図などはどこか独特のこだわりが垣間見える。
1960年代から70年代前半にかけて盛んに日本の浮世絵の模写や日本や東洋の調度品の模写、絵画への取り込みを試みている。当初はエキゾティックに耳目を驚かすような作品などを盛んに試みているが、決して私たちを満足させるような作品ではない。ただ凡庸な画家が室内調度やジャポニズム的な雰囲気の追及に終わらせた試みとは違うのは、モネやゴッホなどのようにジャポニズムの刺激を独自の技法として昇華し得た画家の一人であったということであろう。
それは英国などヨーロッパの風景と浮世絵の風景を混在させようとしたのに始まり、結果としては、構図、淡い色調と微妙なグラデーションによる画面構成、俯瞰する視点、ルネッサンス以来の遠近法の再検討、平面的な画面構成、近景と遠景の混在、など独自の描法を獲得したように見えることではないだろうか。


端的な例として挙げられるのが、「艀」(1861)である。広重の「東海道五十三次見附天竜川図」(1833‐34)である。西洋絵画の伝統にはなかったと云われる画面からはみ出す近景などの大胆な構図を描かれた空間の広がりを暗示するものとして獲得している。


同時にこれらの試みと並行してホイッスラーがクールベ的画風からの転移を果たすきっかけとなったのが、「肌色と緑色の黄昏:バルパライソ」(1866)や「ノクターン:ソレント」(1866)の風景画であると思う。クールベの影響からの離脱、クールベが絡む自身の愛人との三角関係などから逃れるように南米へ出向き、自身の描法獲得となった作品と私には思える。
展示では前者を風景画の範疇に、後者をジャポニズムのコーナーに別々に展示している。解説で、前者は「自在な筆の動きと明るく鮮やかな色彩、精緻な描写」で「最も印象派的」とし、後者は「柔らかく滑らかな筆致が揺れながらカンヴァスを横切り」として対照的な作品として論じている。私にはよく理解できない解説である。
これは対照的な作品というよりも後年の「ノクターンシリーズ」の先駆けとして位置付けられるものと理解した。対象がより淡く海と空とがあいまいになり、そこに溶けていくような船と溶けていくことに抵抗するような微かな灯りに主題が映っていく流れを私は重視したいと感じた。
このふたつの作品からホイッスラーらしい画面がより色濃く展開していく記念碑的な作品だと感じている。
この海(水)と空に溶け込んでいくような風景と淡い色調は、それこそ広重などの浮世絵の風景画から援用した微妙なグラデーションにヒントを得たように思える。さらに先駆者ターナーの影響も私は読み取れるのではないだろうか。

人物画については「三人の女性:ピンクと灰色」(1868‐78)のような試行錯誤は続いているが、私は本質的にホイッスラーという画家は風景画が本領のような気がする。
この1860年代の試行錯誤と新しい表現様式を獲得して、魅力的な1870年代の諸作品が生まれてきたと理解したがどうであろうか。