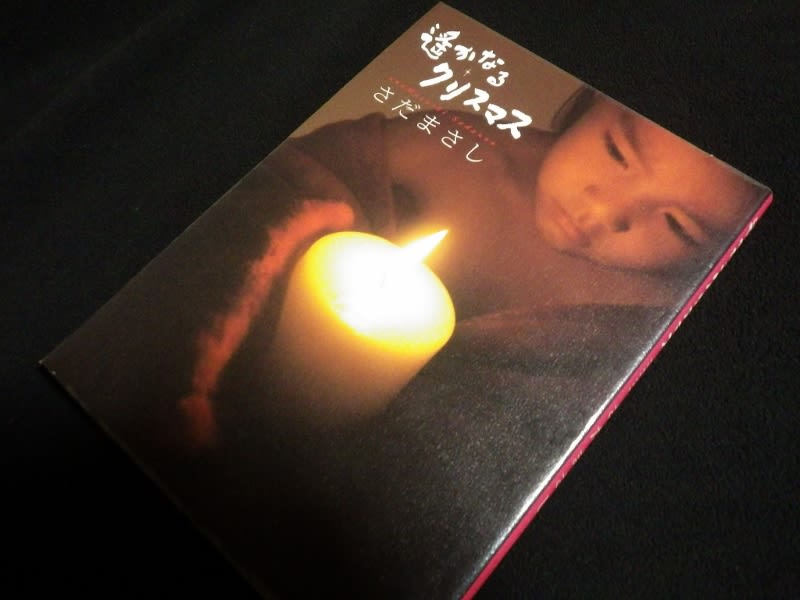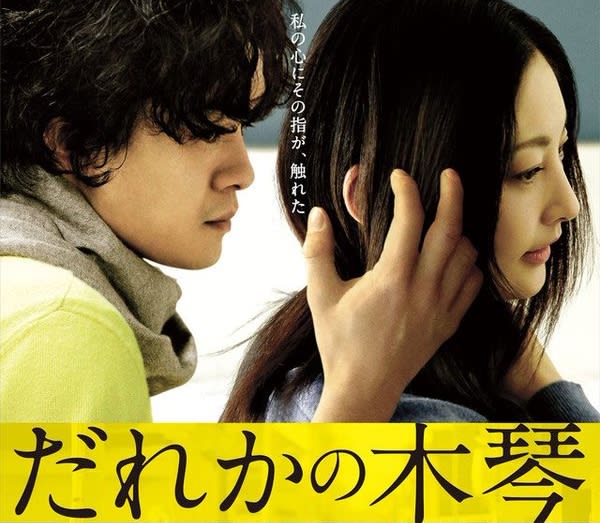ここ数年の私の山行日数は、
2011年は70日、
2012年は69日、
2013年は70日、
2014年は71日、
2015年は69日
と、推移しており、
そして、今年、
2016年は74日であった。
昨年より5日増えたが、
遠くの山へ行くことが少なくなり、
ホームマウンテンである天山や、
佐賀県内の山を主体とした山歩きとなった。
これは、
山岳会に所属していた時代を含め九州内の主だった山は . . . 本文を読む
12月25日に、
裏山の鬼ノ鼻山・聖岳で登り納めをした。
年末年始はずっと仕事をしている私としては、
早めに登り納めをして、
今年最後の公休日である今日(12月28日)は、
午前中は部屋の掃除をして、
午後からは図書館へ行ったり、映画を見に行ったりする筈であった。
だが、
午前中の掃除を終え、
玄関を出た時、天山が見えた。
朝は曇っていて、天山は中腹から上が見えない状態だったのだが、
昼近く . . . 本文を読む
この映画を見たいと思った理由は、三つ。
一つ目は、小松菜奈が出演していたから。
二つ目は、監督が三木孝浩だったから。
三つ目は、吉田智子が脚本を担当していたから。
小松菜奈を初めてスクリーンで見たのは、
『渇き。』(2014年6月27日公開)においてだった。
その後、
『近キョリ恋愛』(2014年10月11日公開)
『予告犯』(2015年6月6日公開)
『バクマン。』(2015年10月3日公 . . . 本文を読む
〈一週間後の今日は、元旦なんだな~〉
と思いつつ、
色々な用事を片付けていた日曜日の午後、
ぽっかりと3時間ほど自由な時間ができたので、
裏山である鬼ノ鼻山から聖岳へ縦走することにした。
おそらく、今年の登り納め……かな?
天ヶ瀬ダムのダム湖をパチリ。
振り返ると、棚田の向うに天山が見えた。
残っていた紅葉を見ながら高度を上げて行く。
こんな標識ができていた。
私がいつも歩くルー . . . 本文を読む
私が購読している地元紙では、
さだまさしの「風のうた」と題するエッセイが、
週一回ほどの割合で連載されている。
先日、さだまさしの絵本『遙かなるクリスマス』の誕生秘話ともいうべきものが載った。
さだまさしには『遙かなるクリスマス』という名曲があり、
その歌詞をもとに作られた絵本が、2004年12月に出版されている。
(2007年11月に文庫化されたが、現在はどちらも絶版状態のようである)
. . . 本文を読む
東陽一監督といえば、
私の青春時代にもっとも輝いていた監督で、
劇映画3作目の(キネマ旬報ベストワンとなった)傑作『サード』(1978年)で、
監督としての確たる地位を築き、
以降、
『もう頰づえはつかない』(1979年/主演・桃井かおり)
『四季・奈津子』(1980年/主演・烏丸せつこ)
『ラブレター』(1981年/主演・関根恵子)
『マノン』(1981年/主演・烏丸せつこ)
『ザ・レイプ』 . . . 本文を読む
土曜日から次女と孫たちが遊びに来ている。
日曜日の今日は、
まだ皆が寝ている間に天山へ朝駆け登山しようと思い、
早朝に車で家を出た。
我が町は霧がたちこめていた。
〈もしかすると雲海が見られるかもしれない……〉
そう思い、ワクワクしながら、登山口へと急いだのだった。
天川登山口に到着。
準備をし、軽くストレッチをして、登り始める。
12月15日に今年の初冠雪を記録した天山。
嬉しいことに . . . 本文を読む
西川美和監督は、私の好きな監督で、
新作は必ず見るようにしている。
『蛇イチゴ』(2002年)監督・脚本
『ゆれる』(2006年)監督・脚本
『ディア・ドクター』(2009年)監督・脚本
『夢売るふたり』(2012年)監督・脚本
と、西川美和監督作品は秀作揃い。
しかも、漫画や小説などの原作ものが全盛の邦画界で、
オリジナル脚本で勝負し続けている姿勢が素晴らしい。
そして、女優と見まがうばかり . . . 本文を読む
12月も中旬ともなれば、
各地で降雪、冠雪の話題が出始め、
日本列島は、もうすっかり冬モードになっているが、
どっこい、九州では、まだまだ秋の名残が見られるのだ。
佐賀県で、もっとも遅く秋を迎える金立山では、
今が紅葉の真っ盛り。
今日(12月11日)は、
当初は「曇り」の予報であったが、
急遽「晴れ」に変わった。
ならば金立山へ行かねばなるまい。(笑)
ということで、
日の出を待って、車で家 . . . 本文を読む
今年は『シン・ゴジラ』、『君の名は。』といった邦画が大ヒットし、
日本映画は安泰……と思いきや、
是枝裕和監督が、日本映画へ危機感を抱いているという。
「このままでは日本の映画は本当に終わってしまう」
と。
是枝裕和監督といえば、
国内でも数々の賞を受けているが、
海外の映画賞でも、多くの受賞歴がある。
『幻の光』(1995年)
バンクーバー映画祭 グランプリ
シカゴ映画祭 グランプリ
『 . . . 本文を読む