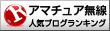今日は午前中から城山湖に行って、夕方17時の閉門まで過ごしました。
連休最終日、天気も良く、結構賑わっていました。無線を楽しんでいる車もチラホラ。
一日長袖で快適に過ごすことが出来ました。大抵は、暑いか寒いかですので、こんな快適な天候はこの時期だけ。非常に充実した一日でした。
さて、何をやってきたかというと、まずは最近愛用のスーパーアンテナ社のMP-1の改良シリーズ第2弾。
第1弾は純正ホイップよりうんと長いホイップへの交換。これでほぼ21MHzより上はフルサイズ動作となり、18MHz以下も全長が伸び、これまでより飛ぶアンテナとなりました。
今日の第2弾は、付属のユニバーサルマウント(クランプでアチコチに取り付ける、厚めのアルミ金具)に、カメラの三脚取り付け用の穴を空ける事。
ドリルと1/4インチネジのタップで出来上がりました。


三脚の雲台の上にMP-1を簡単に取り付ける事が出来るようになりました。
この穴、なんで最初から空けておいてくれないんでしょう、と思うくらいにFBになりました。
ラディックスの小型バンザイアンテナに空いているのを見たのがヒントになっています。
これで地上高が1m程度上がりました。
コイルはちょうど手をあげた位置にあり、調整に不自由はなく、フルサイズとなる28MHzなどにアンテナを縮める時も、三脚の雲台ならアンテナを90度倒すことも楽勝なので、簡単にロッドアンテナを縮めることが出来ます。
立ち姿もなかなか立派。かなり本格的なアンテナに仕上がって来ました。
今日はこれで T32C と21MHz、28MHzで交信できています。
午後はVCHアンテナを応用した電圧給電ノンラジアルアンテナの実験です。
これがもう大変苦労しまして、電圧給電にも使えるチューナー(CQ誌に2年くらい前に載っていたやつ)を使ったのですが、実はどんな長さのエレメントでも、アースなしでもチューナーの操作でSWRはあっさり落ちてしまうため、電圧給電になっているのかいないのか、さっぱりわからないのです。え?感電するかどうかで分かる??。超ハイインピーダンスとなるエレメントの長さが1/2λであることはわかるのですが、何かいい方法無いでしょうか。ローディングコイルが入っているとその位置、インダクタンスが正確に分かれば、計算でも出るのでしょうが、現場合わせではかなり難しいのです。
今回はアンテナのコイルのタップを一巻きづつ変え、チューナーでSWRを1ギリギリまで追い込み、その時のチューナーのコイルの位置、バリコンの位置を記録し、さらにその時のSWRのカーブを記録し続けることで、どんな特性が見えてくるのか、丹念に実験してみました。
その結果わかったのは、エレメントのコイルのある巻数の所では、SWRを落とすのにチューナーのコイルの巻数も一気にたくさん必要になり、バリコンの使用が僅かになるポイント、それが1点存在する、ということが見えてきました。この時のSWRの特性は、この時に限って急峻で、いかにも電圧給電アンテナという特性になります。
これよりもエレメントのコイルを多くしても少なくしても、チューナーのコイルの巻数はその半分以下で、バリコンの容量も増え、、SWRを1近くにまでチューナーで持って来た時のSWRのカーブは、ひじょ~~~~にブロード、緩やかになり、上下数MHz、SWRが低い状態になります。こうなるともう、どんなにコイルを足そうが減らそうが、ほとんどSWR最下点が動かなくなります。ちょっと不思議な状態です。
その一点の位置は以下のとおり、
14MHzでは、エレメントのペットボトルコイルは13巻きで、チューナーのコイル(トイレットペーパーの芯くらいの直径)は16巻き、
18MHzでは、エレメントのペットボトルコイルは8巻きで、チューナーのコイルは11巻き。
21MHzでは、エレメントのペットボトルコイルは6巻き(5巻きでもほぼ同様)、チューナーのコイルは9巻きとなりました。
コイルの巻数がこれより前後2巻き以上多い、又は少ない場合は、チューナーのコイルは4巻きくらいの位置が最もSWRが落ちるようになり、且つ特性が異常にブロードとなりました。
さて、この一点が急峻とは言え、バンド内はほぼカバーするくらいの帯域はあります。いたって普通の特性。逆にこの一点を逃すと異常なくらい帯域が広がってしまうのです。
アンテナ製作のポイントとしては、利得を取るか帯域を取るか、帯域をそこそこ維持しつつ利得を損なわない、などいろいろありますが、果たしてトライしているアンテナはどんな特性がベストなのでしょうか・・・。わかりません。
受信した感じは・・・今日は測定ばかりに費やしたのでまだわかりませんが、この1点に合わせた時だけ性能が上がることが分かればここを追求していけばいい、ということが言えるかなと思います。
今日はこれらの特性がやっと見えてきたところで時間切れ。引き続き来週日曜日に続きを実験してみようと思います。
今日は「実にアンテナと向き合う一日」となりました。
実験に協力していただいたローカル各局、また実験中に交信していただいた各局、ありがとうございました。