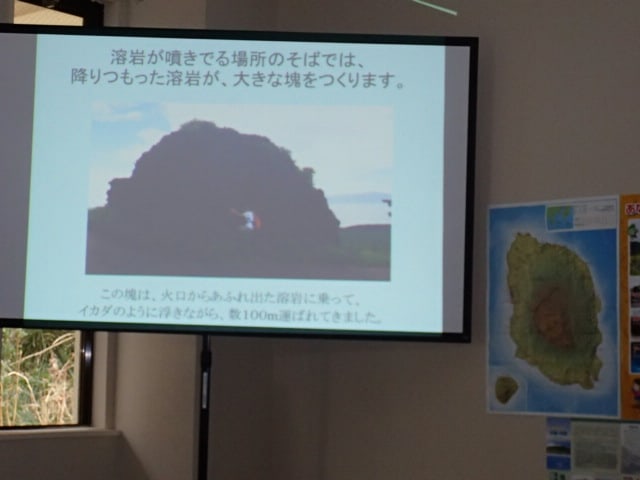一昨日の夜、1~2年ぶりに仲良しの友人と横浜で食事をしました。
その時、彼女が書いた「非売品の本」をもらいました。
それが,コレです。

「アカガシラカラスバトの棲む島で」
小笠原諸島にだけ棲むハトのことを、できる限り多くの人に知ってもらいたくてNPO小笠原自然文化研究所が発行したものだそうです。
本の中には、自然の状態でのアカガシラカラスバトの行動や暮らしぶりが書かれていて、とても面白く、夢中になって読みました。
名前のとおり、カラスのような黒い羽を持つハト“カラスバト”は、伊豆大島でも暮らしています。
こちらは今日、大島の動物園で撮影したカラスバト。

(なんだかこの子も、少し頭が赤っぽいような気がしますが…)
本には以下のようなことが書いてありました。(超、要約です)
アカガシラカラスバトはヒナを巣に残し、親鳥達が両方とも餌探しに出かけてしまう。
これは、地上のヒナを狙う外敵がいなかった小笠原ならでは、の習性。
それが人間が島に持ち込んだネコ達によって、数が激減し絶滅が心配されていた。
2008年1月、島内外から120名が集まり「絶滅を回避するため」に3日間話しあった。
その結果、野生化したネコの影響が一番大きいことがわかり、ネコを島外に出す取り組みをはじめた。
東京で引き取り手を捜し、多くの人達の協力で350頭のネコを島外に出した結果ハトが増えはじめた。
数の増加と共に、今まで1年に1回しか卵を生まなかった“つがい”が、何回か繰り返し卵を産みヒナを育てるようになった。
また、今までは単独かペアでしか見なかったハト達が、若い時は群れを作るようになった。
そして、ハト達は小笠原諸島の島から島へ、餌を求めて移動して暮らしていることがわかって来た。
本の最後のページの「謝辞」には、個人や団体の名前がいっぱい載っていて、人間の影響で減ってしまった鳥を元に戻すために、本当に沢山の人が協力したのだなぁ、と思いました。
最初にハトの暮らしや特徴が、わかりやすく紹介されているからこそ、人間との関わりを考えさせられる…とても素敵な本でした。
ぜひ、みんなに読んでほしい!
…でも残念なことにこの本、非売品なんですよね。
ぜひ是非、販売されることを祈りつつ、大島の風景の中に本をおいてみました。

海の見える大島の動物園に、アカガシラカラスバトの後ろ姿!(笑)
ところで、大島でカラスバトの密度が一番高い動物園の巨大ケージの中には、彼らの好物であるヤブツバキやスダジイなどが生えて(植えられて?)います。

今日は、ケージの中のヤブツバキの花がキレイに咲いていました。

カラスバトの水飲み場も、椿の花で彩られていいました。

小笠原とは、だいぶ違う風景ですが…
美味しい実が、いっぱい実るといいですね!

(カナ)
ところで最後に、またまたお知らせです。(最近このパターンが多い)
先日キャンプ下見にみえたホールアース自然学校の津田さんが担当するツアーが催行決定となり、ホームページにアップされました。私も1日、三原山ツアーを案内します。
その名も「ジオキャンプ!伊豆大島冒険学校~太平洋に浮かぶ島で過ごす5日間」
http://wens.gr.jp/individual/kids_family/izubou.html
案内の中に「キャンプというカタチで、子どもたちと一緒になって伊豆大島を応援しながら、自然の怖さと素晴らしさを、一緒に味わうキャンプにしたいと考えています。」という文章を見つけ、嬉しく思いました。
人と人とのつながりって、素晴らしい!
その時、彼女が書いた「非売品の本」をもらいました。
それが,コレです。

「アカガシラカラスバトの棲む島で」
小笠原諸島にだけ棲むハトのことを、できる限り多くの人に知ってもらいたくてNPO小笠原自然文化研究所が発行したものだそうです。
本の中には、自然の状態でのアカガシラカラスバトの行動や暮らしぶりが書かれていて、とても面白く、夢中になって読みました。
名前のとおり、カラスのような黒い羽を持つハト“カラスバト”は、伊豆大島でも暮らしています。
こちらは今日、大島の動物園で撮影したカラスバト。

(なんだかこの子も、少し頭が赤っぽいような気がしますが…)
本には以下のようなことが書いてありました。(超、要約です)
アカガシラカラスバトはヒナを巣に残し、親鳥達が両方とも餌探しに出かけてしまう。
これは、地上のヒナを狙う外敵がいなかった小笠原ならでは、の習性。
それが人間が島に持ち込んだネコ達によって、数が激減し絶滅が心配されていた。
2008年1月、島内外から120名が集まり「絶滅を回避するため」に3日間話しあった。
その結果、野生化したネコの影響が一番大きいことがわかり、ネコを島外に出す取り組みをはじめた。
東京で引き取り手を捜し、多くの人達の協力で350頭のネコを島外に出した結果ハトが増えはじめた。
数の増加と共に、今まで1年に1回しか卵を生まなかった“つがい”が、何回か繰り返し卵を産みヒナを育てるようになった。
また、今までは単独かペアでしか見なかったハト達が、若い時は群れを作るようになった。
そして、ハト達は小笠原諸島の島から島へ、餌を求めて移動して暮らしていることがわかって来た。
本の最後のページの「謝辞」には、個人や団体の名前がいっぱい載っていて、人間の影響で減ってしまった鳥を元に戻すために、本当に沢山の人が協力したのだなぁ、と思いました。
最初にハトの暮らしや特徴が、わかりやすく紹介されているからこそ、人間との関わりを考えさせられる…とても素敵な本でした。
ぜひ、みんなに読んでほしい!
…でも残念なことにこの本、非売品なんですよね。
ぜひ是非、販売されることを祈りつつ、大島の風景の中に本をおいてみました。

海の見える大島の動物園に、アカガシラカラスバトの後ろ姿!(笑)
ところで、大島でカラスバトの密度が一番高い動物園の巨大ケージの中には、彼らの好物であるヤブツバキやスダジイなどが生えて(植えられて?)います。

今日は、ケージの中のヤブツバキの花がキレイに咲いていました。

カラスバトの水飲み場も、椿の花で彩られていいました。

小笠原とは、だいぶ違う風景ですが…
美味しい実が、いっぱい実るといいですね!

(カナ)
ところで最後に、またまたお知らせです。(最近このパターンが多い)
先日キャンプ下見にみえたホールアース自然学校の津田さんが担当するツアーが催行決定となり、ホームページにアップされました。私も1日、三原山ツアーを案内します。
その名も「ジオキャンプ!伊豆大島冒険学校~太平洋に浮かぶ島で過ごす5日間」
http://wens.gr.jp/individual/kids_family/izubou.html
案内の中に「キャンプというカタチで、子どもたちと一緒になって伊豆大島を応援しながら、自然の怖さと素晴らしさを、一緒に味わうキャンプにしたいと考えています。」という文章を見つけ、嬉しく思いました。
人と人とのつながりって、素晴らしい!