今週は久々に勉強会で山を歩きました。
何気に冬も忙しいグローバルの面々、なかなか予定があわず、しばらくみんな揃っては歩きに行けなかったのですっ。
今回は久々に6人も集まってわいわい楽しく歩きました^^
それにしても見て下さい!

この勉強熱心なメンバーの姿!
これはふと目に入ってきた赤いコケのようなものに反応してみんなで覗きこんでいる所です。
気になったものは写真に残し、持ち帰って何かしらの方法で答えを探し(出来る限り)、またみんなにフィードバックする。
そんな形で少しずつでも確実にメンバーの情報量が増えていっています。
楽しみながら知識を広げていく。素敵な仲間ですね!!
お次はツアーです。
昨日は朝から激しく雨が降っていました。
でもゲストの方々は雨対策もとられていたのでツアー決行!
風雨を避けて樹海~笠松~神社のコースでいきました。
樹海を終えた頃にはもうお天気も回復しており、なかなか快適に過ごせました。

常緑のアオキが花芽をつけていました^^
クローズアップ♪

うーん、なんかちょっとフキノトウみたいで美味しそう^^?!
これから花を咲かせるのが楽しみですね!
神社では一本の杉が分かれて双子ちゃんになっていましたっ。

同じ場所でも行く時の視点で新しいものに出会えます。
同じ植物でも季節ごとに違う顔を見せてくれます。
お客様と一緒に、私もいつも新しい喜び^^
素敵な時間をありがとうございます!!
さて、今日も本当はツアーの予定でした。
しかし、チリの地震で日本にも津波の影響がありましたね。
予定されていたツアーもお客様が島に渡れず中止になってしまいました・・。
遠くから熱海まで足を運んでいただいたのにとても残念ですが、
これに懲りずにぜひまた企画して下さいね!
大きな地震がとても多いですが、どこの国で起きても対策をしっかりして少しでも被害が小さくいられると良いですね。
被災者の方のご冥福をお祈りします。
最後は今日のお月さま。

まるまると太ったお月さま^^
雨が空気を綺麗にしてくれたあとの三原の上空にぽっかりと浮かんでいました♪
(友)
何気に冬も忙しいグローバルの面々、なかなか予定があわず、しばらくみんな揃っては歩きに行けなかったのですっ。
今回は久々に6人も集まってわいわい楽しく歩きました^^
それにしても見て下さい!

この勉強熱心なメンバーの姿!
これはふと目に入ってきた赤いコケのようなものに反応してみんなで覗きこんでいる所です。
気になったものは写真に残し、持ち帰って何かしらの方法で答えを探し(出来る限り)、またみんなにフィードバックする。
そんな形で少しずつでも確実にメンバーの情報量が増えていっています。
楽しみながら知識を広げていく。素敵な仲間ですね!!
お次はツアーです。
昨日は朝から激しく雨が降っていました。
でもゲストの方々は雨対策もとられていたのでツアー決行!
風雨を避けて樹海~笠松~神社のコースでいきました。
樹海を終えた頃にはもうお天気も回復しており、なかなか快適に過ごせました。

常緑のアオキが花芽をつけていました^^
クローズアップ♪

うーん、なんかちょっとフキノトウみたいで美味しそう^^?!
これから花を咲かせるのが楽しみですね!
神社では一本の杉が分かれて双子ちゃんになっていましたっ。

同じ場所でも行く時の視点で新しいものに出会えます。
同じ植物でも季節ごとに違う顔を見せてくれます。
お客様と一緒に、私もいつも新しい喜び^^
素敵な時間をありがとうございます!!
さて、今日も本当はツアーの予定でした。
しかし、チリの地震で日本にも津波の影響がありましたね。
予定されていたツアーもお客様が島に渡れず中止になってしまいました・・。
遠くから熱海まで足を運んでいただいたのにとても残念ですが、
これに懲りずにぜひまた企画して下さいね!
大きな地震がとても多いですが、どこの国で起きても対策をしっかりして少しでも被害が小さくいられると良いですね。
被災者の方のご冥福をお祈りします。
最後は今日のお月さま。

まるまると太ったお月さま^^
雨が空気を綺麗にしてくれたあとの三原の上空にぽっかりと浮かんでいました♪
(友)































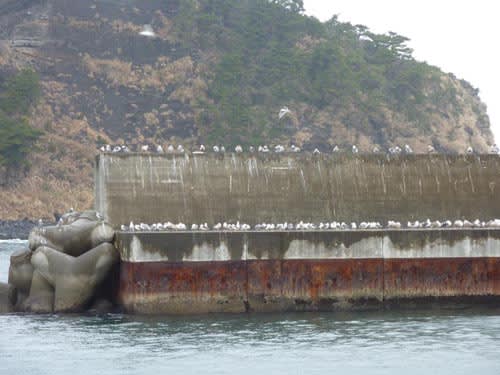





 や焼き物で楽しみ
や焼き物で楽しみ お腹も楽しいおしゃべりも存分に楽しみました)
お腹も楽しいおしゃべりも存分に楽しみました)



















