都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「紙で語る」 大倉集古館
大倉集古館(港区虎ノ門2-10-3 ホテルオークラ東京本館正門前)
「紙で語る」
8/1-10/12
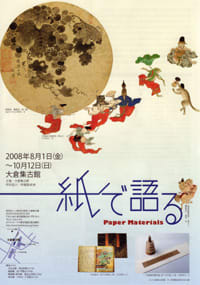
新たに寄託された特種製紙株式会社のコレクションを中心に、書、絵巻、草紙、屏風、それにかるたなど、紙にまつわる品々を概観します。大倉集古館での「紙で語る」展へ行ってきました。

経や書にまるで知識のない私にとって、一階部分、つまりは奈良時代の「大般若経」や南宋の「大唐三蔵取経詩話」などは、端的に表せば『読めない、分からない。』の極致のような展示です。とは言え、紺紙に金字の「訶梨帝母経」における金銀泥の説法図や、遊紙の文様も雅やかな藤原定信の「石山切 貫之集(下)」などは、その絵の美しさもあってか、思いのほかじっくりと見入ることが出来ました。また書関連でとりわけ興味深かったのは、奈良時代、4種の経典を小さな仏塔におさめた「百萬塔陀羅尼」です。これは764年、時の孝謙天皇が国の安寧を願って行ったという一種の国家プロジェクトですが、何と計約百万の経典を、木製の小塔とともに全国各地の寺院へ安置させたのだそうです。そのスケールに圧倒されました。

素人ながらも展示室二階は守備範囲内です。江戸時代の絵画がずらりと揃っています。ここではまず、布袋様の七変化ならぬ「布袋各様図巻」(松花堂昭乗)が何とも滑稽で楽しめました。布袋が様々なポーズをとる姿を、墨の濃淡だけで一つの巻物に描いています。またちらし表紙にも掲載された、英一蝶の「雑画帳」も見逃せません。こちらも同じく墨の表現だけで、豊かな実を付けたぶどうの房を巧みに示しています。輪郭線を用いず、余白を用いて一つ一つの実を描く様はまさに職人芸と言えるでしょう。またにょろにょろとのびるひげの部分もとても親しみが持てました。今回の一推しです。
ごく一部の作品に展示替えが予定されています。集古館ご自慢の一品、若冲の「乗興舟」は会期後半、9月23日からの公開です。
ロングランの展示です。10月12日まで開催されています。
「紙で語る」
8/1-10/12
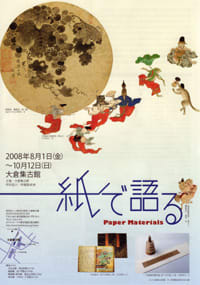
新たに寄託された特種製紙株式会社のコレクションを中心に、書、絵巻、草紙、屏風、それにかるたなど、紙にまつわる品々を概観します。大倉集古館での「紙で語る」展へ行ってきました。

経や書にまるで知識のない私にとって、一階部分、つまりは奈良時代の「大般若経」や南宋の「大唐三蔵取経詩話」などは、端的に表せば『読めない、分からない。』の極致のような展示です。とは言え、紺紙に金字の「訶梨帝母経」における金銀泥の説法図や、遊紙の文様も雅やかな藤原定信の「石山切 貫之集(下)」などは、その絵の美しさもあってか、思いのほかじっくりと見入ることが出来ました。また書関連でとりわけ興味深かったのは、奈良時代、4種の経典を小さな仏塔におさめた「百萬塔陀羅尼」です。これは764年、時の孝謙天皇が国の安寧を願って行ったという一種の国家プロジェクトですが、何と計約百万の経典を、木製の小塔とともに全国各地の寺院へ安置させたのだそうです。そのスケールに圧倒されました。

素人ながらも展示室二階は守備範囲内です。江戸時代の絵画がずらりと揃っています。ここではまず、布袋様の七変化ならぬ「布袋各様図巻」(松花堂昭乗)が何とも滑稽で楽しめました。布袋が様々なポーズをとる姿を、墨の濃淡だけで一つの巻物に描いています。またちらし表紙にも掲載された、英一蝶の「雑画帳」も見逃せません。こちらも同じく墨の表現だけで、豊かな実を付けたぶどうの房を巧みに示しています。輪郭線を用いず、余白を用いて一つ一つの実を描く様はまさに職人芸と言えるでしょう。またにょろにょろとのびるひげの部分もとても親しみが持てました。今回の一推しです。
ごく一部の作品に展示替えが予定されています。集古館ご自慢の一品、若冲の「乗興舟」は会期後半、9月23日からの公開です。
ロングランの展示です。10月12日まで開催されています。
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )










