都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「源氏物語の1000年」 横浜美術館
横浜美術館(横浜市西区みなとみらい3-4-1)
「源氏物語の1000年 - あこがれの王朝ロマン - 」
8/30-11/3
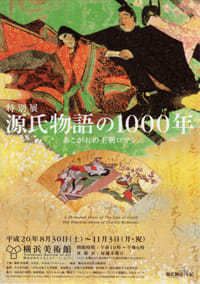
平安時代より現代に至るまでの『源氏絵』を一挙に総覧します。横浜美術館での「源氏物語の1000年」展へ行ってきました。

今年メモリアルを迎えた源氏の展覧会ということで、早速行かれた方も多いかとは思いますが、まず注意したいのは展示替えがいくつかあるということです。例えば五島美術館ご自慢の国宝「紫式部日記絵巻」や、又兵衛の魅力的な一作「和漢故事説話図」の公開は、既に会期一週間のみで終了しています。もちろん出品数全130点とのことで、見るべき作品は他にもあるわけですが、とりあえずは公式HP上の出品リスト(pdf)を確認された方が無難です。ちなみに館内の状況については、まだ早々だったからか、日曜日の午後にも関わらずかなり空いていました。今のところ、押し合いへし合いというのはなさそうです。
展示の終了した作品を挙げるのも気が引けますが、やはり圧巻なのは岩佐又兵衛の説話図より「須磨」と「浮舟」でした。登場人物の心情を風景へ映し込むことに長けた又兵衛のこと、この二作でもやはり浮舟や源氏の面持ちが見事な叙情性をもって表されています。「浮舟」における、薫と匂宮との間で揺れる彼女の心情は背後のしおれた柳の木にも示され、「須磨」では当地へ流された源氏の心の乱れが大嵐となって劇画的に描かれていました。それにしても後者では、源氏のいる庵の塀までが歪んでいます。彼の穏やかでない心中がそっくりそのまま、この歪んだ塀を通して嵐へとつながっているようでした。

伝宗達の「源氏物語図屏風」の「少女」と「初音」をはじめ、源氏物語を表した屏風にも見応えがありましたが、それよりも惹かれたのは、土佐派の絵師をはじめとする多くの画帳でした。土佐光吉の「源氏物語絵色紙帖」は、桃山期とは思えないほど保存状態も良い、実に美しい作品です。金砂子で飾られた画帳には、詞書とともに各場面の様子が細やかな描写で表されています。また秀忠の描いた「源氏物語画帳」も印象に残りました。自らの権力者の立場にありながら、武家にはない平安の雅やかな王朝文化に憧れた、彼の心中を探る一枚と言えるかもしれません。
主に江戸時代に流通した、源氏物語に関係する著作などの展示を過ぎると、今度は大和絵に表されたような優雅な源氏とは一変した、浮世絵における源氏の世界がいくつか紹介されています。そしてここではやはり月岡芳年の「田舎源氏」が一推しです。後景へ無限に広がるような広重風の荒野の中を、源氏が慌ただしく駆けていく様が描かれています。すすきの穂先、または股の下にのぞく衣装の紅色が、かの血みどろの芳年を思わせる鮮烈な赤に見えたのは私だけでしょうか。芳年の色は今作でも健在です。

近代以降の『源氏絵』も相当数出品されています。虚ろでかつ、まさに六条の呪いがそのまま乗り移ったかのような松園の「焔」は鮮烈な一枚です。代表作「花がたみ」の如く、モデルの鬼気迫る表情が絵の中に閉じ込められています。またその他、物語の作者である紫式部モチーフの作品もかなり多く目につきました。紫式部まで遊女に見立てた、川又常正の「見立紫式部図」のような珍品はともかくも、石山寺にて物語を執筆する紫式部の姿は昔から好まれたのでしょう。各絵師たちがどう彼女を描き分けたのかを見るのも、この展覧会の興味深いポイントの一つです。

一見地味ではありますが、梶田半古の「源氏物語図屏風」は意欲的な作品です。一般的にこの手の作品は、物語中の各場面を俯瞰的に描いていますが、梶田はそれを登場人物の視点によせて表しています。ようは有名な柏木の蹴鞠のシーンも、すだれ越しに覗き込む三宮の方から描かれているわけなのです。あたかも自分がその場面に入り込んだかのような錯覚さえしました。
決して難癖をつけるわけではありませんが、素人目からしても展示方法にやや拙さを感じる部分がありました。作品保護の観点とはいえ、随所で照明が暗すぎたり、また作品がケースに写り込んで見にくい箇所がいくつかあります。単眼鏡などがあると重宝しそうです。
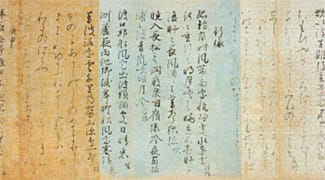
源氏のストーリーに疎い私でも十分に楽しめる展覧会でした。11月3日まで開催されています。
「源氏物語の1000年 - あこがれの王朝ロマン - 」
8/30-11/3
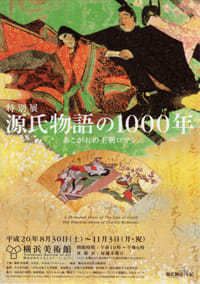
平安時代より現代に至るまでの『源氏絵』を一挙に総覧します。横浜美術館での「源氏物語の1000年」展へ行ってきました。

今年メモリアルを迎えた源氏の展覧会ということで、早速行かれた方も多いかとは思いますが、まず注意したいのは展示替えがいくつかあるということです。例えば五島美術館ご自慢の国宝「紫式部日記絵巻」や、又兵衛の魅力的な一作「和漢故事説話図」の公開は、既に会期一週間のみで終了しています。もちろん出品数全130点とのことで、見るべき作品は他にもあるわけですが、とりあえずは公式HP上の出品リスト(pdf)を確認された方が無難です。ちなみに館内の状況については、まだ早々だったからか、日曜日の午後にも関わらずかなり空いていました。今のところ、押し合いへし合いというのはなさそうです。
展示の終了した作品を挙げるのも気が引けますが、やはり圧巻なのは岩佐又兵衛の説話図より「須磨」と「浮舟」でした。登場人物の心情を風景へ映し込むことに長けた又兵衛のこと、この二作でもやはり浮舟や源氏の面持ちが見事な叙情性をもって表されています。「浮舟」における、薫と匂宮との間で揺れる彼女の心情は背後のしおれた柳の木にも示され、「須磨」では当地へ流された源氏の心の乱れが大嵐となって劇画的に描かれていました。それにしても後者では、源氏のいる庵の塀までが歪んでいます。彼の穏やかでない心中がそっくりそのまま、この歪んだ塀を通して嵐へとつながっているようでした。

伝宗達の「源氏物語図屏風」の「少女」と「初音」をはじめ、源氏物語を表した屏風にも見応えがありましたが、それよりも惹かれたのは、土佐派の絵師をはじめとする多くの画帳でした。土佐光吉の「源氏物語絵色紙帖」は、桃山期とは思えないほど保存状態も良い、実に美しい作品です。金砂子で飾られた画帳には、詞書とともに各場面の様子が細やかな描写で表されています。また秀忠の描いた「源氏物語画帳」も印象に残りました。自らの権力者の立場にありながら、武家にはない平安の雅やかな王朝文化に憧れた、彼の心中を探る一枚と言えるかもしれません。
主に江戸時代に流通した、源氏物語に関係する著作などの展示を過ぎると、今度は大和絵に表されたような優雅な源氏とは一変した、浮世絵における源氏の世界がいくつか紹介されています。そしてここではやはり月岡芳年の「田舎源氏」が一推しです。後景へ無限に広がるような広重風の荒野の中を、源氏が慌ただしく駆けていく様が描かれています。すすきの穂先、または股の下にのぞく衣装の紅色が、かの血みどろの芳年を思わせる鮮烈な赤に見えたのは私だけでしょうか。芳年の色は今作でも健在です。

近代以降の『源氏絵』も相当数出品されています。虚ろでかつ、まさに六条の呪いがそのまま乗り移ったかのような松園の「焔」は鮮烈な一枚です。代表作「花がたみ」の如く、モデルの鬼気迫る表情が絵の中に閉じ込められています。またその他、物語の作者である紫式部モチーフの作品もかなり多く目につきました。紫式部まで遊女に見立てた、川又常正の「見立紫式部図」のような珍品はともかくも、石山寺にて物語を執筆する紫式部の姿は昔から好まれたのでしょう。各絵師たちがどう彼女を描き分けたのかを見るのも、この展覧会の興味深いポイントの一つです。

一見地味ではありますが、梶田半古の「源氏物語図屏風」は意欲的な作品です。一般的にこの手の作品は、物語中の各場面を俯瞰的に描いていますが、梶田はそれを登場人物の視点によせて表しています。ようは有名な柏木の蹴鞠のシーンも、すだれ越しに覗き込む三宮の方から描かれているわけなのです。あたかも自分がその場面に入り込んだかのような錯覚さえしました。
決して難癖をつけるわけではありませんが、素人目からしても展示方法にやや拙さを感じる部分がありました。作品保護の観点とはいえ、随所で照明が暗すぎたり、また作品がケースに写り込んで見にくい箇所がいくつかあります。単眼鏡などがあると重宝しそうです。
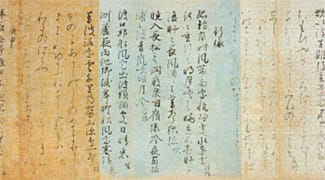
源氏のストーリーに疎い私でも十分に楽しめる展覧会でした。11月3日まで開催されています。
コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )










