都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
講演会:「知られざる山種コレクション」 山種美術館
山種美術館(渋谷区広尾3-12-36)
講演会「知られざる山種コレクション」
日時:7月24日 17:15~
講師:山下裕二氏(明治学院大学教授、山種美術館顧問)
山種美術館で開催中の「江戸絵画への視線」展に関連した山下先生の講演会、「知られざる山種コレクション」を聞いてきました。

大筋で内容は展示作品を一点一点スライドで解説していくものでしたが、早速以下に写真を交え、その様子を簡単にまとめてみます。(なお座席の関係で写真が山下先生のブロマイド状態になってしまいました。山下先生、申し訳ありません。)
~山種美術館と知られざる江戸絵画コレクション~
・茅場町から仮住まいの三番町、そしてこの広尾へと移転してきた山種美術館。
・近現代の日本美術コレクションに定評がある。
・開館一号展はすぐに速水御舟展と決まった。美術館の目玉はやはり速水御舟。
・しかしながら近現代日本美術以外にも知られざるコレクションがある。
・それが今回展観の江戸絵画コレクション=非常に高いクオリティ
・今回、茅場町時代以来、約20年ぶりとなる江戸絵画の展覧会である。(平成元年の「江戸の絵画展」以来。)
・出品にあたっては作品を改めて調査した。(また前回の浮世絵に関しても改めて内容を精査している。特に写楽の作品は重要。)
~琳派の諸作品について~
【宗達は野蛮なデザイナー】

「四季草花下絵和歌短冊帖」俵屋宗達絵 本阿弥光悦書(17世紀)
・短冊帖の上に金銀泥をあしらった作品。
・銀は黒く焼けてしまう傾向があるが、この作品に関してはむしろ良い感じの焼け方をしている。
・保存状態は超一級。
・光の当たり方によって輝きが変化していく様に注目して欲しい。
・短冊と言う細長いフォーマットを逆手にトリミングの妙味で魅せる作品。
・小さな画面にも関わらず大きな世界を作っている
・空間にモチーフを収めるのではなく、あたかもそれを鉈でぶった切るかのように世界をつくる。
【宗達=鉈、光琳=包丁、抱一=かみそり、其一=メス】

「新古今集鹿下絵和歌巻断簡」俵屋宗達絵 本阿弥光悦書(17世紀)
・元々は20m近くある作品。その巻頭部分を山種美術館が所有している。
・後半はシアトル美術館が所蔵。以前、サントリーの展覧会で展示された。
・表具も重要。細かな刺繍の入った着物を転用したのではないか。
・上下空間をぶったぎる宗達の腕力を余すことなく楽しめる名品。
・宗達=鉈、光琳=包丁、抱一=かみそり、其一=メス、とは言えないだろうか。
【槙楓図で追う琳派の系譜】

「槙楓図」伝俵屋宗達(17世紀)
・保存に関してはあまりよくない。補彩もある。
・宗達オリジナルかどうか意見が分かれる。ただし同時代の宗達に近い者の作品であることは間違いない。
・直立する幹をうねる幹の対比などに独特の魅力がある。オリジナルであるかどうかは問題ではない。
・琳派の系譜にとって重要な作品。光琳に同じ作品がある。おそらく光琳はこの作品を見て描いた。(=槙楓図屏風)
【照明の効果~巧みな奥行き感】

「秋草鶉図」酒井抱一(19世紀)
・美術館創設者、山崎種二が所有する以前は、横浜の原三渓が所有していた。抱一の名品。
・原が当時、インドの詩人タゴールにこの屏風を見せ、「金地に黒い柿の種の形をしたものを武蔵野の月だ。」と説明しても理解されなかったという。
・図版ではフラットな空間構成にも見えるが、実物には奥行きがある。
・土佐派風の秋草と銀の変色した黒い月のコントラスト。
・今回の展示では照明も工夫している。LEDで下からの光を強調することで美しい色味を出すことに成功した。
・そもそも江戸時代には上からの照明はなく、ロウソクなどの下からの明かりが殆どだった。
【山崎種二の原点は抱一】
「菊小禽図」/「飛雪白鷺図」酒井抱一(1823-28年頃)
・いわゆる抱一の十二ヶ月花鳥図と呼ばれるシリーズのうちの2点。全点揃いものでは三の丸尚蔵館の他、プライスコレクションなどが有名。
・菊は9月、飛雪は11月を表している。

「十月(柿・目白)」酒井抱一(三の丸尚蔵館蔵。本展非出品。)
・山崎種二のコレクション原体験は抱一。主人に赤い柿の描かれた抱一の絵を見せてもらったことに感銘し、絵画のコレクションをはじめた。
・その柿の絵を思わせるのがこの「十月」。おそらくこの作品に近いものを見たのではないか。
【抱一と若冲】

「白梅図」酒井抱一(19世紀)
・梅の枝が複雑に絡み合う作品。
・若冲の梅の絵を抱一は見ていたのではないか。バーク・コレクションの「月下白梅図」との類似性。
【光甫から酒井鶯浦】
「白藤・紅白蓮・夕もみぢ図」酒井鶯浦(19世紀)
・20年前は本阿弥光甫の作品とされていた作品。今回の調査で抱一一門の鶯浦の作品だと判明した。
・落款が押したものではなく書いてある。つまりは光甫の描いた作を誰かが写したということだ。
~岩佐又兵衛の「官女観菊図」について~
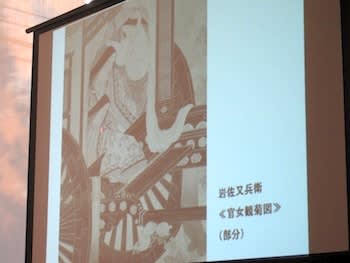
・辻惟雄氏の「奇想の系譜」における原点となる作品。人気こそ若冲に落ちるが、むしろ真価はこれから認知されるだろう。
・特定の場面を描いたわけではない。(伊勢か源氏の特定のシーンではない。)
・ともかくもの凄いのは髪の毛に対する異常な執着。非常に細かに描かれている。
・母を信長に殺された又兵衛は、マザコン的な女性像への追求をやめることがなかった。
・この作品にもまだ見ぬ母の幻影が示されている。
・頬と唇の部分に仄かな朱が入っていることにも注目してほしい。また画面のあちこちに金泥も入っている。
・本作は「金谷屏風」を切り取ったもの。左から二番目のシーンがこの作品。他は散逸しているものもある。
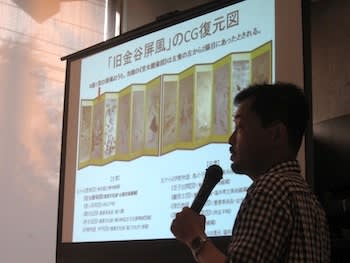
~文人画、またその他の作品について~
「指頭山水図」池大雅(1745年)
・指に墨を付けて描く技法を用いた作品。パフォーマンス的に描いたのではないか。
・池大雅は天才少年。三歳の時の書などが残っている。
「久能山真景図」椿椿山(1837年)
・渡辺華山の弟子の椿椿山の描いた久能山の実景。真景図は比較的ランクが低いとされてきた文人画の中でも高く評価されていた。
・中央に小さな人物が描き込まれていることにも注意して欲しい。

「唐子遊び図」伝長沢芦雪(18世紀)
・言わば問題作。一度「伝」がとられたこともあったが、今回見ることで改めて「伝」を付けた。
・芦雪の師、応挙の作を踏襲して描いたとされる作品。芦雪にしてはアクが強くないが絵自体は良い。
・展示することで研究者の議論を呼べばと思っている。
~まとめ・「江戸絵画への視線」とは~

「名樹散椿」速水御舟(1929年)
・御舟が琳派を意識して描いた作品。今回の展示ではそれをあえて最後に持ってきていた。
・近代絵画から琳派を意識して見て欲しい。
・つまり「視線」とは、現代に生きる我々と、御舟らといった近代の画家がどのように江戸絵画を見たのかという、二重の意味で名付けられたものだ。
時間の関係から前半の琳派を過ぎるとやや駆け足での解説となりましたが、いつもの山下先生らしい熱の入ったトークで楽しむことが出来ました。

ところで冒頭、山下先生も触れておられていましたが、江戸絵画の次は開館一周年を記念した「日本画と洋画のはざまで」という展覧会が予定されています。東近美所蔵の安井曾太郎の「芙蓉」などと、山種美術館の日本画の名品を相互に比較し、その間を追っていくという意欲的な内容になるそうです。こちらもまた楽しみです。
なお「江戸絵画への視線」展の私の感想については昨日のエントリにまとめてあります。
「江戸絵画への視線」 山種美術館(拙ブログ)
「江戸絵画への視線」展は9月5日まで開催されています。
講演会「知られざる山種コレクション」
日時:7月24日 17:15~
講師:山下裕二氏(明治学院大学教授、山種美術館顧問)
山種美術館で開催中の「江戸絵画への視線」展に関連した山下先生の講演会、「知られざる山種コレクション」を聞いてきました。

大筋で内容は展示作品を一点一点スライドで解説していくものでしたが、早速以下に写真を交え、その様子を簡単にまとめてみます。(なお座席の関係で写真が山下先生のブロマイド状態になってしまいました。山下先生、申し訳ありません。)
~山種美術館と知られざる江戸絵画コレクション~
・茅場町から仮住まいの三番町、そしてこの広尾へと移転してきた山種美術館。
・近現代の日本美術コレクションに定評がある。
・開館一号展はすぐに速水御舟展と決まった。美術館の目玉はやはり速水御舟。
・しかしながら近現代日本美術以外にも知られざるコレクションがある。
・それが今回展観の江戸絵画コレクション=非常に高いクオリティ
・今回、茅場町時代以来、約20年ぶりとなる江戸絵画の展覧会である。(平成元年の「江戸の絵画展」以来。)
・出品にあたっては作品を改めて調査した。(また前回の浮世絵に関しても改めて内容を精査している。特に写楽の作品は重要。)
~琳派の諸作品について~
【宗達は野蛮なデザイナー】

「四季草花下絵和歌短冊帖」俵屋宗達絵 本阿弥光悦書(17世紀)
・短冊帖の上に金銀泥をあしらった作品。
・銀は黒く焼けてしまう傾向があるが、この作品に関してはむしろ良い感じの焼け方をしている。
・保存状態は超一級。
・光の当たり方によって輝きが変化していく様に注目して欲しい。
・短冊と言う細長いフォーマットを逆手にトリミングの妙味で魅せる作品。
・小さな画面にも関わらず大きな世界を作っている
・空間にモチーフを収めるのではなく、あたかもそれを鉈でぶった切るかのように世界をつくる。
【宗達=鉈、光琳=包丁、抱一=かみそり、其一=メス】

「新古今集鹿下絵和歌巻断簡」俵屋宗達絵 本阿弥光悦書(17世紀)
・元々は20m近くある作品。その巻頭部分を山種美術館が所有している。
・後半はシアトル美術館が所蔵。以前、サントリーの展覧会で展示された。
・表具も重要。細かな刺繍の入った着物を転用したのではないか。
・上下空間をぶったぎる宗達の腕力を余すことなく楽しめる名品。
・宗達=鉈、光琳=包丁、抱一=かみそり、其一=メス、とは言えないだろうか。
【槙楓図で追う琳派の系譜】

「槙楓図」伝俵屋宗達(17世紀)
・保存に関してはあまりよくない。補彩もある。
・宗達オリジナルかどうか意見が分かれる。ただし同時代の宗達に近い者の作品であることは間違いない。
・直立する幹をうねる幹の対比などに独特の魅力がある。オリジナルであるかどうかは問題ではない。
・琳派の系譜にとって重要な作品。光琳に同じ作品がある。おそらく光琳はこの作品を見て描いた。(=槙楓図屏風)
【照明の効果~巧みな奥行き感】

「秋草鶉図」酒井抱一(19世紀)
・美術館創設者、山崎種二が所有する以前は、横浜の原三渓が所有していた。抱一の名品。
・原が当時、インドの詩人タゴールにこの屏風を見せ、「金地に黒い柿の種の形をしたものを武蔵野の月だ。」と説明しても理解されなかったという。
・図版ではフラットな空間構成にも見えるが、実物には奥行きがある。
・土佐派風の秋草と銀の変色した黒い月のコントラスト。
・今回の展示では照明も工夫している。LEDで下からの光を強調することで美しい色味を出すことに成功した。
・そもそも江戸時代には上からの照明はなく、ロウソクなどの下からの明かりが殆どだった。
【山崎種二の原点は抱一】
「菊小禽図」/「飛雪白鷺図」酒井抱一(1823-28年頃)
・いわゆる抱一の十二ヶ月花鳥図と呼ばれるシリーズのうちの2点。全点揃いものでは三の丸尚蔵館の他、プライスコレクションなどが有名。
・菊は9月、飛雪は11月を表している。

「十月(柿・目白)」酒井抱一(三の丸尚蔵館蔵。本展非出品。)
・山崎種二のコレクション原体験は抱一。主人に赤い柿の描かれた抱一の絵を見せてもらったことに感銘し、絵画のコレクションをはじめた。
・その柿の絵を思わせるのがこの「十月」。おそらくこの作品に近いものを見たのではないか。
【抱一と若冲】

「白梅図」酒井抱一(19世紀)
・梅の枝が複雑に絡み合う作品。
・若冲の梅の絵を抱一は見ていたのではないか。バーク・コレクションの「月下白梅図」との類似性。
【光甫から酒井鶯浦】
「白藤・紅白蓮・夕もみぢ図」酒井鶯浦(19世紀)
・20年前は本阿弥光甫の作品とされていた作品。今回の調査で抱一一門の鶯浦の作品だと判明した。
・落款が押したものではなく書いてある。つまりは光甫の描いた作を誰かが写したということだ。
~岩佐又兵衛の「官女観菊図」について~
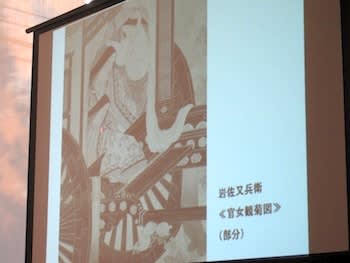
・辻惟雄氏の「奇想の系譜」における原点となる作品。人気こそ若冲に落ちるが、むしろ真価はこれから認知されるだろう。
・特定の場面を描いたわけではない。(伊勢か源氏の特定のシーンではない。)
・ともかくもの凄いのは髪の毛に対する異常な執着。非常に細かに描かれている。
・母を信長に殺された又兵衛は、マザコン的な女性像への追求をやめることがなかった。
・この作品にもまだ見ぬ母の幻影が示されている。
・頬と唇の部分に仄かな朱が入っていることにも注目してほしい。また画面のあちこちに金泥も入っている。
・本作は「金谷屏風」を切り取ったもの。左から二番目のシーンがこの作品。他は散逸しているものもある。
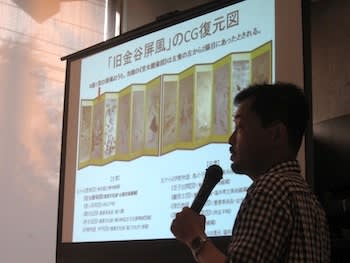
~文人画、またその他の作品について~
「指頭山水図」池大雅(1745年)
・指に墨を付けて描く技法を用いた作品。パフォーマンス的に描いたのではないか。
・池大雅は天才少年。三歳の時の書などが残っている。
「久能山真景図」椿椿山(1837年)
・渡辺華山の弟子の椿椿山の描いた久能山の実景。真景図は比較的ランクが低いとされてきた文人画の中でも高く評価されていた。
・中央に小さな人物が描き込まれていることにも注意して欲しい。

「唐子遊び図」伝長沢芦雪(18世紀)
・言わば問題作。一度「伝」がとられたこともあったが、今回見ることで改めて「伝」を付けた。
・芦雪の師、応挙の作を踏襲して描いたとされる作品。芦雪にしてはアクが強くないが絵自体は良い。
・展示することで研究者の議論を呼べばと思っている。
~まとめ・「江戸絵画への視線」とは~

「名樹散椿」速水御舟(1929年)
・御舟が琳派を意識して描いた作品。今回の展示ではそれをあえて最後に持ってきていた。
・近代絵画から琳派を意識して見て欲しい。
・つまり「視線」とは、現代に生きる我々と、御舟らといった近代の画家がどのように江戸絵画を見たのかという、二重の意味で名付けられたものだ。
時間の関係から前半の琳派を過ぎるとやや駆け足での解説となりましたが、いつもの山下先生らしい熱の入ったトークで楽しむことが出来ました。

ところで冒頭、山下先生も触れておられていましたが、江戸絵画の次は開館一周年を記念した「日本画と洋画のはざまで」という展覧会が予定されています。東近美所蔵の安井曾太郎の「芙蓉」などと、山種美術館の日本画の名品を相互に比較し、その間を追っていくという意欲的な内容になるそうです。こちらもまた楽しみです。
なお「江戸絵画への視線」展の私の感想については昨日のエントリにまとめてあります。
「江戸絵画への視線」 山種美術館(拙ブログ)
「江戸絵画への視線」展は9月5日まで開催されています。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )










