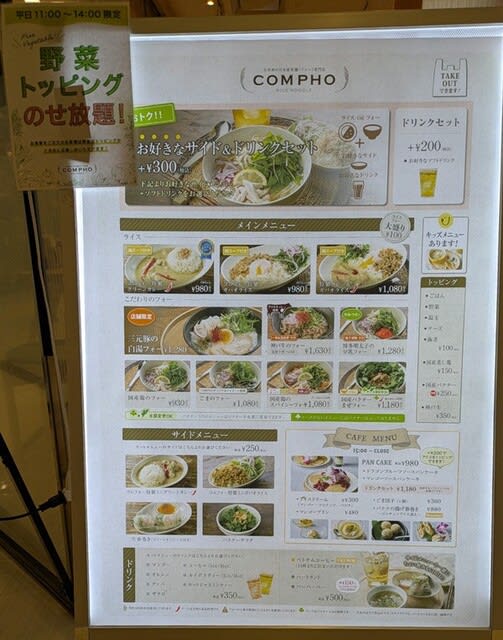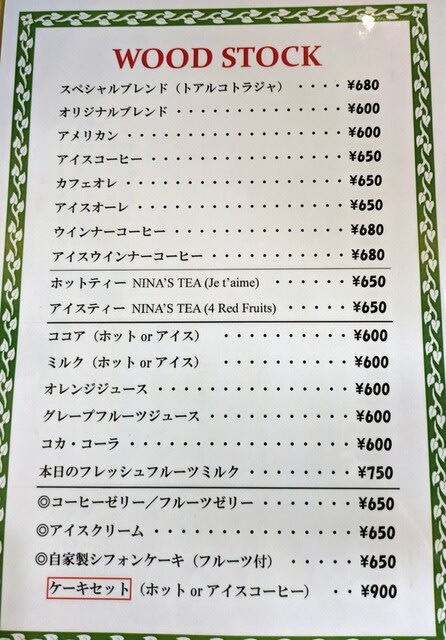南町苗木畑公園を北側に抜け、吾妻通りを横切り、さらに北の五日市街道を東に150mほど行くと、「西高井戸松庵稲荷神社」がある。



御祭神は受持命(うけもちのみこと)
松庵村は万治年間(1658~1660)に萩野松庵という医者が開いたと伝えられている。境内入口に元禄三年(1690)11月、同6年の二基の塔があり、前者に「武州野方領松庵新田」と刻まれている。
この神社は明治維新の際廃寺となった円光寺の境内に松庵村内鎮守として創建され、昭和9年に松庵村の鎮守と中高井戸村の鎮守を合併して西高井戸松庵神社と称し、社殿を改築した。
社前の五日市街道は江戸時代には「青梅街道脇道」と呼ばれ、木炭など生活物資の輸送に大きな役割を果たした。
近年、町名変更により西高井戸の地名が失われたので、神前に社号標を建立して由来を記した。
昔、当稲荷神社の西側に円光寺と言う寺があり、大きな築山があった。 狐が穴を掘って小狐を育てていたが、寺が廃寺となり、明治30年頃、築山を取り去ったので、親狐は子狐と別れる悲しみのあまり、前足をくわえたままの姿で拝殿の床下から発見された。昭和36年末社を建て、古来からお稲荷様のお使い姫と言い伝えられるこのお狐様をおさめてお祀りしている。
現在このミイラは鳥居をくぐって左手にある小さな祠(ほこら/し)に安置されている。ミイラは前足を口にくわえた状態のまま真綿の上に置かれているが、その姿を見ることはできない。この祠の前には、奉納された大小さまざまな狐の置物がたくさん並べられている。

神社北側には明治初年に廃寺となった(*)円光寺の住職の墓が隣接している。

中央の五輪塔は、地元の人々が、歴代住職の霊を慰め、手厚く供養するために昭和40年にこの墓地を整備したてた供養塔である。

経緯を記した看板

通り過ぎてしまうようなお稲荷様にも、調べてみると、オモロイ?話があるのだ。
「江戸紫染め」
元禄・宝永(1688~1711)のころ、松庵新田の豪農・仙蔵(のち杉田仙蔵)は、京都智積院の僧・円光の指導により、苦労の末「江戸紫染め」を完成させ、その子が広め、栄えた。円光寺は、仙蔵が建立したとも、円光が仙蔵の菩提を弔い、仙蔵が生前大切にしていた馬頭観音を本尊として建立したものともいわれる。馬頭観音は現在、宮前三丁目の慈宏寺(じこうじ)の写経堂に安置されている。
*廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)
廃仏毀釈は、明治維新政府の神道国教化政策に基づいて行われた仏教の弾圧運動。
明治元年(1868年)3月に「神仏分離令」が公布され、神社から仏教的な要素を排除し、1870年、大教宣布の詔を出し、伊勢神宮を頂点として、全国の神社を序列化する神社制度が整えられた。
これを受けて、長年仏教に圧迫されてきたと考える神職者たちによって全国的に廃仏運動が起こされ、激化し、神官、群衆が寺を襲って仏像や仏具などが破壊され、廃寺となった寺院も多い。明治4年頃にはほぼ終息したが、寺院の被害は大きかった。