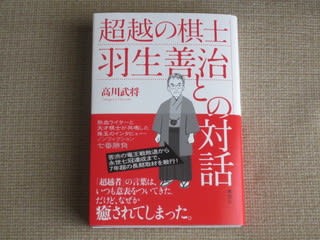高川武将 2018年9月 講談社
おもしろそうだと思って、10月ころに買ってたんだけど、先週になってやっと読んだ。
そしたら、竜王戦で負けて羽生さんは無冠になってしまったというタイミングにあたっちゃった、なんてこった、てっきりタイトル通算100期達成だと思ったのに。
たまたま、本書の終盤2016年6月のインタビューでも、
>たとえば、保持しているタイトルがなくなるのは、引き際を考えるタイミングになりますか。(p.358)
なんて問いがあったけど、どうなんだろうね。
本書は2010年から2016年にかけての7回のロングインタビューを主に、2017年と2018年はじめの2回が加わってる構成だが、現在の将棋について羽生さんは、2017年に
>やっぱり、現代の将棋にまだ自分自身がきちんと対応できていない、ということだと思っています。(p.28)
なんて第一人者にしてはえらい謙虚過ぎるようなことを言ってる。ところが、2010年の時点でも、
>だから、最先端の将棋を研究するのは大前提として、さらにその上で何をするか考えなくてはいけないんです(p.40)
と情報が多くて研究が盛んな時代についてくことの大変さを語ってて、この2010年代ずっと危機感もってトップにいたんだってわかる。
羽生さんの若いころからの努力のしかたを、まわりのイメージするスマートなデータ駆使とか、そんなんぢゃなかったってあたりを
>彼らは根性の形を変えたんです。根性の表現方法を変えた。(p.264)
って島研の主宰者だった島九段が明かしてくれている。
羽生さんの姿勢って、自分を客観視するというか、メタレベルにたてるところがすばらしいってのは、今までも何かにつけて感じてたんだけど、本書のなかでも、いや、そこまで言う、って驚かされるのがいくつもある。
>でも、モチベーションやテンションに関しては、どうにもならないところもあるんじゃないですかね。一年を通してでも、一日単位でも、そう思います。(p.144)
とかってのもそうだけど、そこでふつうはどうにかしようとするもんだろうに、羽生さんは自分で調整できないって割り切っちゃう。
あと、いくらメタレベルったって、自身の対局について、
>自分が予想しないドラマを対局しながら観ていくという感覚は、やっぱりありますね。うん。どうせ観るなら、つまらないドラマよりも、面白いドラマを観たほうがいいので(p.114)
とまで言うのは、すごい。プレイすることを試合を楽しみます、なんて言うアスリートはいるけど、ちょっと次元がちがうような。
本書全般を通じて、何を目標とするかとか、何のためにやるかとかって問いに、羽生さんはあっさりと無い、っつーか考えない、みたいな答えを繰り返す。
めんどくさくて言ってんぢゃなくて、ホントにそう思ってる、なんかホントそこ超越してるって感じ。
考えてもわからないもの、考えたってしかたないことは、考えない、そういうスタンスが、すごい。
でも、きわめつけは、この激動の時代に将棋界の第一人者として自身の役割はと問われたのに対し、
>役割ですか? 役割なんて、あるんですかねぇ……(略)役割はないですよ。自分のできることをやっていく、ということですね(p.295)
って答えてる、これには参った。そうかあ、そぉなんだー。
どうでもいいけど、著者は羽生さんにインタビューすると、なんか癒しを感じてしまうと言ってるんだけど、そのへんのとこ、インタビューの模様を、「うーん、うーん」「ええ、ええ」「はい、はい」「ハハッ、ハハッ(笑い声)」って羽生さんの放つ間を省略編集せずに活字にしてあるんで、こっちも読んでてあの独特の話し方を思い出させられるとこがよかったりする。
序章 7年目のカプチーノ
第一局 私、完璧主義じゃないんです
渡辺明――「この人、不思議だな」と思うときがある
第二局 闘うものは何もない
久保利明――羽生さんは本当に楽しんでいた
第三局 勝ちに行くとき、隙が生まれる
谷川浩司――嫉妬と恐怖心を乗り越えて
第四局 考えてもしようがないっしょ
桜井章一――羽生善治が歩く「獣道」
第五局 コンピュータにできるなら人間だって
島朗――羽生将棋の本質はど根性だ
第六局 人間に役割なんてあるんですか?
森内俊之――僕を育ててくれた理想のチャンピオン
第七局 忘れることが大事です
終章 死ぬまで? そういうものですよね
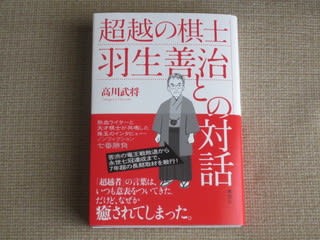
おもしろそうだと思って、10月ころに買ってたんだけど、先週になってやっと読んだ。
そしたら、竜王戦で負けて羽生さんは無冠になってしまったというタイミングにあたっちゃった、なんてこった、てっきりタイトル通算100期達成だと思ったのに。
たまたま、本書の終盤2016年6月のインタビューでも、
>たとえば、保持しているタイトルがなくなるのは、引き際を考えるタイミングになりますか。(p.358)
なんて問いがあったけど、どうなんだろうね。
本書は2010年から2016年にかけての7回のロングインタビューを主に、2017年と2018年はじめの2回が加わってる構成だが、現在の将棋について羽生さんは、2017年に
>やっぱり、現代の将棋にまだ自分自身がきちんと対応できていない、ということだと思っています。(p.28)
なんて第一人者にしてはえらい謙虚過ぎるようなことを言ってる。ところが、2010年の時点でも、
>だから、最先端の将棋を研究するのは大前提として、さらにその上で何をするか考えなくてはいけないんです(p.40)
と情報が多くて研究が盛んな時代についてくことの大変さを語ってて、この2010年代ずっと危機感もってトップにいたんだってわかる。
羽生さんの若いころからの努力のしかたを、まわりのイメージするスマートなデータ駆使とか、そんなんぢゃなかったってあたりを
>彼らは根性の形を変えたんです。根性の表現方法を変えた。(p.264)
って島研の主宰者だった島九段が明かしてくれている。
羽生さんの姿勢って、自分を客観視するというか、メタレベルにたてるところがすばらしいってのは、今までも何かにつけて感じてたんだけど、本書のなかでも、いや、そこまで言う、って驚かされるのがいくつもある。
>でも、モチベーションやテンションに関しては、どうにもならないところもあるんじゃないですかね。一年を通してでも、一日単位でも、そう思います。(p.144)
とかってのもそうだけど、そこでふつうはどうにかしようとするもんだろうに、羽生さんは自分で調整できないって割り切っちゃう。
あと、いくらメタレベルったって、自身の対局について、
>自分が予想しないドラマを対局しながら観ていくという感覚は、やっぱりありますね。うん。どうせ観るなら、つまらないドラマよりも、面白いドラマを観たほうがいいので(p.114)
とまで言うのは、すごい。プレイすることを試合を楽しみます、なんて言うアスリートはいるけど、ちょっと次元がちがうような。
本書全般を通じて、何を目標とするかとか、何のためにやるかとかって問いに、羽生さんはあっさりと無い、っつーか考えない、みたいな答えを繰り返す。
めんどくさくて言ってんぢゃなくて、ホントにそう思ってる、なんかホントそこ超越してるって感じ。
考えてもわからないもの、考えたってしかたないことは、考えない、そういうスタンスが、すごい。
でも、きわめつけは、この激動の時代に将棋界の第一人者として自身の役割はと問われたのに対し、
>役割ですか? 役割なんて、あるんですかねぇ……(略)役割はないですよ。自分のできることをやっていく、ということですね(p.295)
って答えてる、これには参った。そうかあ、そぉなんだー。
どうでもいいけど、著者は羽生さんにインタビューすると、なんか癒しを感じてしまうと言ってるんだけど、そのへんのとこ、インタビューの模様を、「うーん、うーん」「ええ、ええ」「はい、はい」「ハハッ、ハハッ(笑い声)」って羽生さんの放つ間を省略編集せずに活字にしてあるんで、こっちも読んでてあの独特の話し方を思い出させられるとこがよかったりする。
序章 7年目のカプチーノ
第一局 私、完璧主義じゃないんです
渡辺明――「この人、不思議だな」と思うときがある
第二局 闘うものは何もない
久保利明――羽生さんは本当に楽しんでいた
第三局 勝ちに行くとき、隙が生まれる
谷川浩司――嫉妬と恐怖心を乗り越えて
第四局 考えてもしようがないっしょ
桜井章一――羽生善治が歩く「獣道」
第五局 コンピュータにできるなら人間だって
島朗――羽生将棋の本質はど根性だ
第六局 人間に役割なんてあるんですか?
森内俊之――僕を育ててくれた理想のチャンピオン
第七局 忘れることが大事です
終章 死ぬまで? そういうものですよね