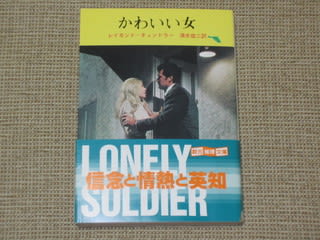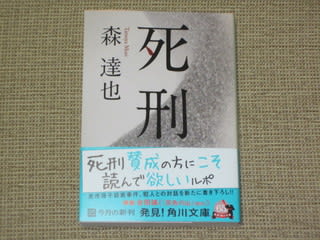2週間ぶりに、乗馬にいく。
先週は、乗馬練習しなかったけど、場所をかえて、やっぱ馬を見てたりはしたんだけどね。

さて、きょうの馬は、ギルデッドエージ。私ははじめて。

けど有名だよね、このサラブレッドは。
2010年の某ドラマでは主演してたし。

(↑ロケで来たときのひとこま。三日月型の星はメイク。)
あのときの調教シーンの撮影では、すごいスピードで駈けてったのが印象的だった。
(馬もすごいけど、騎手役の俳優さんがそれに乗ってったのにも驚いた。)
去年のうちわの試合では、たしか障害ではなく馬場馬術のほうに出てたような記憶があるけど。
さて、先入観はナシで、またがってみる。
なんかフワッフワとした感じ。サラブレッドにはめずらしい感じ、ピョコンピョコンはずむような歩き方。
5分常歩、5分速歩。しかし、なんか全然うまく乗れそうもないぞ。

あとでちょっとだけ障害をやることになり、20分くらいの猶予が与えられたので、フラットワーク。
速歩10分やって、ぜんぜん前に出てる感じなくて、駈歩5分やるけど、これまた詰め伸ばしできず。残りの5分、休憩しちゃった。
すこし景気よく駈歩を出してきたいんだけど、うまくいかない。
上でジタバタして、馬の背中を押しちゃうもんだから、敏感に反応されて、そのたびに手前を替えるような動きになっちゃう。
巻乗りすると(特に左手前)、なんか止まっちゃいそうな勢いになるし、これでは、とても障害は飛べないぞ。
でも、いーの、夏は暑いから、半分遊び、人馬ともにゲーム気分で、障害あれば飛んでみて、楽しくやれればそれでいい。でなきゃ、暑くてやってられないって。

そしたら、アブミは3つくらい短くして、スタンバイ。ぜんぜん障害飛ぶ自信なんかないけど、まあ、こないだみたいに、障害はじめたら馬がやる気出すかもしれないしね。
速歩で、低いクロス、飛んだら駈歩、3歩で先にあるバーをまたぐ、そしたら真っ直ぐ行って、速歩におとす。
4頭の隊列の3番目なんて無難なポジションに位置して、順に障害に向かう。
回転を強く、って思ったんだけど、弱いよ、これぢゃ、あわてて推進するが、あまり直前でバシバシやっても馬の集中の邪魔になるだけだから、とにかく真っ直ぐ真ん中に連れてこうとする。
止まったり逃げたりする感じはなく飛越、でも、そのあともすぐ止まっちゃいそう、わりとサラブレッドって興奮して走ってくもんなんだけどね。あらためて前へって推進してみるけど、横木は3歩半で跨ぐことになっちゃう。
「飛んだあとはツーポイントで、弱ければ脚!」 うーん、いまのは動かそうとあせって、座って鞍をグリグリ圧してたし。
どうもツーポイントで脚とかって、軽やかな乗りかたは苦手だな、ほっぽっとくと馬の背中を無理に圧そうとしちゃうことのほうが多い。
繰り返し、飛んだあとすぐ止まりそうなんで(暴走されるよりいいんだけどね、個人的には)、やっぱグイグイと前に出すことを促さざるをえない。
反応しなかったらムチ使ってもいいっていうんだけど、障害飛んだあとムチくれるのもなあ、と思う私の持ってるワザは、やっぱホメることだけなんだよね。
駈歩を維持して横木をまたいだとこで、思いっきりホメる、そして真っ直ぐスローダウンしたとこで、またホメる。「できるじゃーん、いまの調子で頼むよ」って、回転しながらホメる。
来た、馬が反応してるよ。次に飛んだあと、グイっと自分から前に出る感じが出てきた。1・2・3で横木跨ぐ、スローダウン、馬が褒められるの待ってるのがわかる。
当然めちゃめちゃホメる。「なんだよ、こんなことでいーのかよ、早く言えよ」って馬の背中から伝わってくる。
もう次回からは、飛んだあとの脚はろくすっぽ必要なくなってくる。
ゲームのルールを理解した馬に乗るのはおもしろい、けど飛んだあと加速しなくていいんだぜ。「ずっと同じペースの駈歩を続けられるように!」って言われちゃう。そうなんだよ、回転を強く、障害向いたらジッとして、飛んだあとも自然に前へ、って全部同じペースでやりたいんだけど。

障害の高さを上げて、そのあと垂直に変わる。そしたらこんどは駈歩で垂直だ。
テーマは駈歩の維持なんで、ちょっと変わったことに、だいぶ(10mくらい?)手前に横木が1本置かれる、駈歩でそれをまたいだら3歩で踏切バー、んで飛越、飛んだあとはさっきとおんなじ3歩先にまたバー、というライン。
最初のバーをまたいでから仕掛けるようなことをしたら、リズム崩れちゃうな、って思って、回転のとこから強くいくつもりで行くんだけど、うまく前に出せないから、「もっと前から動かして来て」と言われちゃう、わかってんのにできないとがっかりする。
繰り返すうちに、障害向くと馬にスイッチ入るような気がしてくるんで、こんどはさっきまでと逆、「ゆっくり行こうな」って話しかけながら飛ぶ。ときどき左右に傾くような感じがしちゃうときあるけど、それくらいではもう全然止まる感じではない。自分から向かってく馬に乗ってるのは楽しい。
できてきたんで、ちょっと複雑に組み合わせる。左手前の駈歩で、このラインを飛んだら、速歩におとして右手前の輪乗り、右の駈歩出したら、180度回転して、クロス、大きく180度回転して同じ最初のライン、また速歩におとして左手前の輪乗り、左駈歩出したら、180度回転して、垂直。
左手前の回転は、フラットワークのときからうまくいかないんだけど、とにかく前出して、障害向ければ、まあ、飛んではくれる。右回転は比べるとスムーズ、このクロスは初めてだけど、前につれてけば躊躇することなんかなく飛越。飛越したらすぐ次を見て、回転、横木またぐと馬にスイッチ入る、おさえるぐらいの感じで飛越。左回転、左はどうにもうまくいかない、オーバーランしたんで、もう一回巻き乗りして、弧から障害への導線をスムーズなラインにしたいんだけど、ちょっとイメージより外(右)いっちゃったのを修正しながら入る、飛越。最後の飛んだあとも、流さない、真っ直ぐ真っ直ぐ、ゆっくりとスローダウン。
「もう一回、最後に左手前で横木からのラインと、左回転しての垂直」って、できてねーとこ見抜かれてーら。
回転がうまくいかない。前出して!って言われて、気づく。前進してなきゃ、いくらハンドルまわしたり舵切っても曲がっていかないんだよね。内の脚ドンドンやって向かってく。飛越、回転、また飛越。
まーいーでしょ、ってことで終了。
納得いかないんで、速歩のクールダウンの後、常歩で回転を試みる。比べれば右手前は外の手綱で回れる気がするけど、左手前は外へ張ってっちゃう。人間の右の肩を内に回さないように意識してやってみるんだけど、どうにもうまくいかない。
次回は、もうすこし馬のアタマと肩の位置とかに気をつけて、内に向けたときにバランス崩したり、人が前に倒れて馬の肩に乗っちゃたりしないように注意しよう。

いろいろやったけど、まあ、騎座でグリグリしたりとか、拳でぎゅぎゅっとやったりとか、馬に迷惑かけたんで、頭絡と鞍を外したあとは放牧場に一度放してやる。


解放されて、好きなように寝っ転がる馬を見てると、あーこれでバランスの崩れも解消されたかなって、いいことしてやった気になる。
っつーか、馬にはこれがいちばん、と私は思ってる。
(私のほうも姿勢わるくて歪んぢゃってんだろうから、整体でもいったらいいのかもしれない。)