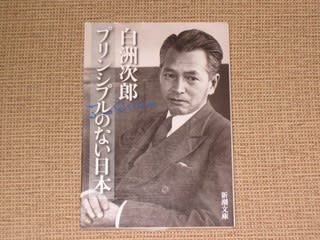白洲次郎 平成18年 新潮文庫版
前から気になってたんだけど、こないだ選挙なんてあったもんだからこの機に(?)、その後で、つい最近読んだ本。
白洲次郎さんというのは、どんなひとか詳しくは知らなかったんだが、戦後すぐの時代に、GHQから日本の憲法の案をわたされて、これ訳して政府案にしろって言われて、面くらいながらも仕事してたチームの一員だったらしい。
ほかの翻訳官に「シンボル」の訳を求められて、辞書ひいたら「象徴」と書いてあるって答えたところが、現在の憲法第1条に採用された所以だそうである。
本書に入ってるのは、1950年代に雑誌に寄せたものがほとんどで、最後の2編だけは1969年に書かれたもの。
でも、いま読んでも、日本・日本人について、言ってることは通用するというか、当たってると思うものが多い。
占領下で憲法をそうやっておしつけられた経験もあるから、著者は憲法改正には賛成している。
なかでも面白いのは、参議院を縮小すべきという意見で、「解散の対象になり得ない国会の一部が、衆議院と殆ど同様な権限を持つことは、二院制ということから考えて見て無意味だ」という理由である。
関連して、首相と内閣の大臣の過半数は「国会議員」でなくてはならない、という条文にも反対。参議院議員が首相になって、参議院議員ばっかりで内閣をつくったら、自分たちは6年間身分安泰で、都合のいい結果がでるまで衆議院を何度でも解散するでしょ、っていう理由。(だから改正案は、首相と内閣の過半数は「衆議院議員」とするのがよいと。)
あと、政局もそうなんだけど、それを取り巻くマスコミも含めて、日本人の論争の仕方とかに疑問を呈してるとこ、とても鋭い。
日本の言葉って、アヤとか含みとかがあるせいで、語るひとによっては表現が正確ぢゃなくなる、「いろんな含みのあるような表現をする。その表現に自分が先に酔っちゃうのだ」と指摘している。ついでに、「そういう言葉の魔術に引っ掛かるのが、日本の読者の低級さ」とまで言ってる。
また、一方では、「日本人は一般的に非常に何でも総括論的の筆法がお好きらしい」として、戦争中は八紘一宇とか一億一心とか簡単に何字かで表現しちゃったように、「複雑な事程簡単に片付けてしまいたいらしい」と言っている。
そういったことは、ただ文章表現だけの問題ぢゃなくて、ものの考え方がそうなっちゃってんぢゃないの、って警鐘を鳴らしてる。はっきりした言い方しないから、問題の本質にいかないで、議論が同じとこグルグル空虚にまわっちゃうんだよね、きっと。
政争に関しては、「この大和民族はどうも政治の論争がアッという間に感情問題に急進展して、ヒステリーの女そっちのけの坊主が憎けりゃケサまでにくい論法に行くことがあまりにも多い様に思う」として、活発な論争とガタガタ(辞めろとかなんとか)反対反対と騒ぐのは違うだろと。
国会議員もマスコミも、議会政治というもののプリンシプルがわかってるのかという一節もおもしろい。
「政府与党が過半数を制している議会においては、政府与党の提出する法案が通過成立することは当り前」であって、反対なら反対意見を堂々と議会で述べるのはいいけど、審議拒否するとか引き延ばして成立を阻止しようってのはダメ。
政府与党がよくないことをしようとしてたとしても、それは間接的にその政府を選出した国民の不明であって、政府を批難することはそれらの人々を選出した国民を批難することである。
「国会議員は主権者たる国民の代表であって、代表が主権者を批判してよりものかどうかじっくり考えてもらいたい」とは、さすが憲法をつくったときに現場にいたひとの意見だね。
「いま反対党のあなた方には、政府の提出する法案を阻止する権限は国民から与えられていないのです」ってのは、時代を問わずいつの世でも日本の野党にはよく言っといたほうがいいように思える。
ぢゃあ、嫌な法案とおっちゃったらどうしたらいいのか。次の選挙に勝って多数を制して、その法律を廃止すればよい、と。非常に明快。
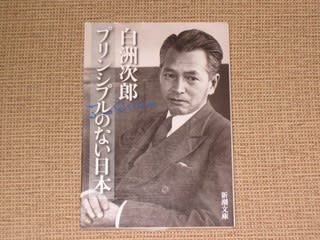
前から気になってたんだけど、こないだ選挙なんてあったもんだからこの機に(?)、その後で、つい最近読んだ本。
白洲次郎さんというのは、どんなひとか詳しくは知らなかったんだが、戦後すぐの時代に、GHQから日本の憲法の案をわたされて、これ訳して政府案にしろって言われて、面くらいながらも仕事してたチームの一員だったらしい。
ほかの翻訳官に「シンボル」の訳を求められて、辞書ひいたら「象徴」と書いてあるって答えたところが、現在の憲法第1条に採用された所以だそうである。
本書に入ってるのは、1950年代に雑誌に寄せたものがほとんどで、最後の2編だけは1969年に書かれたもの。
でも、いま読んでも、日本・日本人について、言ってることは通用するというか、当たってると思うものが多い。
占領下で憲法をそうやっておしつけられた経験もあるから、著者は憲法改正には賛成している。
なかでも面白いのは、参議院を縮小すべきという意見で、「解散の対象になり得ない国会の一部が、衆議院と殆ど同様な権限を持つことは、二院制ということから考えて見て無意味だ」という理由である。
関連して、首相と内閣の大臣の過半数は「国会議員」でなくてはならない、という条文にも反対。参議院議員が首相になって、参議院議員ばっかりで内閣をつくったら、自分たちは6年間身分安泰で、都合のいい結果がでるまで衆議院を何度でも解散するでしょ、っていう理由。(だから改正案は、首相と内閣の過半数は「衆議院議員」とするのがよいと。)
あと、政局もそうなんだけど、それを取り巻くマスコミも含めて、日本人の論争の仕方とかに疑問を呈してるとこ、とても鋭い。
日本の言葉って、アヤとか含みとかがあるせいで、語るひとによっては表現が正確ぢゃなくなる、「いろんな含みのあるような表現をする。その表現に自分が先に酔っちゃうのだ」と指摘している。ついでに、「そういう言葉の魔術に引っ掛かるのが、日本の読者の低級さ」とまで言ってる。
また、一方では、「日本人は一般的に非常に何でも総括論的の筆法がお好きらしい」として、戦争中は八紘一宇とか一億一心とか簡単に何字かで表現しちゃったように、「複雑な事程簡単に片付けてしまいたいらしい」と言っている。
そういったことは、ただ文章表現だけの問題ぢゃなくて、ものの考え方がそうなっちゃってんぢゃないの、って警鐘を鳴らしてる。はっきりした言い方しないから、問題の本質にいかないで、議論が同じとこグルグル空虚にまわっちゃうんだよね、きっと。
政争に関しては、「この大和民族はどうも政治の論争がアッという間に感情問題に急進展して、ヒステリーの女そっちのけの坊主が憎けりゃケサまでにくい論法に行くことがあまりにも多い様に思う」として、活発な論争とガタガタ(辞めろとかなんとか)反対反対と騒ぐのは違うだろと。
国会議員もマスコミも、議会政治というもののプリンシプルがわかってるのかという一節もおもしろい。
「政府与党が過半数を制している議会においては、政府与党の提出する法案が通過成立することは当り前」であって、反対なら反対意見を堂々と議会で述べるのはいいけど、審議拒否するとか引き延ばして成立を阻止しようってのはダメ。
政府与党がよくないことをしようとしてたとしても、それは間接的にその政府を選出した国民の不明であって、政府を批難することはそれらの人々を選出した国民を批難することである。
「国会議員は主権者たる国民の代表であって、代表が主権者を批判してよりものかどうかじっくり考えてもらいたい」とは、さすが憲法をつくったときに現場にいたひとの意見だね。
「いま反対党のあなた方には、政府の提出する法案を阻止する権限は国民から与えられていないのです」ってのは、時代を問わずいつの世でも日本の野党にはよく言っといたほうがいいように思える。
ぢゃあ、嫌な法案とおっちゃったらどうしたらいいのか。次の選挙に勝って多数を制して、その法律を廃止すればよい、と。非常に明快。