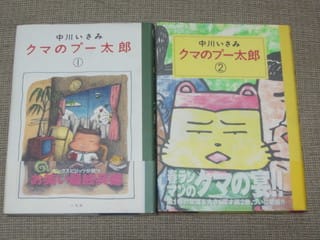島田雅彦 2004年 集英社文庫版
新作発表されたら必ず読むってほどぢゃないんだけど、おもしろいから好きなんだよね、島田雅彦。
んで、おもしろいから何度も何度も読み返す、ってタイプでもないんだよね。
で、ひさしぶりに読み返してみた、これ。文庫の初版だから、出たときに興味もったんだろうけど、単行本が出たからってすぐ買って読もうってほど興味あるわけぢゃないんだよね。
それはとにかく、読めばおもしろい。やめられない止まらないで、ズンズン読んぢゃう。
郊外に住む小説家が主人公。浮気がすぎて、奥さんに愛想つかされる苦悩の日々なんだが、近所に住む同じような家族構成の医者の一家では母子殺人事件が起きたりする。
時代は1995年ころ、主人公が35歳になる年に、日本では震災や地下鉄サリン事件が起きるような状況。
>この国は何か不吉なことが起きると、とたんに冗談やユーモアが通じにくくなり、警察が元気になり、パンクやホームレスやアーティストの肩身が狭くなる
と主人公が嘆く世相だあね。
殺人事件の真相とか、主人公のとる行動とかは、ネタばらしてもしょうがないんで、ここで言及しないけど、
>でも、こういう自由にはあまり馴れていないので、途方に暮れている。自由の刑ってやつだな。
ってフレーズは、そういえば、そんなタイトルの小説が著者には同じころにあったな、なんて思う。
自由は必ずしも歓迎することぢゃなくて、見ようによっては刑罰みたいなもんだってね、束縛されてたほうが人間ラクだったりするから。
どうでもいいけど、頻繁に読み返したりしないから憶えてない証拠に、本書の主人公の千鳥姫彦って名前、著者の初期の作品「優しいサヨクのための嬉遊曲」の主人公と同じだって、巻末の解説みるまで気づかなかった。デビュー作の後日談?

新作発表されたら必ず読むってほどぢゃないんだけど、おもしろいから好きなんだよね、島田雅彦。
んで、おもしろいから何度も何度も読み返す、ってタイプでもないんだよね。
で、ひさしぶりに読み返してみた、これ。文庫の初版だから、出たときに興味もったんだろうけど、単行本が出たからってすぐ買って読もうってほど興味あるわけぢゃないんだよね。
それはとにかく、読めばおもしろい。やめられない止まらないで、ズンズン読んぢゃう。
郊外に住む小説家が主人公。浮気がすぎて、奥さんに愛想つかされる苦悩の日々なんだが、近所に住む同じような家族構成の医者の一家では母子殺人事件が起きたりする。
時代は1995年ころ、主人公が35歳になる年に、日本では震災や地下鉄サリン事件が起きるような状況。
>この国は何か不吉なことが起きると、とたんに冗談やユーモアが通じにくくなり、警察が元気になり、パンクやホームレスやアーティストの肩身が狭くなる
と主人公が嘆く世相だあね。
殺人事件の真相とか、主人公のとる行動とかは、ネタばらしてもしょうがないんで、ここで言及しないけど、
>でも、こういう自由にはあまり馴れていないので、途方に暮れている。自由の刑ってやつだな。
ってフレーズは、そういえば、そんなタイトルの小説が著者には同じころにあったな、なんて思う。
自由は必ずしも歓迎することぢゃなくて、見ようによっては刑罰みたいなもんだってね、束縛されてたほうが人間ラクだったりするから。
どうでもいいけど、頻繁に読み返したりしないから憶えてない証拠に、本書の主人公の千鳥姫彦って名前、著者の初期の作品「優しいサヨクのための嬉遊曲」の主人公と同じだって、巻末の解説みるまで気づかなかった。デビュー作の後日談?