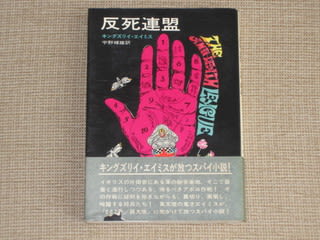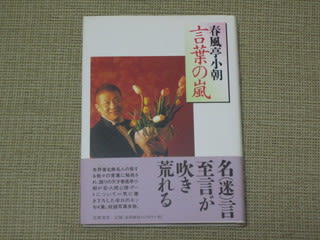松本博文 2017年5月 洋泉社
サブタイトルは「人間vs.人工知能の激闘の歴史」で、題名どおり、看板に偽りなしで、そういう内容の本です。
「おわりに」の日付が、2017年4月17日となっているので、4月1日に人間である名人がソフトとの対局の第1局に負けたあとに書かれたということになる。
本書が出版されたの知って、読んでみようと書店で探してたら、たまたま、同じ著者のこないだとりあげた『ドキュメント コンピュータ将棋』って新書を見っけちゃった。
そっちは2015年のものだったから、読むなら時系列に沿ってだろうなと思って、二つとも買って、順番に読んだんだが。
特に両方読む必要はなかったかな、こっちだけで十分だったかという感想をもった。
それだけいろんなことがギュッと詰まってて、棋士対コンピュータの歴史的出来事とか登場人物とかについて、わかりやすい。
(個人的には、ことし名人はソフトに敗けてしまったわけだが、いっちゃん強いひとりである豊島クンが過去にソフトに敗けてなかったのは良かったなと思う。)
指し手の解説はなし、将棋の歴史についてはあり、チェスや囲碁のこともちょっとあって、まあ将棋指さないひと向けではあると思う。
将棋ソフトの開発、発展の歴史、ソフトにも開発者の個性が出るんだってあたりが、知らないことばかりだったのでおもしろい。
やっぱ、いちばんえらいひとは、将棋知らないのに強いBonanzaつくって、それ全部公開しちゃった保木さんだと思うな。
コンテンツは以下のとおり。
第一章 神が創りたもうたゲームの系譜
(一)囲碁・将棋の歴史を振り返る
(二)幕を開けた人間と機械の戦い
第二章 電王戦前夜―人間vsコンピュータの始まり
(一)コンピュータ将棋の黎明期
(二)人間を凌駕するコンピュータ
(三)人智を超えた“学習する”将棋ソフト
第三章 AIが人間を超えた日
(一)女流トッププロvsコンピュータ連合軍
(二)第一回電王戦
(三)第二回電王戦
(四)第三回電王戦
第四章 苦闘―棋士の葛藤と矜持
(一)電王戦FINAL
(二)FINAL最終戦に見た両者の信念
第五章 棋士とAIの未来
(一)新たにスタートした第一期電王戦
(二)第二期電王戦
(三)AIとの苦闘が残すもの

サブタイトルは「人間vs.人工知能の激闘の歴史」で、題名どおり、看板に偽りなしで、そういう内容の本です。
「おわりに」の日付が、2017年4月17日となっているので、4月1日に人間である名人がソフトとの対局の第1局に負けたあとに書かれたということになる。
本書が出版されたの知って、読んでみようと書店で探してたら、たまたま、同じ著者のこないだとりあげた『ドキュメント コンピュータ将棋』って新書を見っけちゃった。
そっちは2015年のものだったから、読むなら時系列に沿ってだろうなと思って、二つとも買って、順番に読んだんだが。
特に両方読む必要はなかったかな、こっちだけで十分だったかという感想をもった。
それだけいろんなことがギュッと詰まってて、棋士対コンピュータの歴史的出来事とか登場人物とかについて、わかりやすい。
(個人的には、ことし名人はソフトに敗けてしまったわけだが、いっちゃん強いひとりである豊島クンが過去にソフトに敗けてなかったのは良かったなと思う。)
指し手の解説はなし、将棋の歴史についてはあり、チェスや囲碁のこともちょっとあって、まあ将棋指さないひと向けではあると思う。
将棋ソフトの開発、発展の歴史、ソフトにも開発者の個性が出るんだってあたりが、知らないことばかりだったのでおもしろい。
やっぱ、いちばんえらいひとは、将棋知らないのに強いBonanzaつくって、それ全部公開しちゃった保木さんだと思うな。
コンテンツは以下のとおり。
第一章 神が創りたもうたゲームの系譜
(一)囲碁・将棋の歴史を振り返る
(二)幕を開けた人間と機械の戦い
第二章 電王戦前夜―人間vsコンピュータの始まり
(一)コンピュータ将棋の黎明期
(二)人間を凌駕するコンピュータ
(三)人智を超えた“学習する”将棋ソフト
第三章 AIが人間を超えた日
(一)女流トッププロvsコンピュータ連合軍
(二)第一回電王戦
(三)第二回電王戦
(四)第三回電王戦
第四章 苦闘―棋士の葛藤と矜持
(一)電王戦FINAL
(二)FINAL最終戦に見た両者の信念
第五章 棋士とAIの未来
(一)新たにスタートした第一期電王戦
(二)第二期電王戦
(三)AIとの苦闘が残すもの