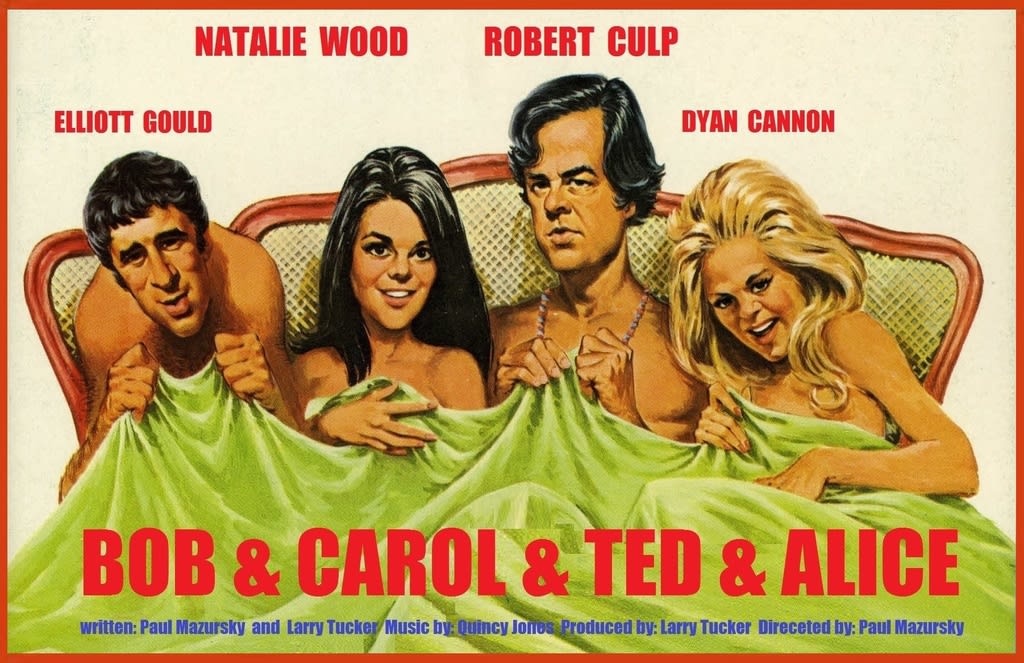Michael Douglas and Jack Nicholson on the set of One Flew Over the Cuckoo's Nest pic.twitter.com/iW5ClkBBTA
— Eyes On Cinema (@RealEOC) October 7, 2019
高さは大した事ないですが、ご指摘の通り鉄塔に激突すれば即死のスタント。
— 高瀬将嗣 (@masatsugutakase) October 8, 2019
殺陣師がキャメラの死角に這いつくばってストップウォッチ測りながらGoサインを出しました。
ちなみに鉄塔は三本で、その間を縫う作業。
ましてや一人目は仰向け。
前日はスタントマンはもとより殺陣師も眠れませんでした。 https://t.co/coyEZeyJh6
Kirk Douglas on having great success and great failure with One Flew Over the Cuckoo’s Nest pic.twitter.com/kfVp6DP0M4
— Eyes On Cinema (@RealEOC) October 7, 2019
原題はretroactive(さかのぼる、遡及)。1997年作。
デーモン閣下といえば、特撮好きとしても有名でな
— reo/gum (@rmemom0806) October 5, 2019
特に怪獣の声真似はグランプリをとったほど
個人用にまとめてみた#特撮 pic.twitter.com/9EcUiPK2el
フィリピンオオコウモリこんなでかいの
— 明日くん M3秋B-14a (@AxSxKxN) September 26, 2019
人じゃんもう pic.twitter.com/Ej6BWeSTXX
Michael Caine, 1964 pic.twitter.com/0fBFoOmOvW
— History Lovers Club (@historylvrsclub) October 7, 2019
8月度の兵庫の死亡労災だけど、一軒目が怖すぎる pic.twitter.com/wUI1hLTg1a
— えむねふぉ™ (@_mNEFO_) October 7, 2019
我慢できずに、日本橋高島屋 池田晃将展に。攻殻機動隊やマトリックス、森博嗣とかとか...SFやサイバーエンタメが血肉になっている人にはたまらない、其れ等と日本伝統超絶技巧の融合です。まるで「真理」が形になって現れたかのような。これ、螺鈿細工なんですよ→ pic.twitter.com/OyQnjocqKz
— おかざき真里 (@cafemari) October 7, 2019
ミラ・ジョヴォヴィッチが悪役にまわったけれど、こちらも似合う。
クリーチヤーたちのグロテスクなデザインや流血ゴア描写など相当にどぎつい。
クリーチヤーデザイン は 大いに凝っているのだけれども ギレルモ・デルトロ 版みたいに映画の中で美的にはまるといったことはあまりない。良くも悪くも平明。
テレビシリーズ「ハワイ5-0」のレギュラーをギャラの折り合いがつかず降板したダニエル・デイ・キムが顔にすごい傷痕をつけたメイクで登場、なんかこちらでレギュラーになりそう。
魔女バーバ・ヤーガの二本の鶏の脚で支えられた家が出てきた時、あ、ハウルの動く城と思ったが、もちろん順番が逆でバーバ・ヤーガの方が先。古くからロシアに伝わる魔女で、ムソルグスキーの「展覧会の絵」にも出てくる。
ジョン・ウィック見たんですけど隣に座ったおじいちゃんが見終わった後「あんなに銃撃ったら気持ちよさそう」って俺よりはるかに浅すぎる感想言ったので自分の浅さのレベルの低さを思い知って打ちのめされてしまった
— ハンバーガー (@HundredBurger) October 4, 2019
TDK ビデオテープ エクストラHG CM。(1982)スティーヴ・ストレンジ(『ウィスパーズ』ヴィサージ)
— みどりん (@icu_0828) October 5, 2019
1982 TDK video tape Ad featuring Steve Strange pic.twitter.com/Md0KeA6GxT
ヤマト運輸の『宅急便コンパクト』の箱封を切ると10匹のクロネコがいて一コマづつ撮影するとちゃんとアニメーションになってたw
— Takeo Hayashi (@BoxDogPuppy) October 5, 2019
かわいいっ pic.twitter.com/MNtmZnho9P
家族のハロウィン衣装がかわいすぎる pic.twitter.com/8JICNj6gub
— σ(゚∀゚ まて私は味方だ (@tyomateee) September 26, 2019
James Dean as a little kid. Check out for more: https://t.co/R9M2a0abhB pic.twitter.com/PgCWNeuxug
— History Lovers Club (@historylvrsclub) October 6, 2019
感情移入って、「登場人物を通じて見る(読む)人の感情が動く」ことで、「登場人物に共感する」ことではない。後者だと主役は無害な善人ばかりになり、物語は痩せる。
— 一色伸幸 (@nobuyukiisshiki) October 6, 2019
座頭市と化した金田正一に叩き斬られる勝新太郎。 pic.twitter.com/mGJJkeLoZ7
— 吉田光雄 (@WORLDJAPAN) March 27, 2014
うがって見ると、ネット上を行き交う「情報」よりはあくまで発言できないでいる生の人間の顔と声を伝えることを重視している姿と思え、だからネットでリアルタイムで戦地の現況を伝えながら命を落とすというアイロニカルな構成をとっているようにも思える。
隻眼に眼帯という姿は海賊みたいで、同じロバート・リチャードソン撮影の「サルバドル」で描かれた実在のゴンゾ(ならずもの)ジャーナリスト、リチャード・ボイルみたいなキャラクターかと思ったら真逆。
戦場シーンの人物にぴたっとついていくやたらスムースな前進移動撮影と音響効果は「フルメタル・ジャケット」を思わせる。
「日の丸が あがってうれし オリンピア」
— 三一十四四二三 (@31104423) October 5, 2019
これは私が9歳の時に作った、オリンピック俳句だ。
ミュンヘン オリンピックの時に、グリコかどこかが募集したもので、私はこのつまらない句で、「銀メダル」を獲得。カレー1年分が送られてきたのだ。
でも、その頃から私はオリンピックにはなんの
ちなみに『芝園団地に住んでいます』の表紙写真右側に写っている棟は『童夢』で大きな爆発が起こり超能力で破壊される場面で使われていて(ただし内部は違う棟になっている)、日本のマンガ史に残る建築物かもしれない。下はそれが判るp154~155の見開きと同アングルの写真。15年前に撮影。 pic.twitter.com/D3yR2FyuXw
— 古書ノーボ (@koshonovo) October 4, 2019
Brilliant tribute to the work of Buster Keaton
— Eyes On Cinema (@RealEOC) October 1, 2019
source: https://t.co/VANtAHRbL9 pic.twitter.com/2FBvQBKs5C
ブルース・リーの弟子テッド・ウォンが語る、現実のブルース・リーの戦い方
— ストライクフォース (@kamaeatte) October 4, 2019
・映画のように不必要に動き回らず、目の前に立ちはだかって微動だにしない
・しかしそこからの変化は素早く、「パンチが来るのが見えなかった」
・動きにいつも何らかの変化を加えていた
・怪鳥音?あれは映画の中の話だ
スコセッシが11歳の時に描いたストーリーボード。オープニングシークエンスのタイトルの描き込みっぷりに早くも業の深さが… https://t.co/VOawytaaRT
— junkTokyo (@junktokyo) October 5, 2019
「狼よさらば」を代表とするヴィジランテ(自警主義)ものの新しい一作。女性が復讐するというのはジョディ・フォスター主演の「ブレイブ・ワン」というのがあったし、必ずしも前例がないわけではない。
この映画の新味とすると、冒頭でいきなり復讐シーンから始めて、それから回想で事情を語っていく形式をとっていることで、とにかく初めからやたら強いという設定らしてどうやって犯罪組織を相手にできるくらい強くなれたかという理由づけはあまり気にせずとにかく強いのだという設定で押しきっていること。
これはこれで美女のアクションを見せるという本来の目的からすれば割りきっているとも言える。もともと荒唐無稽さや法的モラル的な乱暴さに対する批判は免れないジャンルなのだし。
ラスボスが髪型含めて「コマンドー」のバーノン・ウェルズみたい。
あとヒロインがスラムに身を隠しスラムの住人に邦題通り女神扱いされるという趣向もある。「狼よさらば」の頃は中産階級層が厚かったから市民社会が喝采するという感じだったが、今では社会の底が抜けたのを反映している感
Steve McQueen, Bruce Lee and Fumio Demura. Check out for more: https://t.co/f44vFeFv0e pic.twitter.com/GrwCfpeMYG
— History Lovers Club (@historylvrsclub) October 4, 2019
Young Christopher Walken as a clown, 1955 pic.twitter.com/rwiVINekiJ
— Eyes On Cinema (@RealEOC) October 3, 2019
昔は徹夜で仕事してよく椅子に座ったまま寝た。眠りが浅いので奇怪な夢をたくさん見た。あれは健康に良くない。 pic.twitter.com/nmsUbvQasd
— 唐沢なをき (@nawokikarasawa) October 3, 2019
「帰ってきたウルトラマン」第18話 本放送時に流れたナレーション
— ヒロミ・ファンファニー (@hiromifanfannyY) October 4, 2019
全日空機雫石衝突事故の報道特別番組のため、当初7月30日に放送する予定だった第18話の放送が翌週に順延された。8月6日の放送に際し、メインタイトル部に郷秀樹(団次郎=団時朗)による、お詫びのナレーションが流れた。 @retoro_mode pic.twitter.com/Dl7rh5CKMV
子供、それも男の子が幼児を世話をする図がすでに意表を突き、女性監督の目が光るところでもあるだろう。
たかが身分証がないくらいで、と日本にいると思ってしまうが、考えてみると日本にも戸籍を持たずそれで多大な社会的不利益を蒙っている人はいくらもいるのを思い出した。
本質が存在に先行するなんて言葉があるが、本質とも言えないレッテルが中身より先行するというのはいかにも今の世界を典型的に表す。
監督のナディーン・ラバキーは女優でもあって、弁護士役で出演もしているが、少年があなたたち(いい身分の人間)には僕のことはわからないと作中の裁判で言われるのは実際に言われたことでもあるだろうし、この映画を作るにあたっての自戒でもあるだろう。
Stanley Kubrick directs Danny Lloyd on the set of The Shining pic.twitter.com/IMoJwmww1Z
— Eyes On Cinema (@RealEOC) October 2, 2019
#登山の日
— James(ジェームズ) (@James81458933) October 3, 2019
「アイガーサンクション」ユタ州の奇岩の間でスタント無しの綱渡りに挑戦したイーストウッドと撮影の様子。確か彼も高所恐怖症だったはず。 pic.twitter.com/8KbNPaH1uo
Carrie Fisher, 1983. pic.twitter.com/ei2Jg5wPES
— History Lovers Club (@historylvrsclub) October 3, 2019
山形国際ドキュメンタリー映画祭30年。『阿賀に生きる』クランクイン30年。山形新聞に寄稿しました。
— 小林茂 (@kobacamera) October 1, 2019
『阿賀に生きる』撮影小林茂。 pic.twitter.com/TCmwhUBCZn
この法律破った人いるのかな… pic.twitter.com/wxV57P6BYc
— BuzzFeed Japan (@BuzzFeedJapan) October 2, 2019
Young Clint Eastwood pic.twitter.com/yGpaAVBZ1U
— History Lovers Club (@historylvrsclub) October 2, 2019
ちょうど貫地谷しほりその人が結婚したというニュースが流れた後で見たのが妙に効果的。余談だが、週刊文春だかで当分結婚はなさそうであると書かれた直後。