今年の彼岸花は、漱石の長編小説の題名のように彼岸過迄、咲いている。いや、まだ咲いていないのもたくさんある。瑞泉寺はどうか、ミュージカル映画 、”イースター・パレード”を川喜多映画記念館で見たあと、踊るように、うきうき気分で出かけた(汗)。
途中で寄った、八幡様の土塁の彼岸花は、咲き始めた株が、全体の1、2割程度、一方、宝戒寺は、紅も白もまずまず咲いていた。さて、瑞泉寺はどうか。
はい、”まずまず組”でした。ほらね。

この、夢窓疎石の作庭の石庭前の彼岸花も。

夢窓疎石といえば、横浜の歴博で展覧会が開催されている。吾輩は行く予定でごわす。

瑞泉寺といえば、芙蓉も有名。花のつきはもうひとつだったけれど。

今秋の鎌倉観光のポスターは瑞泉寺でごわす。ピンク色の秋明菊が主役。

こんな、写真を撮りたかったが、ピンクはわずかに残っている程度、白いのがようやく咲き始め。

でも、想定外の事態も発生。冬桜が開花。水戸黄門さまお手植えの桜でごわす。ぼけたのかな。

ぼけた木もいました。

・・・
宝戒寺にて
紅白曼珠沙華

コミカルなミュージカル映画は、心をうきうきさせてくれる。

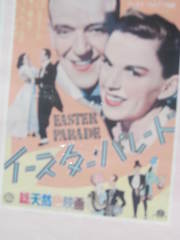
今日のお天気は崩れそう。女子オープン、最終日は行かないことにした。中秋の名月もむづかしそう。
途中で寄った、八幡様の土塁の彼岸花は、咲き始めた株が、全体の1、2割程度、一方、宝戒寺は、紅も白もまずまず咲いていた。さて、瑞泉寺はどうか。
はい、”まずまず組”でした。ほらね。

この、夢窓疎石の作庭の石庭前の彼岸花も。

夢窓疎石といえば、横浜の歴博で展覧会が開催されている。吾輩は行く予定でごわす。

瑞泉寺といえば、芙蓉も有名。花のつきはもうひとつだったけれど。

今秋の鎌倉観光のポスターは瑞泉寺でごわす。ピンク色の秋明菊が主役。

こんな、写真を撮りたかったが、ピンクはわずかに残っている程度、白いのがようやく咲き始め。

でも、想定外の事態も発生。冬桜が開花。水戸黄門さまお手植えの桜でごわす。ぼけたのかな。


ぼけた木もいました。


・・・
宝戒寺にて
紅白曼珠沙華

コミカルなミュージカル映画は、心をうきうきさせてくれる。

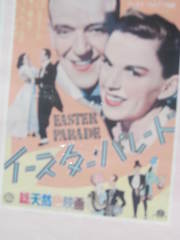
今日のお天気は崩れそう。女子オープン、最終日は行かないことにした。中秋の名月もむづかしそう。

















