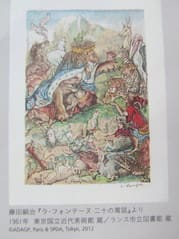暑さ寒さも彼岸まで。そろそろ秋がきてもらわないと。
草冠に秋、萩。文字通り秋の花が咲き始めた鎌倉。海蔵寺、淨光明寺&英勝寺をめぐってみた。
海蔵寺
山門前の萩

境内の萩


紫苑も咲き始めた。


コムラサキも色づいて

海蔵寺は初秋の風情だった。

淨光明寺
萩は咲いたか、彼岸花はまだかいな。まだでごわす。萩はOKでごわす。


楊貴妃観音さまは反日ではなかった。うれしか。

淨光明寺も初秋の風情だった。

英勝寺
ここも、萩は咲いたか、彼岸花はまだかいな、だった。
境内の萩

苔緑がビロードのようだった。

竹林

竹林でみつけた姫御殿跡。ここは尼寺でやんす。

英勝寺も初秋の風情だった。

寿福寺も初秋の風情だった。

大船の花屋さんも初秋の風情だった。友禅菊。

草冠に秋、萩。文字通り秋の花が咲き始めた鎌倉。海蔵寺、淨光明寺&英勝寺をめぐってみた。
海蔵寺
山門前の萩

境内の萩


紫苑も咲き始めた。


コムラサキも色づいて

海蔵寺は初秋の風情だった。

淨光明寺
萩は咲いたか、彼岸花はまだかいな。まだでごわす。萩はOKでごわす。


楊貴妃観音さまは反日ではなかった。うれしか。

淨光明寺も初秋の風情だった。

英勝寺
ここも、萩は咲いたか、彼岸花はまだかいな、だった。
境内の萩

苔緑がビロードのようだった。

竹林

竹林でみつけた姫御殿跡。ここは尼寺でやんす。

英勝寺も初秋の風情だった。

寿福寺も初秋の風情だった。

大船の花屋さんも初秋の風情だった。友禅菊。