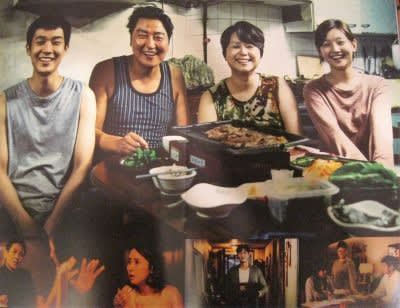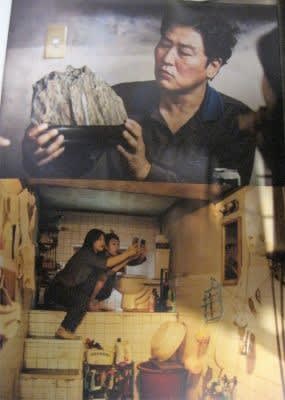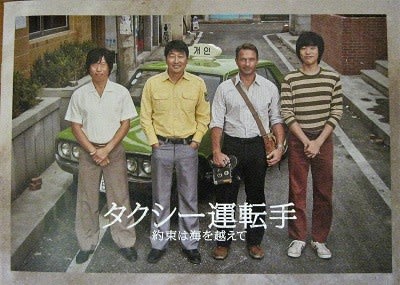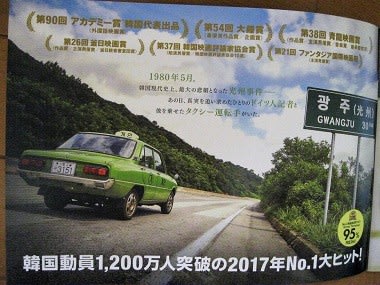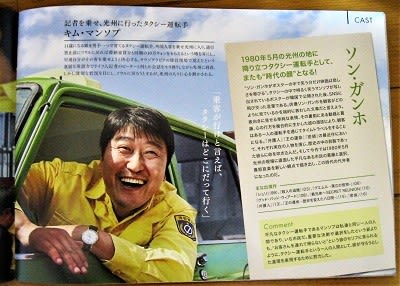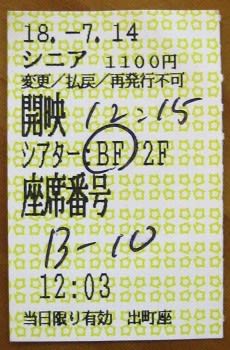YouTubeで1936年制作の映画「有りがたうさん」というのを見ました。
上の画面か、上の青い文字「有りがたうさん」の文字をクリックすると、視聴できます。
幾つもの村を通り抜けて、峠を二つ越えて山道を走る路線バスの「ロード・ムービー」です。
道普請の人たち、馬で荷を運ぶ人たち、道で遊ぶ子らが、バスが通れるように脇によけてくれる。
そのたびに運転手さんは右向いて、左向いて「ありがとう、ありがとう」と声をかけます。
それでいつか「ありがとうさん」と呼ばれるようになった運転手さんが主人公です。

着物と洋服、髪型もいろいろ、身の上も年齢も様々な人が乗り合わせ、少しだけ言葉を交わす。
みんなとてもゆっくりしゃべるのが印象的です。
まだ幼さが残る娘がやむなく峠を越えて東京へ行くらしい。
僅かの会話から、つらい事情が想像されます。
心がゆれる運転手は「峠を越えて行った者は戻ってこない・・・」と言います。
髭の滑稽な紳士も出てきます。

バスが行く村々の風景、暮らしの姿も、今では消えてしまったものが沢山登場して、
とても興味深く見ました。

脚本・監督の、清水宏(1903年生~1966年没)の暖かな目とオール・ロケへの意気込みを感じる作品です。
*****************************
古い映画をユーチューブで、無料で、随分と見ることができます。
画面が見えにくいのもありますが、きれいなのも多くあります。
暇な時にいろいろ探ってみようと思います。
清水宏監督の他の作品もたくさん上がっています。
楽しみが増えました。